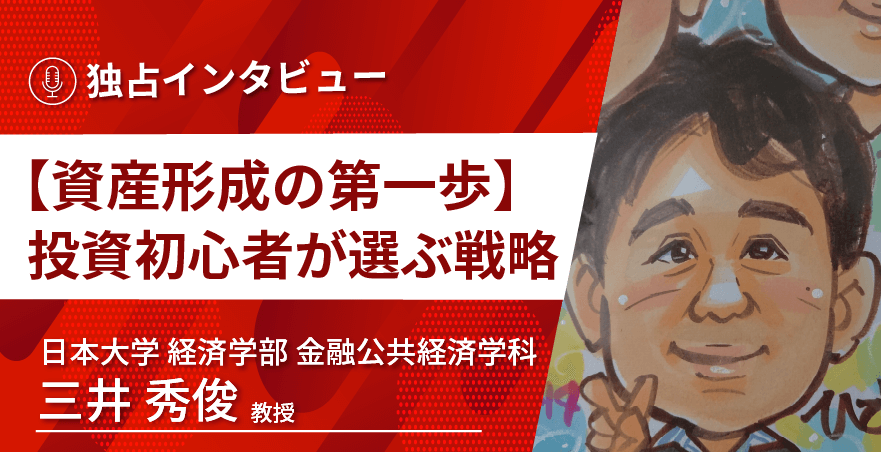近年、「老後2000万円問題」を皮切りに投資を始める方が増えてきています。しかし、投資に伴うリスクやその向き合い方について知っている方は多くないのではないでしょうか。
そこで今回、日本大学の三井秀俊教授に、資産形成を始める前にどのような準備を整えておくべきかについて独自取材を通じてお話を伺いました。
リスクとの向き合い方、そして投資を始める前に本当にしておくべき必要なこととは何かについて、三井教授のお話から探っていきましょう。
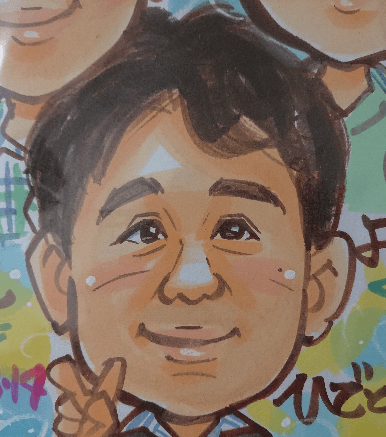
日本大学 経済学部 金融公共経済学科
三井秀俊(ミツイ ヒデトシ) 教授
東京都立大学経済学部経済学科を卒業後、同大学社会科学研究科にて博士(経済学)を取得。
2002年より日本大学経済学部専任講師、2007年より同大学准教授、2015年より現職に至る。
埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 客員教授
〈研究分野〉
人文/社会・金融・ファイナンス・金融計量経済学
〈著書・論文〉
「Trend Analysis of the Nikkei Stock Average under Japan’s Low Interest Rate Policy」(2024年)
「Time Series Characteristics of the ChiNext Board Index and the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index in China’s Growth Enterprise ,Market」(2023年)
「Bayesian Estimation of a Stable Distribution Using the Hamiltonian Monte Carlo Method with Application to Stock Indices」(2023年)
資産形成の出発点──投資初心者が最初に押さえるべきこと
カードローンの窓口合同会社 編集部:近年、「老後2000万円問題」や物価上昇といった社会背景や将来への不安から資産形成に関心を持つ方、実際に始めている方が増えていると感じています。
そこで、投資初心者の方が資産形成を始める前に、どのような準備を整えておくべきか教えていただけますか?
三井教授:まずは前提からお話しますが、投資と一口に言っても、いろいろな手段があります。
昔からあるのは不動産と株式ですが、最近はFX(外国通貨証拠金取引)やCFD(差金決済取引)、暗号通貨といった選択肢も増えています。
他にもさまざまな資産運用手段がありますが、私の個人的な意見としては、やはり伝統的な投資手法である不動産と株式が、一般の個人投資家にとって最も適していると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。選択肢が増える中でも、伝統的な投資手法が良いとされる理由について、もう少し詳しく教えていただけますか?
三井教授:理由としては、伝統的な手法には長い年月をかけて蓄積された知見があること、そしてリスクや問題点についてもある程度明らかになっていることの2点が挙げられます。
例えば、先ほど挙げた暗号通貨や先物、オプションといった新しい投資手段は、日本ではまだ歴史が浅いのです。先物やオプションは50年弱、暗号通貨に至っては十数年程度の歴史しかありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、比較的新しいものには未知のリスクも多そうですよね。
三井教授:はい。その点、不動産や株式には長い歴史があり、過去のデータの蓄積や失敗事例も豊富です。投資の基本を学ぶには、こうした堅実な分野から入るのが良いかと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:納得しました。ただ、不動産は金額的なハードルが高い印象もあります。
三井教授:そうですね。不動産投資はどうしてもまとまった資金が必要になるので、個人が気軽に始めるには少し難しいところがあります。
そのため、投資初心者の方は株式から始めるのが現実的だと言えるでしょう。
もちろん、どこに投資するかはご自身でしっかり勉強して判断していただく必要がありますが、やはり最初のステップとしては適していると思いますよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。では、投資を始める1つ目のステップは「株式投資を学ぶ」ことになるのですね。
三井教授:はい。昔からある手法は、それだけで信頼に値するものだと思います。これは投資に限らず、他の分野にも共通することかもしれませんね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:おっしゃる通りだと思います。では、株式投資を学ぶにあたって、どのような方法で学び始めるのが良いのでしょうか?
三井教授:基本は「本」から入るのが良いと思います。繰り返しになりますが、株式投資には長い歴史があります。
その分、質の高い書籍が数多く出版されているので、インターネットを使って学ぶよりも書籍を用いるのがおすすめです。初心者向けの定番本もありますから、まずはそういったものを手に取るのが良いですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、インターネットは情報が氾濫しているので、本の方が適しているというのはその通りですね。
三井教授:はい。ただし、注意していただきたいのが、出版されている本のうち、正直なところ9割はあまり参考にならない内容で、残りの1割こそが本当に役立つということです。
数多くある書籍の中から、自分に合った信頼性の高いものを選ぶのが、投資を学ぶ上でも大切ですよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。では、勉強が終わり実際に投資をする段階に入った際、初期費用としてどのくらいの金額を用意しておけば良いのでしょうか?
三井教授:前提として、初期費用に関しては個人によるとしか言えない部分もあります。
その上でお話しするなら、株式投資に関して最近は昔と違ってまとまった大金が必要ではなくなったと言えるでしょう。
例えば、投資信託やミニ株、それから米国株のように1株から購入できるものもあります。そのため、数万円の資金でも株式投資は十分に始められるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:数万円であれば、かなり気軽に始められそうですね。
三井教授:そうですね。そういった意味でも、株式投資は初心者が入りやすい投資分野だと思います。大学生など、若い方でもチャレンジできるのはメリットの1つと言えるでしょう。
ただし、ここで1つお話しておきたいのが、「世代によって資産形成の優先順位は変わる」ということです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:資産形成の優先順位ですか?
三井教授:はい。個人的な考えにはなりますが、私は資産形成を始める前に「自分自身に投資すること」が大切だと考えています。
例を挙げるなら、大学や大学院に進学する、仕事に必要な資格を取るといったことが「自分自身への投資」と言えるでしょう。
こうした自己投資は、将来的に大きなリターンに繋がる可能性があります。
実際、株式の配当利回りや資産の成長と比較しても、若い人が自分に投資して得られる成長の方が、はるかに大きなリターンになります。
ですから、若いうちは無理に資産形成にこだわるのではなく、まず自分の基盤をしっかり作ることを優先していただきたいです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、「資産形成のために大学に行かない」などとなると、本末転倒ですよね。
三井教授:その通りです。お金がもったいないから大学や大学院に行かない、資格を取らないといった選択をしてまで投資を始める必要はありません。
簡単に言うなら、「株式投資を始める前に他にやるべきことはないか?」ということを考え直してほしいのです。
とはいえ、生活費を確保し、自分への投資もしっかり行った上で、少額からでも資産形成を始めたいというのであれば、若いうちから始めるのはもちろん良いことです。資産形成の勉強にもなりますし、時間をかけた分、資産を増やせます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。その辺りのバランス感覚は、これから資産形成をしたいと考えている方にとって非常に重要なポイントになっていきそうですね。
話は変わりますが、資産形成では「リスク管理を徹底すること」が非常に大事だとよく耳にします。実際、投資における1番のリスクとはどのようなものなのでしょうか?
三井教授:難しい質問ですね。というのも、投資経験のある人と初心者とでは、前提としている感覚がまったく違うのです。
今回は学生や一般の方向けということで、「投資と普段の買い物の感覚の違い」を例に考えてみましょう。
例えば、スーパーやデパートで同じ商品が1~2ヶ月程度で2倍、3倍になることは、ほとんどあり得ませんよね。反対に、1/2や1/3に値下がりすることもほとんどありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、日常生活でそのように大きな変動が起きることはまずないと思います。
三井教授:その通りです。しかし、株式投資の世界では、そんな大きな変動が「普通」なのです。
半年で価値が半分になることもあれば、逆に2倍になることもある。その値動きの大きさは、日常の感覚とはまったくの別物です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、その前提が理解できていないと、リスク管理どころの話ではないということでしょうか?
三井教授:はい。投資では、リスク管理以前に値動きにパニックになってしまう方が非常に多いのです。
例えば、新NISA制度は岸田前総理が勧めていたこともあって注目を集めていますよね。これも、去年 (2024年) からの円高の影響もあり、資産価値が1~2年で20~30%下がってしまったケースも少なくありません。
こう聞くと、あまりの値動きに驚いてしまう方もいるかもしれませんが、投資の世界ではそれが「普通」なのです。
繰り返しますが、株式投資では半年で半分、1年で2倍になるというのは日常的に起こることであり、それを前提にして株式投資を始めなければいけません。
よく言われる「リスク管理の甘さ」は、多くの方がその現実を知らないまま投資をスタートしていることに起因しているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:それは肝に銘じておかなければいけませんね……。
三井教授:「投資は余剰資金でやりなさい」というのも、これが関係しています。
余剰資金で投資をするというのは、株を買ったとして、それが半年~1年で1/3、1/4に下がっても平気ということです。
多くの方は、この「下がる前提」の感覚がないまま投資をしているので、非常に危険です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。上がる期待だけ持って投資を始めてしまう分、下がった時の衝撃が大きくてパニックになってしまうのですね。
三井教授:そうです。1年で2~3倍になることがあるというのは、裏を返せば1年で1/2や1/3になるリスクもあるということです。
それを冷静に受け入れることが、リスク管理において最も大切な視点と言えるでしょう。
なお、これらと比較すると、不動産投資は比較的価格のブレが小さいと言えます。株のように短期間で2倍や1/2になることはあり得ません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、不動産はそういった意味では非常に安定している印象があります。
三井教授:はい。そのため、ある程度まとまった余剰資金があって、激しい値動きに心を乱されたくないという方は、不動産投資が向いていると思います。
要するに、「株式投資では人生で経験したことのないような価格変動が起きる」ということを忘れないでいただきたいのです。今回お話しした前提を理解した上で、自分の許容できる範囲で投資を始めてほしいですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:おっしゃる通りだと思います。私自身、利益を得る方向ばかりに視線が向いて、リスクから目を逸らしている部分があるような気もして、少しドキッとしました。
三井教授:そうですね。そもそも、投資という字は「資を投げる」という言葉で構成されているのを今一度認識していただければと思います。
多くの人は、投資と言うとどうしても甘い側面、つまり「儲かる話」ばかりに目が向いてしまいがちです。
しかし、それは投資の本質ではありません。実際には、儲かることがあれば、同じくらい損をすることもあります。それが商取引の基本なのです。
まずは、良い話ばかりではなく、リスクにも目を向け、前提をきちんと学ぶ。これが投資を始める上で大切になるでしょう。
インデックス投資とアクティブ投資──初心者が選ぶべきなのは?
カードローンの窓口合同会社 編集部:投資について調べていると、「インデックス投資」と「アクティブ投資」という言葉を目にすることがあります。この2つの違いについて、初心者にも分かりやすく教えていただけますか?
三井教授:まず、インデックス投資というのは、株価指数に連動する投資信託のことです。代表的なものとしては、株価指数連動型ETF(上場投資信託)があります。
日本であれば日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)、アメリカであればダウ平均やS&P500などの株価指数に連動するように設計されたファンドです。
一方、アクティブ投資というのは、個別銘柄などをファンドマネジャーが選び、タイミングを見て売買する投資スタイルを指します。一般的には、「市場平均以上のリターンを目指して積極的に投資すること」とも言われていますよ。
そんな2つの投資のうち、インデックス投資は実は初心者に限らず、多くの投資家にとって「最適な投資」と言われています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「最適な投資」というのは、一体どういうことでしょうか?
三井教授:「最適」というのは、手間が少なく、分散効果が高くて、コストも安いという意味です。
株価指数は常に見直されています。例えば、日経平均は日本を代表する225社で構成されていますが、これはずっと同じ会社ではなく、毎年、構成銘柄の見直しがあるのです。
つまり、日経平均連動型のETFを買うということは、常に「旬の日本企業225社」に分散投資しているようなものなのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:それは、個別銘柄を買うより効率的ですね。
三井教授:その通りです。アメリカのダウ平均やS&P500も同様で、今現在最も活力のある企業の集合体となっています。
だからこそ、こういったインデックスファンドに投資するのが「最適」だと言われているのです。
もちろん、「最適」だからと言って、必ず儲けられるわけではない点は誤解しないでいただきたいですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、「最適」と「確実に儲かる」は別物ですね。
三井教授:はい。また、インデックスファンドは対象となる株価指数をそのまま買っているようなものなので、選ぶ側の負担が少ないというメリットもあります。
これは、投資初心者の方にとっても非常にありがたい点と言えるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。序盤の方で「投資を学ぶには本が良い」というお話もありましたが、インデックス投資に関しておすすめの本はありますか?
三井教授:チャールズ・エリス氏による「敗者のゲーム」(日本経済新聞社)は名著ですね。投資信託の実態がよく分かる内容になっています。
一部内容をご紹介すると、この本では投資信託全体を見ると、実はベンチマークとされている株価指数のパフォーマンスを上回っているファンドは2割ほどしかない、という検証結果が紹介されています。
つまり、8割のアクティブファンドはインデックスに勝てていないのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そんなに少ないなんて衝撃的です。
三井教授:そうですよね。このように、「インデックス投資が最適」というのは、数学的にも証明されています。
それを踏まえると、「どのアクティブファンドが良いか」と選ぶこと自体に時間をかけるより、日経平均やS&P500などのインデックスファンドを選ぶ方がはるかに合理的でしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。では、アクティブ投資を選ぶメリットはあまりないのでしょうか?
三井教授:そうですね。アクティブファンドは、その分野に精通していて、情報収集や比較検討に時間をしっかりかけられる人にしかできないと思います。
投資信託は世界中に何千種類とありますから、普通の人には選べません。それを見極めるのは、個別株を選ぶより難しいくらいです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:アクティブ投資をできるのは、専門家くらいなのですね……。となると、やはり初心者はインデックス投資が無難ということになりますね。
三井教授:その通りです。新NISA制度でも、日経平均やS&P500などの株価指数連動型ETF、あるいはオルカンと呼ばれる世界分散型の投資信託が推奨されています。そうした選択なら、基本的に間違いはありません。
ただ、それらには為替リスクという落とし穴がある点にも注意が必要です。
特に、アメリカや全世界株式の投資信託に投資した方は、昨年(2024年)の夏からの円高で為替差損が出ているケースも多くあります。株価が上がっていても、円に換算すると目減りしてしまうこともあります。
つまり、「株が上がった=儲かった」ということには、必ずしもなりません。海外資産に投資する場合には、こういった為替変動によるリスクもセットで理解しておくと良いでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:実は私も、新NISAの制度に乗っかる形で、とりあえずオルカンを買ってみたのです。現に資産は減っている状況ですね。
三井教授:そうなのですね。とはいえ、オルカンやS&P500などに投資するのは、間違いではありませんよ。銘柄構成も優れていますし、分散効果も高いです。
ただ、特に日本の場合は「円高リスク」に注意した方が良いでしょう。これは他国とは違う、日本特有の要素です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:円高リスクですか?
三井教授:よく誤解されがちなのですが、もともと円は「強い通貨」なのです。
たまたまここ数年は円安が進みましたが、長いスパンで見ると先進国通貨としての安定性があります。つまり、いずれ円高に戻る可能性があるわけです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、最近の円安続きでその感覚はなかったかもしれません。
三井教授:そこなのです。先ほどもお話しましたが、為替リスクを十分に考慮しないままオルカンなどの海外資産に投資すると、株価が上がっても為替差損で結果的に資産が目減りすることもあり得ます。
あえて言うなら、他の通貨圏の方がオルカンに投資する場合は、そこまで神経質になる必要はないかもしれません。
しかし、日本の個人投資家であれば、円という通貨の性質と、それが持つ為替変動リスクをしっかりと考慮する必要がありますよ。
やはり円は世界的に見ても信用度の高い通貨です。長期的には円高方向に動く可能性は常にあると思っていた方が良いですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。今のお話からすると、やはりインデックス投資の方が現実的な選択なのですね。
三井教授:はい。初心者が長期的に資産形成を目指すのであれば、やはりインデックス投資が適していると思います。
それともう1つ、よく誤解されるのが「株と為替、どちらのリスクが高いか」という点です。実は株の方が変動幅は大きいのですよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうなのですか?なんとなく為替の方がリスクの高いイメージがありました。
三井教授:そういう印象を持っている方は多いですね。
最近のFXに対する報道の影響もあってそういった印象があるのかもしれませんが、実際には個別株の方が値動きは激しいのです。
最初の方でもお話ししましたが、株式は1年で2分の1、あるいは2倍3倍になることも珍しくありません。一方、為替が1年で半分になるなんてあり得ないのです。
例えば、今のドル円は146~147円くらいですよね。ピークは約161円95銭だったので、下落幅にすると、約1割程度になります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、数字にしてみると、個別株の方がはるかに値動きの大きいことが分かりますね……。
三井教授:はい。さらに言えば、レバレッジをかけずにドルを買って持っていれば、年利で4%前後のスワップポイントがもらえます。
円高で1割程度の為替差損が出たとしても、スワップや利息で差し引き6%前後の下落で済むのです。こう考えてみると、実はFXもそこまで大きなリスクがあるわけではないことが分かりますよね。
むしろ、株の方がよっぽど変動は大きいと言えます。それを理解しておくだけでも、リスクに対する感覚はだいぶ変わると思いますよ。
金融リテラシーと資産形成──教育現場・家庭・社会の役割とは
カードローンの窓口合同会社 編集部:お話を伺う中で、自分自身もリスク意識の甘さなどを痛感しました。情報に踊らされるまま投資をするのは本当に危険なのですね。
こういった金融リテラシーが不足していることで起きやすいトラブルなどがあれば教えていただけますか?
三井教授:そうですね。まず、前提からお話したいのですが、皆さんはよく「金融リテラシーが大事」と口にしますよね。
もちろん、それが重要なのは否定しません。ただ、私が思うのは、「結局、金融というのは経済活動の一部」ということです。
ここまでお話した株取引やFXも、行っていることは商取引です。ですから、金融リテラシーも大切ですが、その前に「もう少し基本的なことを勉強した方が良いのでは」と感じています。
基本的なところというのは、経済学の基礎、特に外国為替相場や株式市場といった資本市場の構造です。
例えば、経済学にはミクロ経済学とマクロ経済学がありますが、為替は主にマクロ経済学の分野に当たります。
他に挙げるとすれば、簿記もそうですね。資本主義の基本となる複式簿記や財務諸表、会計の読み方といったものを、投資や金融を学ぶ前にぜひ勉強してほしいです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。金融リテラシーを知るためには、そもそも「金融とは?」という基本的な部分を知っておかなければ意味がないですよね。
三井教授:はい。金融に関する雑誌や書籍を読む前に、まずは土台を作ることを意識していただきたいと思います。
そうしないと、意味を誤解したり、騙されたりしてしまいますからね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:おっしゃる通りですね。序盤で三井様がお話していた「まず自分に投資しよう」という点も、ここに通じるかと思います。
三井教授:その通りです。ただ、今挙げたようなことをするのは労力や時間もかかります。
そこで私がおすすめしているのが、「今自分がいる業界について詳しく知ること」です。
例えば、小売業をしているなら小売業界のこと。不動産業にいるなら不動産業界のことをしっかりと勉強する。そうすれば、その業界における企業の株価の動きやその背景を実感として理解できるようになります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そう言われると、たしかに私たちのそばには常に経済活動がありますね。
三井教授:本当にそうです。お金に関する勉強の機会は身近なところにいくらでもあります。
しかし、皆さんはそれを飛び越えて、いきなり資産形成に走ってしまうのです。その結果、詐欺などの被害にあうことも少なくありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:耳が痛いお話です。目先の利益にかられて、今の状況が見えていないと、甘い話に飛びついてしまいますよね。
三井教授:そうですね。これは社会人の方向けのお話でしたが、これは学生にも通じます。
学生の中には「株や企業は自分とは関係ない」と思っている人も多いでしょう。
しかし、少し考えてみてください。今日、あなたは朝ごはんに何を食べましたか?通学に何を利用しましたか?
パン、牛乳、納豆、電車、バス……すべて株式会社が関わっていますよね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、改めて言われるとそうですね。
三井教授:つまり、日常のあらゆる場面に株式会社は関わっているのです。
ですから、金融や投資を学ぶためにも、まずは身近なところから勉強した方が良いと思います。
「株で儲ける」などではなく、「自分の生活に株式会社がどう関わっているのか」を考えるところから始めた方が、よほど建設的です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:本当にその通りですね。私もそうですが、「何のためにあるのか」ということを考えず、ただ言葉や情報に踊らされてしまっていたと思います。
三井教授:多くの人がそうだと思いますよ。だからこそ、私は「まず自分に投資を」と言い続けているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。今のお話にも通じますが、金融について知るために、学校教育や家庭での会話、メディアによる情報発信などについて、今後気を付けた方が良いことがあれば教えていただけますか?
三井教授:少し言い過ぎに聞こえるかもしれませんが……。TV、新聞、ラジオ、雑誌、ネッㇳなど、ほとんどの情報は資産形成においてあまり役に立ちません。
役に立たないというより、むしろミスリードするものが多いのです。ですから、私は学生にも「マスメディアを見るより、企業が発信している一次情報を見ろ」と伝えています。
今はIR情報や財務データなどをネット上で簡単に確認できますから、それをしっかりと調べることが大切です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。簡単にまとめられた二次情報を見るより、自分の目で正しい情報を把握しようとする姿勢が大切なのですね。
三井教授:そうです。他には、信頼できる本を読んだり、実際にうまく資産形成している人の話を聞いたりするのが良いと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほど学生に一次情報を見るように伝えているというお話がありましたが、他に講義内で意識されていることはあるのでしょうか?
三井教授:はい。私は、TVや新聞の記事を題材に講義をすることはありません。「自分で役立つ情報を探せ」「一次情報を見ろ」という2つを徹底しているのです。
例えば、株を扱うなら、まずは株価の変動を見るところから。今回お話したように、株価の変動は普段の感覚とはまったく違います。それを見て、自分で体感として理解することが大事なのです。
あとは、「どこかに簡単に儲かる情報がある」とは決して思わないことも伝えています。そんな情報があったら、みんなお金持ちになれているはずですからね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:本当にそうですよね。「絶対に儲けられる」といったうたい文句のセミナーなどもありますが、それに参加するだけで儲けられるなら、投資で失敗する人はこんなに多くないと思います。
三井教授:その通りです。世界の経済成長が年に3~4%程度の現状で、投資でそれ以上の利回りを得るのは非常に難しいことです。
参考までに、トヨタの営業利益率はどれくらいだと思いますか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:20~30%程度でしょうか?
三井教授:いいえ、年によって違いはありますが、平均で10%前後です。
「世界のトヨタ」と呼ばれている企業でさえ、営業利益率はそれくらいなのですよ。
それを踏まえれば、一般の投資家が年5~10%の利益を安定的に出すのが、どれだけ大変か分かりますよね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、そうですね。投資で成功している人の情報が多く発信されているせいか、どこか宝くじ感覚で「うまく行けば良いな」程度の感覚で投資を始めている人もいそうです。
三井教授:そうですね。投資と宝くじはまったくの別物です。
ですから、しっかりと冷静に、客観的に、自分で調べて判断するところからまずは始めてみましょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:おっしゃる通りですね。「まずは自分の業界を知るべき」というお話もありましたが、私もそこから始めてみようと思います。
三井教授:はい。私もそれをおすすめします。自分の業界なら体感的に理解しやすいですし、経済や経営の知識にも繋げていけますよ。
なお、余談にはなりますが、業界の中には航空会社のように人気があり華やかなものもありますよね。そういった業界は、実は利益率が低いことも多いのです。
ですから、そういう「見た目」に惑わされず、投資の際は地味でも堅実な企業に注目してみると良いでしょう。
繰り返しにはなりますが、派手さに惑わされず、冷静に、客観的に見ること。それが投資に繋がるスタートですよ。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年7月14日