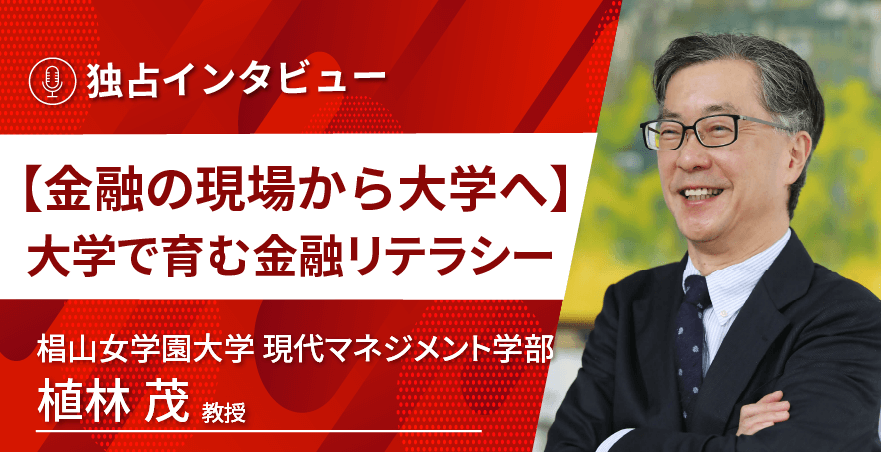社会のあらゆる場面で避けて通れない「お金」の知識ですが、日本では先進国と比べて金融リテラシーが低いと言われ、特に教育現場における金融教育のあり方が注目を集めています。
そこで今回は、日本銀行でのキャリアを経て、現在は椙山女学園大学で学生に金融を教えている植林教授にインタビューしました。
実務経験を踏まえた教育の工夫や、これからの社会で求められる金融リテラシーについてお話を伺います。

椙山女学園大学 現代マネジメント学部
植林茂(ウエバヤシ シゲル) 教授
椙⼭⼥学園⼤学現代マネジメント学部 教授/学部⻑。博士(経済学)。大学卒業後、日本銀行に入行。考査局、営業局、経済企画庁への出向、金融機構局、調査統計局等を経験した後、椙山女学園大学に着任。日本銀行時代の経験を活かし、金融論や日本経済論を教える。著書に『金融危機と政府・中央銀行』(日本経済評論社)、『日本金融の誤解と誤算―通説を疑い検証する―』(編著、勁草書房)がある。
金融の現場から教室へ―実務経験が育てる学びのかたち
カードローンの窓口合同会社 編集部:まず最初に、日本銀行でのご経験の中で、今の教育活動に特に影響を与えていると感じる出来事や視点があれば、お聞かせください。
植林教授:日銀では、審議委員(中原伸之氏)のスタッフとして金融政策を考えたり、考査(金融市場の立ち入り調査)等で金融機関を調べたり、調査統計局に所属して景気を調査・分析する仕事などをしていました。
学者や政治家を含め、さまざまな人と意見を交わす機会があり、その経験が今の教育活動に大きく影響しています。
金融というのは理論だけでは不十分で、実務だけでも理解が浅くなってしまう。両面を知っているからこそ、学生に「現実に即した金融の理解」を伝えられるのだと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。実務と学問の両方をご存じだからこそ、学生に伝えられる学びがあるのですね。
植林教授:そうです。例えば銀行の利用方法ひとつをとっても大きく変わりました。
昔は預金を引き出したり振り込みを行うときには、窓口で払戻請求書や振込依頼書などの帳票を書いてテラーのいる窓口で処理をしていましたが、今はネットバンキングを使えばスマホを使って振込までできるようになっています。
こうした身近な変化も、授業で「金融は生活に直結している」と伝える良い素材になっています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:学生に教える上で、難しさややりがいを感じるのはどんな瞬間ですか?
植林教授:難しい点は2つあります。ひとつは専門用語が多く、背景まで理解しようとすると初学者には難しいこと。
もうひとつは、金融を取り巻く環境の変化が非常に速く、知識がすぐ陳腐化してしまうことです。
たとえば、少額ローンの審査にAI、自動審査システムなどが利用されたり、また日常事務処理については業務フローを見直したうえで定型事務の処理にRPA(ロボテックプロセスオートメーション)が活用されてきています。
また多くの金融機関では、情報系システム、証券系システムなど多くのシステム分野でクラウドコンピューティングを利用するなどして金融実務の目まぐるしい変化に対応しようとしています。
こうした変化を学生に伝えるのは大変ですが、同時に面白さでもあります。
難しいと思っていた言葉がニュースや新聞で日常的に登場するものだと気づいたとき、学生の表情が変わる。それが教育の醍醐味ですね。
特に、金融政策の理論を教えるときには、机上の数式やモデルだけでなく、「政策決定の現場で何が起きていたのか」「実際にどんな判断が求められていたのか」を合わせて伝えるようにしています。
学生には「教科書で学ぶ理論が、現実の政策運営ではどう作用していたのか」を理解してほしいからです。
たとえば、2000年代のサブプライムローン問題を例に、理論と現実のズレを示すこともあります。
理論上は一見リスク分散できていたようにみえた金融商品が、実際には市場全体を不安定化させる大きな要因となった。
その背景を考えることで、「経済を読む力」や「仕組みを疑う視点」が養われるのです。
金融教育を社会の力に―国家的な課題意識と教育現場の実情
カードローンの窓口合同会社 編集部:近年、金融教育が社会的に注目されるようになっています。その背景をどのようにご覧になっていますか。
植林教授:日本の金融リテラシーは、比較の仕方にもよりますが類似のテストの点数で比較すると、先進国と比べておよそ1割低いと言われています。理由は2つあります。
ひとつは受験勉強に偏り、生活に直結する金融教育が十分でなかったこと。
もうひとつは、欧米がリーマンショックを契機に教育を強化したことです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:リーマンショックが教育強化につながったのですか?
植林教授:そうです。アメリカでは返済能力のない人まで住宅ローンを借り、バブルが崩壊すると多くの人が困窮しました。
その反省から、小学生から高齢者まで世代ごとに金融教育を行い、国民全体の知識を底上げしたのです。
日本は出遅れましたが、近年は学習指導要領に金融教育が大幅に盛り込まれ、家庭科や社会科で扱う内容が増えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:日本の金融教育における課題は、どんな点にあると感じますか?
植林教授:大きな課題は世代間の格差です。高齢者はスマホやキャッシュレスに不慣れで十分に活用できません。
これは日本だけでなく、スウェーデンのようなキャッシュレス先進国でも同じ問題が起きています。
一方で若い世代はデジタルに慣れていますが、教える側の先生が必ずしもITに強いとは限らない。教育内容にギャップが生じています。
金融教育はIT教育と不可分であり、全国的に一律の取り組みが必要になるかもしれません。
また、金融政策そのものも複雑化しています。
ゼロ金利やマイナス金利、量的・質的金融緩和、イールドカーブ・コントロールなど、新聞で頻繁に出る言葉ですが、仕組みを知らなければ理解できません。
こうした専門的な内容をどう噛み砕いて伝えるかが、今後の大きな課題です。
もう一つ重要なのは、こうした教育を通じて学生が「自分の生活や社会にどう関係するか」を考えられるようにすることです。
金融教育は、単にお金の計算を学ぶことではありません。
将来、住宅を購入したり、事業を始めたり、年金制度を理解したりといった場面で、自分の判断を支える知識になります。
つまり、社会で“生きて働く知識”として金融を教えることが大切です。
知識を生きる力へ―大学教育で育む金融リテラシー
カードローンの窓口合同会社 編集部:椙山女学園大学での金融教育には、どんな特色がありますか?
植林教授:金融入門や金融政策論などの基礎から、ファイナンス、金融リテラシー、FP資格講座まで幅広い科目があります。
J-FLEC(金融経済教育機構)との提携講座や証券会社と連携した実務的な授業も特徴的です。
ゼミ活動ではPBL(プロジェクトベーストラーニング、社会的課題に対して企業と連携して取り組む活動)として名古屋市信用保証協会と協力し、若い女性の起業支援にも取り組んでいます。
ビジネスプランコンテストで選ばれた事業に保証をつけて支援するなど、地域経済の活性化を目指す実践的な活動です。
学生が社会課題に挑むPBL(課題解決型学習)を積極的に取り入れています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:学問だけでなく、地域と連携した実践的な学びが多いのですね。
植林教授:そうですね。大学教育では、理論と実務のバランスを取ることを常に意識しています。
講義で理論を学び、PBLなどの実践を通してそれを現実の課題に落とし込む。
この往復があって初めて、知識が「生きる力」になると考えています。
学生が社会に出てからも、ニュースや政策の背景を自分で理解し、判断できるようになる。
そうした金融リテラシーを育てることが、教育者としての使命だと思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:最後に、これから社会に出る学生にどんな力を身につけてほしいとお考えでしょうか。
植林教授:金融は「生きる力」です。お金は一生ついて回るものですから、できるだけ早い時期から関心を持ち、少しずつ知識を積み重ねることが大切です。
公的年金だけでは将来を支えるのは難しいでしょう。NISAやiDeCoといった制度を理解し、自助努力が必要です。
また、世の中でデジタル化が進むことなどによって、そのままにしておくと人々の金融知識の格差は広がっていくと予想されます。
だからこそ、金融を学問としてだけでなく「社会で活かす力」として身につけてほしい。
ニュースを理解し、正しく判断し、主体的に行動できる力を養ってほしいと思います。
金融を学ぶ必要があるのは金融機関を目指す人だけではありません。すべての人に必要な知識であり、未来の自分を守る力になるのです。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年10月4日