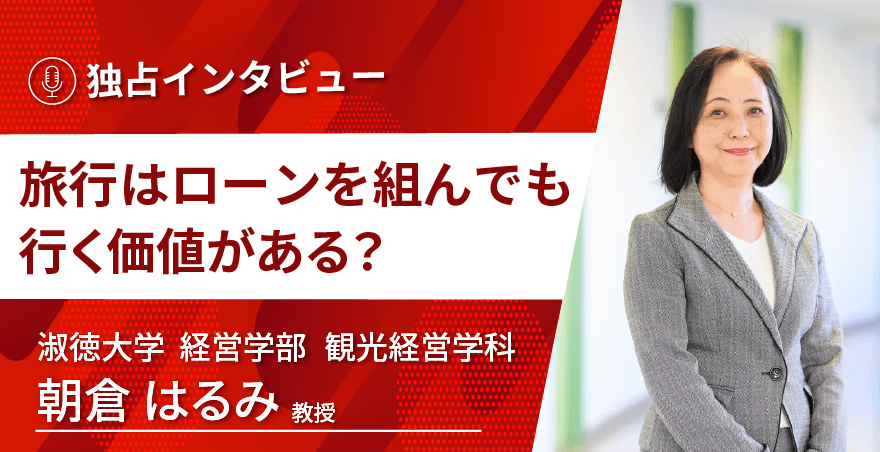「旅行に行きたいけれど費用が気になる」という方は多いでしょう。そんな中、「トラベルローン」という存在を見聞きしたことがある人もいるはずです。確かに旅行は人生を豊かにすると言われますが、借金をしてまで行くべきなのかは考えどころです。
そこで今回、淑徳大学の朝倉教授に、旅行はローンを組んでも行く価値があるのか、独自取材を通じてお話を伺いました。
経験にお金を使うことは本当に幸せに繋がるのでしょうか?それとも、後悔する可能性があるのでしょうか?インタビューを通じて旅行とお金の関係、旅行の魅力について迫ります。

淑徳大学 経営学部 観光経営学科
朝倉はるみ(アサクラ ハルミ) 教授
東京女子大学文理学部英米文学科卒業。
1987年度より財団法人日本交通公社研究調査部にて調査・研究業務に従事。
2012年度 淑徳大学経営学部観光経営学科に転職、准教授を経て、2018年より現職。
〈専門分野〉
観光マーケティング
〈論文〉
「観光地のキャッシュレス決済に関する研究―Phase 3」(2024年)
「「各地にゆかりの人物」を持続可能な観光資源として活用するための関連施設に関する基礎的研究-近畿・中国・四国地方-」(2024年)
「ヨーロッパ5都市における観光資源としての「墓地・墓所」の来訪推奨要素」(2023年)
ローンを利用する消費者層とその動機
カードローンの窓口合同会社 編集部: 最近の旅行業界ではキャッシュレス決済や分割払い、今回のテーマでもあるトラベルローンなど、支払い方法が多様化しています。
ローンを利用して旅行費用を支払う消費者層は一体どのような動機や目的があるのでしょうか?
朝倉教授:そもそもローンというのは、高額な商品を購入する時に利用しますよね。例を挙げるとするなら、自動車や住宅が一般的でしょう。
そんな中、旅行というのは円安により、かつてのような「高額商品」に戻りつつあります。特に、かつて「一生に一度のもの」と言われていた海外旅行に関しては、昔ほど極端ではないにしろ、高額な費用が掛かる状況です。
こういった状況では一括の支払いが難しくなりますから、トラベルローンを利用する消費者が増加傾向にあっても、不思議ではありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、学生などは一度に大きな額を用意するのが難しいですよね。
朝倉教授:そうですね。今は海外旅行の例を挙げましたが、日本人が自由に海外旅行へ行けるようになったのは1964年のことです。
それ以前は、将来的に海外観光旅行が自由化されることを見越した旅行会社が、消費者に「旅行積立」というものを勧めていました。
旅行積立とは事前にお金を積み立て、その資金で旅行に行く仕組みでした。その後、海外旅行にかかる費用が下がり、日本人の収入も上がったことで、多くの人が気軽に旅行へ行けるようになったのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:現代に至るまでにそのような流れがあったのですね。ちなみに、現在でも旅行積立は行われているのでしょうか?
朝倉教授:最近はあまり聞かなくなりましたね。
旅行積立は旅行会社にとっても利点があったことから、旅行会社が積極的に販売していたようです。
しかし、次第に旅行が高額商品ではなくなってきたこと、さらに旅行会社にとって積立の利息負担が利益を圧迫するようになったことが影響し、近年ではあまり耳にしなくなりました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。確かに今は「旅行積立」という言葉自体あまり聞かなくなった気がします。
ちなみに、トラベルローンでは「今すぐ旅行を楽しめる」という点がメリットとして挙げられますが、一方で後に残る経済的負担が懸念されます。消費者はローンを利用する際、どのようなリスクを感じていると思われますか?
朝倉教授:旅行は形のない商品ですから、そういった点はリスクだと思います。
例えば、車や住宅であれば、購入後も手元に残りますし、ローンを払いながら実際に使い続けることができますよね。しかし、旅行となるとそうはいきません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、旅行は体験型の商品ですから、車や住宅のようにはなりませんよね。
朝倉教授:そうですね。旅行の場合は楽しい時間を先に消費して、後からお金を払うことになります。
この「使ったものに対して後払いする」という感覚に違和感を覚える人もいるでしょう。
ただ、旅行は行って終わりというものではありません。実は私自身も大学の卒業旅行はローンを組んでヨーロッパに3週間行ったのですが、旅行には「3つの楽しみ方」がありました。
1つ目は、旅行前の楽しみ。おそらく編集部さんも、旅行に行く前にいろいろと調べた経験があるのではないでしょうか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうですね。旅行先や環境地、食べ物など、いろいろ調べてどうするかを考えていました。
朝倉教授:「どこに行こう?」「何を食べよう?」「どんな体験をしよう?」と考える時間は楽しいですよね。私もガイドブックを見るのが好きなので、計画を立てる時間はすごくワクワクします。
2つ目は、現地での楽しみ。実際に旅行先で食事をしたり、写真を撮ったり、予想していなかった発見があったりしますよね。
「こんなおいしいものがあったんだ!」とか、「こんなお土産が売ってたんだ!」といった経験です。これも当然、楽しいに決まっています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、旅行という非日常の中で新たな発見をするのは、普段とは違う感動を得られるような気がします。
朝倉教授:そうですよね。そして3つ目は、旅行後の楽しみ。
写真を見返したり、お土産を眺めたりすることで、思い出を振り返ることができます。編集部さんも、自分用にお土産を買うことはありますか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:買いますね。旅の思い出として何かしら持ち帰ることが多いです。
朝倉教授:私もそうです。大きなものではなくても、旅行先で何かしら買って帰ります。
写真を撮るのもそうですが、記録として残るものがあると、思い出がより鮮明になりますよね。
例えば、私は何十年も間に卒業旅行で海外へ行きましたが、今でもその時のことを鮮明に思い出せます。今こうして編集部さんに話しているだけでも、当時の楽しい記憶がよみがえってきます。
つまり、旅行には「行く前」「現地」「帰ってから」という3つの楽しみ方があるのです。
ちなみに、編集部さんはどうですか?もし旅行が嫌いでなければ、撮ってきた写真を見返した経験があるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部: そうですね。写真を見たりしますし、先ほどおっしゃっていたような行く前の準備も楽しみの1つです。
「何を着ていこうかな?」と考えて実際に服を買いに行くなど、準備期間の楽しさも含めて旅行が好きだと感じています。
朝倉教授:私も、一泊二日の旅行でも「どこに行こうかな?」といろいろ考えるのが楽しいです。そういう準備の時間も含めて、旅行の楽しみの一部だと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。そのような準備期間や旅行後の思い出も含めて考えると、ローンで支払う金額は単なる「旅費」ではなく、長く楽しめる旅行全体の価値として払っているのかもしれませんね。
そうすると、あまり「リスク」という風には感じにくいのではないでしょうか?
朝倉教授:そうですね。ただ、ローンの金額や返済期間によると思います。
例えば、100万円の海外旅行を全額ローンで支払う場合、それを1年で返済するのか、2年で返済するのかによって、毎月の負担額も大きく変わりますよね。
毎月10万円返済するのと5万円ずつ返済するのでは生活への影響も違いますし、負担が大きすぎると、旅行の楽しみよりも「返済のプレッシャー」の方が勝ってしまうかもしれません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、ローンの計画をしっかりと立てることが、返済だけでなく旅行を楽しむうえでも重要になりそうですね。
支払い方法の柔軟化が消費者の旅行選びに与える影響
カードローンの窓口合同会社 編集部: 近年、旅行業界ではキャッシュレス決済の普及が進んでいます。そういった支払い方法の柔軟化は、消費者の旅行選びや消費パターンに影響を与えているのでしょうか?
朝倉教授:キャッシュレス決済は、旅行においても利便性が高いですよね。
昔は旅行商品を購入するために旅行会社の店舗へ行く必要がありましたが、今はオンラインで、24時間いつでもツアーや航空券を購入できます。
これは国内だけでなく、海外旅行のパッケージツアーなどでも同様です。ツアー商品やホテルなど、さまざまな旅行商品を夜中にスマホ1つで予約できるようになりました。
このように、キャッシュレス決済の技術が発展し、旅行の購入が簡単になったことで、消費者によってはより旅行しやすい環境が整ったと言えるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:キャッシュレス決済が普及する前と後では、旅行者の数も増えたのでしょうか?
朝倉教授:旅行者の数についてのデータはありますが、「その旅行商品をキャッシュレスで購入したのか、現金で支払ったのか」という細かい調査は、私も見たことがありません。
ただ、日常生活ではクレジットカードやQRコード決済が一般化し、「カード1枚あれば、あるいはスマホがあれば、現金を持たなくても良い」という状況になっていますよね。
これは旅行においても同じで、現金を持ち歩くリスクが減ったことで、消費者にとってより安心な旅行が可能になったと言えるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、今では航空券を予約する際も「現地払い」というのはほとんど聞かなくなりました。
朝倉教授:そうですね。技術の進歩のおかげで、旅行の計画や手配がよりスムーズになりました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:旅行者にとっても、旅行会社にとってもメリットがありますよね。
朝倉教授:そう思います。旅行業界にとっても、キャッシュレス決済の普及は大きな影響を与えていますね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:では、キャッシュレス決済によって「現金を持ち歩かなくても旅行ができる」「支払いが便利で安全になった」ことが消費者の旅行の楽しさや満足度に影響を与えていると思われますか?
朝倉教授:それは大きいと思いますね。
海外旅行では、現金を持ち歩くと盗難のリスクがありますし、両替の手間もかかります。また、国によっては両替手数料が高いこともあります。
こうした負担は、キャッシュレス決済が普及したことで大幅に軽減されました。
現金を持ち歩かなくても良いというのは、旅行者にとって大きな安心材料になります。例えば、財布の中のお金を気にしながら買い物をするのはストレスですが、キャッシュレスならその心配がありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。残高を気にしてATMに行く手間がかからないというのは大きなメリットですね。
朝倉教授:私も、旅行中は「いくら残っているか」を気にしながら買い物をするのが嫌なので、キャッシュレス決済ができるなら、そちらを利用することが多いですね。
また、キャッシュレス決済が普及することで、旅行者の消費額が増える可能性もあります。「現金が足りないから買えない」という状況が減れば、より自由に買い物ができるようになるからです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ただ、キャッシュレス決済が進んでいない地域もまだありますよね。特に国内の観光地では、現金払いのみの場所も残っていると思います。そういった地域では、今後どのようにキャッシュレス決済が普及していくのでしょうか?
朝倉教授:最近では、地方の観光地の飲食店や土産店でもキャッシュレス決済が増えてきていますね。特に、QRコード決済は導入コストが低く、ポイント還元もあるため、消費者にも店舗側にもメリットがあります。
ただし、小規模な飲食店や土産店では、クレジットカードの手数料負担が大きいため、「現金払いのみ」としているところもあります。この流れはすぐには変わらないのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。店舗側にとっては手数料が負担になることもあるわけですね。
朝倉教授:そうですね。ただ、経営者が代替わりすることで、一気にキャッシュレス化が進む可能性もあります。
また、QRコード決済はクレジットカードに比べて手数料が低いことから、最近では「現金 or QRコード決済のみ」というお店も増えてきています。
このように少しずつキャッシュレス決済の選択肢が増えていけば、旅行者もお金を使いやすく、観光地もハッピーになれるのではないかなと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:消費が増えることは観光地にとっても大きなメリットですよね。まだまだ課題は残っているとは思いますが、少しずつキャッシュレス化が進んでいくことを期待したいです。
ローンを組んでも旅行に行く価値を感じるための条件とは
カードローンの窓口合同会社 編集部: そもそもローンを利用して旅行を楽しむ場合、消費者が「旅行に行って良かった」と感じるためには旅行業界がどのような施策を講じるべきなのでしょうか?
朝倉教授:まず根本的な問題として、「旅行のためにローンが組める」ということ自体を知らない消費者が多いのではないかと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうですね。私も詳しいことについてはあまり知りませんでした。
朝倉教授:旅行会社はネットなどで様々な旅行商品を紹介していますが、旅行代金が高額な場合は「ローンも利用できますよ」と提案することがあります。
ただ、消費者がオンラインで旅行を申し込む段階になると、ローンをセットで勧めるのは(画面上では)なかなか難しいのではないかと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、そういう場面はあまり見かけないですね。
朝倉教授:住宅や車のローンであれば、テレビCMでも積極的に宣伝されていますよね。
「住宅ローンでマイホームを購入しました」「車をローンで買いました」というのは一般的な話ですが、旅行のローンについては、旅行業界全体でほとんどPRされていないのではないでしょうか。
売る側が発信しなければ、消費者も「そんな支払い方法があるのか」と気づかないですよね。
ですから、まずは「旅行ローン」という選択肢があることをもっとPRするのも1つの方法かもしれません。
また、円安の影響で海外旅行が高額になってきていることを考えると、支払い方法の多様化を進めることも必要だと思います。
SNSでの情報発信が当たり前になった今、旅行ローンの存在を知っている人が増えれば、利用する層も広がるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、ローンがあると知っていれば旅行の選択肢が広がるかもしれませんね。
朝倉教授:もちろん、円安の影響を受けない国内旅行にも魅力的なプランがたくさんありますし、コロナ禍が収束した今、多くの人が再び旅行を楽しめる環境になっています。
旅行が「人生を豊かにする商品」の1つとして、もっと選ばれるようになると良いですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほどお話にあったように、旅行業界はあまりローンの利用を推奨するようなCMを打っていませんよね。これは、旅行業界自体がローン利用を積極的に推進していないということでしょうか?
朝倉教授:それもありますが、やはり広告費がかかる点が大きいと思います。
そのため、旅行会社としてはゴールデンウィークや夏休みなどの繁忙期にスポット的にCMを打たざるを得ないという形なのではないでしょうか。
また、消費者側も「旅行のためにローンを組むのは恥ずかしい」と思う人もいるかもしれません。
例えば、「家/車を買うためにローンを組んだ」と言っても、特に珍しいことではないですが、「旅行のためにローンを組んだ」と言うと、少し違和感を持たれる可能性もありますよね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、ローンで旅行に行くことは、あまり一般的には認識されていないかもしれません。
朝倉教授:旅行ローンが一般的でない分、「ローンを組んでまで旅行するなんて…」とネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし、旅行が人生にもたらす価値を考えると、「ローンを活用してでも行く価値がある」と思う人も増えてくるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。続いて最後の質問になりますが、朝倉様が現在取り組まれている「各地の偉人に関する施設の活用」について詳しく伺いたいです。
この研究は、観光業や消費者行動とどのような関連性があるのでしょうか?
朝倉教授:そうですね…。編集部さんは大河ドラマをご覧になりますか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:私はあまり見たことがないですね。
朝倉教授:私も熱心に見るわけではないのですが、大河ドラマは毎年話題になりますよね。
そして、大河ドラマの登場人物にゆかりのある場所には、「大河ドラマ館」という観光施設が作られることが多いのです。
この施設はドラマの放映期間だけ、つまり1年間だけ存在します。既存の施設を活用することもあれば、期間限定の建物を新しく立てて、そのドラマの紹介を行うこともあります。
このような大河ドラマに取り上げられる人物は、全国的に有名な偉人が多いですよね。しかし、全国には「教科書には載らないけれど、地元で愛されている英雄」が必ずいるはずです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、地域ごとに知られざる偉人がいるということですね。
朝倉教授:そうです。
そういう視点で日本全国の市町村を調べてみると、一般的にはあまり知られていない人物に関連する施設が数多く存在していることが分かりました。正直、私もそれまで全く聞いたことのない人物の記念館を見つけることが多かったですね。
例えば、ある県には知事の資料館があったり、日本で初めて石油採掘に貢献した「アラビア太郎」と呼ばれる人物の記念館があったりしました。
こうした偉人たちは、全国的な知名度はなくても、日本の歴史や社会を支えてきた存在です。しかし、そうした記念館や資料館がなければ、偉大な人物も、時が経つにつれて忘れられてしまうことも少なくありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、その土地について詳しく調べなければ、そうした偉人の存在やその人にまつわる施設を知る機会はないかもしれません。
朝倉教授:そうですね。私がそうした施設の入場者数を調査したところ、毎年一定の入場者数を維持している施設も見られました。
もちろん、大河ドラマ館のように何万人、何十万人と訪れるわけではありませんが、それでもその偉人について知るために足を運んでいる人々がいるわけです。
例えば、坂本龍馬の資料館は高知県以外にもいくつか存在します。そのため、高知県の資料館は全国的に見ても特別な施設ではないかもしれません。
しかし、市町村単位で考えると、「ここにしかない」貴重な施設になります。つまり、その人物について知りたければ、ここに来るしかないということです。
このように、研究を通じて地域独自の観光施設がいかに貴重な存在であるかを再確認しました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。私の家の近くにも地域の偉人に関する施設がありますが、あまり観光客が訪れている印象がありません。実際、こうした施設には、観光客も訪れているのでしょうか?
朝倉教授:実は、観光客がどれくらい訪れているのかは、正確には分からないことが多いのです。
というのも、こうした施設では入館者数は記録しているものの、訪問者が地元の人なのか、学校の団体なのか、それとも観光客なのかを分けて集計していないケースがほとんどだからです。
例えば、編集部さんの近くの施設では、入館時に「どこに住んでいますか?」と聞かれますか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:いいえ、聞かれません。
朝倉教授:そうですよね。つまり、データ上では観光客の内訳(居住地)は分からない場合が多いのです。
また、県や市町村がこうした施設を管理している場合、「観光課」ではなく「教育委員会」のケースも多くあります。
そのため、施設の役割が「観光資源」ではなく、「地域住民の教育施設」として認識されてしまっているのです。その結果、積極的なPRが行われないままになってしまうことが少なくありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、そうなのですね。確かに、そういった施設は観光目的というより、小中学校の校外学習などで利用されるイメージがある気もします。
朝倉教授:ですから、こうした施設が観光課や商工会などと連携し、「地元にはこんな偉人がいて、こんな施設があります」とPRしていくことが重要だと考えています。
施設の管理者が観光関係の部署と協力し、積極的に情報を発信することで、より多くの観光客に訪れてもらえる可能性が高まるでしょう。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年1月23日