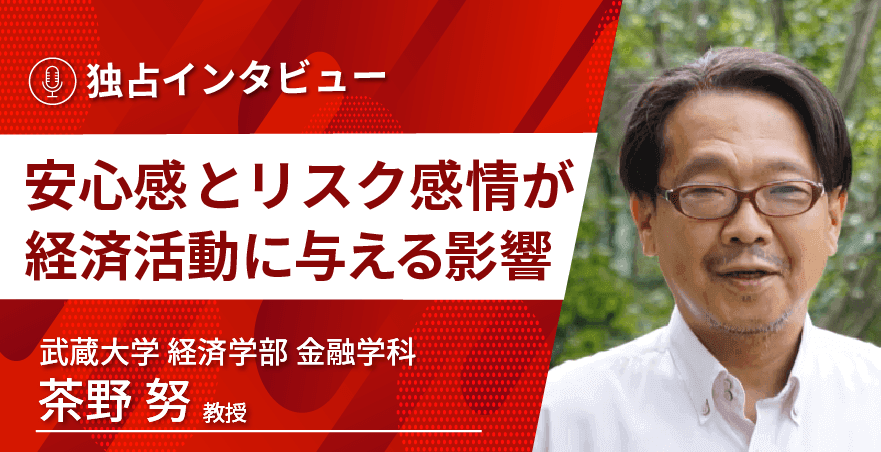私たちの経済活動には、常に「安心感」が伴っています。安心感がないものに対して、私たちは商品を購入したり、投資を行ったりすることはないはずです。
そこで今回、武蔵大学の茶野努教授に、安心感は経済活動にどのように影響するのか、信頼感やリスク感情も含めた経済学について独自取材を通じてお話を伺いました。
これからの将来に向けたリスクとの向き合い方、そして安心感がいかに経済において重要なのかを、茶野教授のお話から紐解いていきましょう。
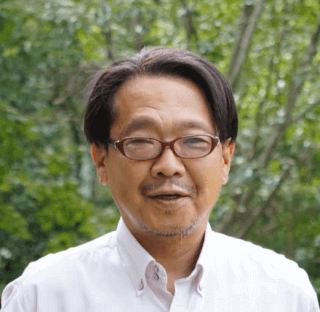
武蔵大学 経済学部 金融学科
茶野努(チャノ ツトム) 教授
大阪大学経済学部を卒業後、
同大学大学院国際公共政策課にて博士(国際公共政策)を取得。
1987年に住友生命保険相互会社に入社後、1999年より九州大学経済学部にて客員助教授(任期2年)に就任。
2008年に住友生命保険相互会社を退職後、現職に至る。
〈研究分野〉
金融論・リスクマネジメント論
〈著書・論文〉
「女性は男性よりもリスク回避的か?」(2024年・共著)
『保険と金融から学ぶリスクマネジメント』(2024年・共著)
『基礎から理解するERM─高度化するグローバル規制とリスク管理─』(2020年・共編著)
『日本企業のコーポレート・ガバナンス』(2020年・共編著)
『日本版ビッグバン以後の金融機関経営』(2019年・共編著)
”安心”と”リスク”はどう経済行動に影響するのか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:一般消費者が商品を購入したり、投資を行ったりする際、「安心できるかどうか」が選択の判断材料になることが多いように思います。この「安心感」や「不安感」について、経済学ではどのように捉えられているのでしょうか?
茶野教授:そのご指摘は、経済学で広く知られている「アカロフのレモンプロブレム」と深く関係しています。
これは、売り手と買い手の間で情報の格差、つまり「情報の非対称性」が存在することで、市場が適切に機能しなくなるという問題を指すものです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「情報の非対称性」とは、具体的にどのような状態なのでしょうか?
茶野教授:例えば保険の場合、加入者は自分の健康状態をよく分かっているけれども、保険会社はそれを把握できませんよね。こうした情報格差がある状況が、まさに非対称性の典型例です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、自分の健康については保険会社よりも本人の方が分かりますね。
茶野教授:そうですよね。古典的な経済学では、市場に任せておけば価格が適正に決まり、優良な商品や業者が自然に残るという「市場原理」が働くという思想が基本にあります。
ただ、情報の非対称性があると、そうした原理がうまく働かず、結果として粗悪な商品ばかりが市場に残るという逆転現象が起こるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:悪い商品だけが残るのは、なぜなのでしょうか?
茶野教授:仮に、健康な人は月1万円、病気を抱えた人は月3万円の保険料が妥当だとします。しかし保険会社は加入者の状態を判断できないため、平均を取って月2万円に設定したとしましょう。
すると健康な人は「高すぎる」と感じて加入を控え、病気を抱えた人は「安く入れる」と判断して加入してくるはずです。
その結果、保険会社にはリスクの高い加入者が集まり、採算が取れなくなるという構図が生まれます。
このように、価格設定が平均化されたことで、質の高い消費者が市場から離れてしまうという現象が生じてしまうのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。つまり、お互いが「これは安心できる、良い商品だ」と信じられる環境を作ることが、市場の安定には欠かせないということなのですね。
茶野教授:おっしゃる通りです。アカロフやスティグリッツといったノーベル経済学賞受賞者たちもこの問題を研究していて、「情報の非対称性があると、市場は必ずしも良い方向には進まない」ということを明らかにしています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:では、市場を健全に保つためには、「不安」はできるだけ排除すべき要素と考えて良いのでしょうか?
茶野教授:はい。取引には「信頼」が最も大切です。不安感が市場をうまく機能させるという考え方は、基本的には成立しません。
経済学では、信頼感の高い国と低い国とで、どれだけ経済に差が出るかという研究も進められています。
例えば、政治家や官僚が不正をしている国と、そうでない国を比較した場合、信頼性の高い国の方が経済成長率も高い、というデータもあります。
信頼できる制度がある社会では、市民同士が安心して取引できるため、経済活動も活発になります。逆に、取引相手や制度に不安を感じるような社会では、どうしても取引が控えられ、経済の成長も鈍くなってしまう傾向にあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり「少しぐらい不安があった方がいい」という見方は、経済的には逆効果だということですね。
茶野教授:はい。市場がうまく回るためには、取引に関わるすべての人が「安心と信頼」を持てる環境作りが重要です。
そうした安定的な取引の積み重ねが、結果的に経済全体の発展にも繋がっていくと考えられます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ところで、市場における安心や信頼といった感覚に関して、よく「女性は男性よりリスクを避ける傾向がある」と言われることがあります。
茶野様は以前「それは統計的に確認できない」とお話しされていましたが、現在もその見解は変わっていないのでしょうか?
茶野教授:実は、データを改めて精査し直したところ、リスク回避行動については男女差が統計的に確認できるという可能性が高いことがわかってきました。
前回の研究では、生命保険文化センターのデータを用いて、「独身」男女に限定して分析を行っており、その際は男女間でリスク回避に大きな差は見られないという結果になっていたのです。
保険加入金額や支払い保険料額の多寡をリスク回避傾向の指標として分析したところ、独身者において男女差はあまり確認されませんでした。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ということは、分析の対象を広げたことで、新たな傾向が見えてきたということですね。
茶野教授:その通りです。分析対象を既婚者まで広げ、また保険加入金額や支払い保険料額の所得に対する比率を指標として用いると結果は大きく異なりました。
婚姻状況などの条件を加味した上で再度分析を行ったところ、保険加入金額などの比率は男性より女性の方が相対的に多い傾向が見られたのです。
前回の研究では「男女間に明確な差はない」という見解を示していましたが、現在では「女性の方がリスク回避的である可能性が高い」と考えています。
もっとも、これはあくまで日本国内のデータをもとにした結論です。今後は中国をはじめとした他国との比較も視野に入れて、より広い視点で研究を進めていく予定です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:海外ではまた違う可能性もあるのですか?
茶野教授:そうですね。リスクに対する姿勢には、国民性や文化的背景が大きく影響すると考えられます。
制度や社会構造の違いも含め、各国でどのような傾向が見られるのかを丁寧に調査していくつもりです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。先ほど、独身者だけでなく、既婚者や子育て世代など分析対象を広げたことで傾向が変わったというお話がありました。
結婚や出産といったライフステージの変化は、男女問わずリスク回避傾向に影響するのでしょうか?
茶野教授:はい、その通りです。リスク回避傾向に大きく影響する要因として挙げられるのは、ライフステージも含めた「年齢」です。
一般的には、若い世代ほどリスクを取りやすく、年齢が上がるにつれてリスク回避的になる傾向が見られます。目安としては、おおよそ45歳を境に保守的な選択が増えていくとされていますが、もちろん個人差はあります。
これに加えて、結婚や出産、子育てといった家庭環境の変化があると、「家庭を守る」という意識が強く働くようになります。
そのため、年齢やライフイベントの変化は、リスク回避傾向を男女問わず強める方向に作用していると考えられるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。年齢や家庭環境の変化によって、リスクに対する態度も柔軟に変化していくというわけですね。
茶野教授:まさにその通りです。人はライフステージに応じて、リスクを取るか回避するかをバランス良く判断しながら、投資や保険といった経済行動を調整しています。
このような行動の変化を丁寧に捉えていくことが、経済学の視点からは非常に重要なのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「若年層は比較的リスクを取りやすい傾向がある」とおっしゃっていましたが、具体的にはどのような行動が見られるのでしょうか?
茶野教授:年齢別に株式などの、いわゆる「リスク資産」への投資比率を見てみると、20代や30代前半の若い世代の方が高い傾向にあります。さらには昔と比べると、近年はその傾向がさらに強まっているのです。
日本人はもともと「預金好き」と言われてきました。特に年配の方には「お金は銀行に預けておくもの」という意識が根強く、証券投資については「危ない」「騙されるかもしれない」といった不安を抱く方も多かったと思います。
一方で、若い世代にはそうした先入観が比較的少ない印象があります。
例えば、近年では新NISAのような制度が整備され、税制面での優遇措置も導入されています。そうした「安心材料」があることで、株式などのリスク資産に対しても前向きに投資しようとする動きが出てきていると感じています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:若い世代がリスク資産にも投資しやすくなっている背景には、やはり国の政策も大きく影響しているのでしょうか?
茶野教授:おっしゃる通りです。日本では今挙げたように新NISAの拡充など、自助努力による資産形成を後押しする政策が進められています。
このような資産形成が後押しされる背景には、将来の公的年金制度に対する不安があります。公的年金財政が必ずしも盤石ではないという認識が広がっている中で、「老後生活は自分で備えるものだ」という意識が高まってきているのです。
現在のように金利が低い状況において、預金だけでは資産を大きく増やすことは難しいのが現実です。
だからこそ、若いうちからリスクを分散しながら、株式などに投資して資産を形成していくという考え方が、今の時代においては重要になっています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:将来の備えとして、若いうちからの積極的な行動が求められるようになっているのですね。
茶野教授:まさにそうですね。経済政策や制度改革は人々の安心感や不安感に深く影響し、経済行動を変化させているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほど、若いうちの貯蓄がますます重要になっているというお話がありましたが、実際のデータとして、若年層の金融資産や貯蓄額は昔に比べて増えているのでしょうか?
茶野教授:必ずしも増えているとは言えないのです。
というのも、現在の日本は所得の伸びが昔ほどではありません。比較対象とする時期にもよりますが、例えば高度経済成長期には、年10%を超える経済成長率を記録することもありました。
一方で、現在の日本経済では年2%成長すれば良い方、という状況です。そのため、若い世代の所得や貯蓄額が以前より大きく伸びているかというと、そうではありません。余裕のある資金を持っている若者は決して多くないのが現実だと思います。
ただし、注目すべきは「投資への意識の変化」です。昔の同年代と比べて、現在の若い世代は、株式やFXなどのリスク資産に対する関心が高くなっています。
これは新NISAのような制度だけでなく、ネット証券の登場によって投資がより身近なものになったことも大きいです。取引手数料も下がり、スマートフォン一つで簡単に投資できるようになったことで、投資が特別なものではなくなってきています。
そのため、保有する金融資産の総額自体は増えていなくても、「危険資産に回す投資比率」──すなわち金融資産の配分構造──は、確実に以前より変化してきていると言えるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。金額の大小ではなく、意識そのものが変わってきているということですね。
茶野教授:まさにその通りです。将来に向けた備え方、あるいは不安への向き合い方が、時代とともに少しずつ変化してきているのだと感じています。
社会制度は”安心”をどう設計するか?
カードローンの窓口合同会社 編集部:近年は地震などの自然災害や、新型コロナウイルスのような大規模な感染症など、将来への不安を感じさせるニュースが増えているように思います。
そうした中で、保険や公的年金といった制度が、私たちの「安心」にどのように繋がっているのか、もう少し詳しく伺えますか?
茶野教授:はい。保険という制度は、社会の安定を支える非常に重要な役割を果たしています。
例えば、交通事故にあった場合や、住宅が火災で焼失してしまったような場合に、現状の生活を取り戻すには多額の資金が必要になりますよね。
その時、もし保険が存在しなければ、被害を受けた人は1から生活を立て直さなければいけません。しかし保険に加入していれば、損害に応じて一定の保険金が支払われ、生活の再建が可能になります。
つまり、保険とは「やり直すための仕組み」と言えるのです。
その意味で、保険は私たちの生活を支える「社会インフラ」のひとつです。もし保険という制度が存在しなければ、人々は常に不安を抱え、経済活動や日常の行動も慎重になり、社会全体が委縮する可能性が極めて高いです。
「万が一の時にも備えがある」と思えることで、行動の自由度が広がり、経済も活性化します。そうした観点からも、保険は社会の基盤を支える制度として非常に重要なのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。たしかに、何かあった時にやり直せる仕組みがあるというのは、大きな安心感に繋がりますよね。
公的年金制度についても、最近は不安を抱く方が多いと思いますが、それでもやはり社会の安定を支える柱であることに変わりはないのでしょうか?
茶野教授:そうですね。今後、公的年金の給付水準が相対的に下がったり、支給開始年齢が引き上げられたりする可能性は十分にあります。
それでも、公的年金は社会保障の「土台」としての役割は依然として大きいと考えています。
今後の税制度のあり方なども含めて、制度自体の見直しが進むことはあると思いますが、仮に公的年金制度がなくなってしまえば、社会の安定は著しく損なわれてしまうでしょう。
相対的な給付水準が下がったとしても、最低限の生活を支える仕組みとして、公的年金制度は不可欠だと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。公的年金もまた、安心して暮らしていくための土台として重要な制度だということですね。
一方で、最近は「公的年金制度が将来破綻するのではないか」という声もよく耳にします。茶野様は、公的年金制度の破綻は現実的に起こりうるとお考えですか?
茶野教授:結論から申し上げると、公的年金制度そのものが完全に「破綻する」ということは、基本的にないと思います。
ただし、制度を維持していくためには、給付水準の相対的な引き下げや支給開始年齢の引き上げといった調整は避けられないでしょう。例えば、支給年齢が70歳を超えるような時代が到来する可能性もあります。
また、公的年金財源を確保するために、消費税の引き上げなど、国民が一定の負担を担うことも必要になるかもしれません。
公的年金は「天からお金が降ってくる制度」ではありませんから、国民全体で制度を支えていく姿勢が求められるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。つまり、制度を維持するためには国民の理解と協力が必要だということですね。
茶野教授:はい。先ほども申し上げましたが、私は「公的年金制度が財政的に完全に破綻する」とは考えていません。
なぜなら、それが現実となれば、国家としての機能そのものが成り立たなくなるからです。
だからこそ、公的年金制度を破綻させないように努力することが、政治や行政の責任であり、同時に私たち国民一人ひとりの責任でもあると考えています。
つまり、「破綻するかどうか」という話ではなく、「破綻させてはならない制度」である、というのが私の考えです。公的年金制度は社会を支える基盤インフラのひとつとして、守っていく必要があると強く感じています。
”安心”をどう伝えるか?──メッセージと行動の経済学
カードローンの窓口合同会社 編集部:保険のCMや政府の広報などでは、「安心してください」「安心のための制度です」といったメッセージをよく見かけます。
ただ、個人的には、あまりにも「安心」が強調されるとかえって不安に感じてしまうこともあります。こうした現象は、経済学や心理学の観点から説明がつくものなのでしょうか?
茶野教授:それはどちらかというと、心理学的な側面が強いかもしれません。
一部には行動経済学としての視点もあるとは思いますが、「安心してください」と繰り返されることで逆に不安を感じるというのは、多くの人が共感できる心理だと思います。
人間はそれほど単純な存在ではないので、「安心してください」と何度も言われると、かえって「なぜそこまで言うのか?本当は安心できない事情があるのではないか?」と疑いたくなるものです。それは、ある意味で合理的な反応とも言えます。
そのため、「安心してください」という言葉そのものが、逆効果になってしまうことは十分に考えられます。
このような場合、「安心できない」と感じるのは、情報を受け取る側の問題ではなく、情報を発信する側の伝え方に原因があることも多いのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、言葉だけではなく、納得できる情報が伴っていなければ、安心には繋がらないということですね。
茶野教授:その通りです。本当に安心してもらいたいのであれば、やはり国民が納得できるような、適切な情報開示が必要でしょう。
例えば、バブル崩壊後の日本では、金融機関は「大丈夫です」「潰れません」といったメッセージが当局から繰り返し発信されました。しかし実際には、相次いで金融機関が破綻してしまった。
情報が小出しで対応が遅れて深刻な影響を国民経済に及ぼした結果、大蔵省が解体されて、財務省と金融庁に分かれるという大きな制度改革が行われましたよね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:あの出来事は、多くの人の記憶に強く残っていますね。
茶野教授:そうですね。つまり、「大丈夫」と言われているのに、次々と不安材料が現れるような状況では、人は自然と「これは危ないのでは」と考えるようになります。それは心理的にも、合理的な判断としても、ごく当たり前の反応です。
だからこそ、情報を発信する側、例えば公的年金制度であれば国が、正確かつ透明性のある情報開示を行い、国民が納得できる形で説明を尽くすことが何よりも重要だと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。先ほど、情報開示の仕方に工夫が必要だというお話がありましたが、消費者が「安心できる」「信頼できる」と感じられるために、国や保険会社が提示すべき情報には、どのようなものがあるのでしょうか?
茶野教授:そうですね。例えば、保険会社の財務報告やディスクロージャー資料などはすでに詳細な情報が公開されています。
しかし、実際にご覧になった方はお分かりかと思いますが、資料も分厚く、それらの内容は非常に専門的で、読み解くのは容易ではありません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:はい。私も一度見たことがありますが、正直、内容を理解するのはかなり難しかったです。
茶野教授:そうなのです。一般の方がそれをすべて理解するのは難しいでしょうし、我々のように専門に関わっている者であっても、忙しい日常の中でしっかり読み込むのは簡単なことではありません。
これは公的年金制度も同様です。例えば、厚生労働省が公表している財政検証レポートには、将来の公的年金支給水準などを予測するシミュレーションが含まれていますが、これも非常に複雑で、正しく読み取るには相応の知識が必要になります。
ですから、すでに公開されているこうした資料を、もっと国民に近い立場から、中立的に解釈・翻訳して伝える存在が必要なのではないかと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、情報を「翻訳」してくれるような存在が必要ということでしょうか?
茶野教授:そうですね。例えば、公的年金制度について新たな発表があった際には、「これはこういう内容ですよ」と丁寧に解説してくれる機関などがもっとあると良いと思います。
また、保険会社や銀行が開示するディスクロージャー資料についても、「この数値はこう読むべきです」「この項目に注目するとリスクが見えてきます」といった解説を提供する存在が増えることで、消費者の理解も深まるはずです。
もちろん、新聞などのメディアでも情報発信はされていますが、どうしても編集方針などによってバイアスがかかることは避けられません。
ですので、理想としては、より中立的で消費者に近い立場の組織が、正確かつ分かりやすい情報を届ける体制を整えていくことが、社会全体の安心に繋がっていくのではないかと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:国民目線の情報提供が必要というのはおっしゃる通りですが、現状そうした情報を届けてくれる機関は多くないかと思います。
そこでお伺いしたいのですが、現在、政府や保険会社が提供している情報を一般の人が見る際に、「特にここを見ておけばいい」という注目ポイントのようなものはあるのでしょうか?
茶野教授:1番大切なのは、「ソルベンシー」、つまり「将来的に支払い能力があるかどうか」という点です。
保険や公的年金は、将来発生する可能性のある支払いに備える仕組みですよね。ですから、今どれだけの資産を持っていて、それをどう運用していくか──この点が極めて重要です。
将来的な支払いに備えて、どれだけ持続可能な資産形成と運用ができるか。つまり「資産の配分」や「期待できる運用利回り」などが、支払い能力に直結します。
カードローンの窓口合同会社 編集部:とはいえ、一般の方がそうした情報を読んでも、正確に理解するのは難しいように思います。
茶野教授:おっしゃる通りです。ソルベンシーを見積もるには、人口の将来的な推移や経済成長率など、様々な前提条件が関わってきます。
つまり、仮に「支払い能力は十分にあります」と書かれていても、その前提が楽観的すぎれば、実際には将来の不安定要素が潜んでいることもあり得るのです。
ですので、「どんな前提のもとで」「どのように見積もられているか」という両方を確認することが大切です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。ただ、そういった内容に詳しい中立的な解説者や機関は、まだ多くはない印象です。となると、現状は新聞を読み比べるといった方法が有効でしょうか?
茶野教授:そうですね。それは非常に有効な方法だと思います。新聞社によってスタンスに違いがあり、政府寄りのところもあれば、そうでないところもあります。
そうした違いを踏まえて、複数の新聞や雑誌の解説記事を見比べることで、情報に対する見方が広がります。比較・検討していくという姿勢が、とても大切だと思いますね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。今後も、社会や経済の不確実な状況は続いていくかと思われます。そうした中で、私たちが安心して生活していくために、必要な心構えや大切なことがあればお聞かせいただけますか?
茶野教授:はい。現在の日本社会は、いわゆる逆ピラミッド型の人口構成になっており、若い世代の負担が非常に大きくなっています。かつてのように家族内で高齢者を支える構造は希薄になり、今では公的年金制度に大きく依存している状況です。
しかし、その制度がもし機能不全に陥るような事態になれば、若い世代の負担はさらに増大します。そうなれば、働く意欲や将来への希望すら損なわれかねません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、それは深刻な問題ですね。
茶野教授:だからこそ、家族や地域といった小さな単位の中で、互いに支え合うような社会のかたちをもう一度見直す必要があると考えています。
「かつての価値観に戻そう」というわけではありませんが、国の制度だけに依存せず、身近な人々との助け合いを前提とした社会構造に移行していくことが求められているのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。制度と地域の支え合いを組み合わせるようなイメージでしょうか?
茶野教授:その通りです。若い世代が過度な負担を背負わずに済むような社会。
そして、働くことでやりがいと正当な見返りが得られる環境作り──それがこれからの日本にとって重要だと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:今、地域のコミュニティが重要というお話もありましたが、現実には核家族化や地域の分断が進んでしまっている印象があります。このような状況下で、地域の再生に向けた工夫としては、どのようなことが必要とお考えですか?
茶野教授:特に大きな課題は、過疎化の進行によって高齢者ばかりの社会が形成されてしまっている地域が増えている点です。若い人たちが都市部に出て行き、戻りたくても戻れない。こうした状況が、地域の世代バランスを崩しているのです。
理想的なのは、年配の方、働き盛りの世代、そして子どもが揃って暮らすような社会です。子どもたちは地域に活気をもたらし、高齢者がその成長を温かく見守る。そうした世代間の循環があることで、地域社会の安定に繋がっていきます。
例えば、最近では子どもの登下校を地域の高齢者が見守る「見守り隊」のような取り組みもあります。一見すると簡単な活動のように見えますが、実は地域全体の安心感を支える、大切な役割を果たしているのですよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。そうした小さな繋がりでも、地域の安定感に繋がるのですね。
茶野教授:はい。社会が疲弊していくと、どうしても治安の悪化が起こりやすくなります。そこから盗難や傷害事件などが増えていくと、問題は経済的な範囲を超えてしまうでしょう。
そうなる前に、人と人との繋がりで支え合える社会を作ることが、結果として大きな不安の予防にもなると考えています。
少し話は逸れますが、よく「江戸時代は幸せだった」と言う人がいますよね。当時の生活水準は現代よりはるかに低かったはずですが、それでも浮世絵や歌舞伎といった町人文化が花開き、人々が生きがいを持って暮らしていたわけです。
もちろん、飢饉など厳しい現実もありましたが、それでも「幸福感」は決して今より劣っていたとは限らない。物質的な豊かさだけでなく、文化や繋がりといった「心の豊かさ」が社会の安定を支えていたのだと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:経済成長だけを追い求めるのではなく、社会全体の幸福感を大切にするということですね。
茶野教授:まさにそうです。私たちが本当に求めているのはGDPの数値ではなく、「幸せな人生」であるはずです。
それを実現するには、一枚岩のような大きな社会ではなく、小さなコミュニティが多数存在し、それぞれが助け合っているという構造のほうが、持続可能で安定した社会に繋がるのではないかと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。最後に、将来への不安を抱える若い世代に向けて、茶野様からメッセージをいただけますか?
茶野教授:そうですね。大学で日々学生と接していて感じるのは、以前と比べて「貪欲さ」が少し薄れてきているという点です。先日、卒業生とも話をしていたのですが、「がむしゃらに頑張る」という姿勢が見られにくくなってきた印象があります。
もちろん、ただひたすら努力すれば良いということではありません。しかし、日常の中で活力を蓄え、自分の中にエネルギーを持っておくことは、非常に大切だと思います。
そして何より重要なのが、「ポジティブに考えること」です。悲観的になると、良いことも悪く見えてしまい、悪いことはさらに悪く感じられるという、負の連鎖に陥りやすくなります。
だからこそ、少しでも前向きに、少しでも希望を持って、「きっとうまくいく」と信じる気持ちを持ってほしい。特に若い世代には、ポジティブな姿勢が未来を切り拓く大きな力になると、私は信じています。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年7月14日