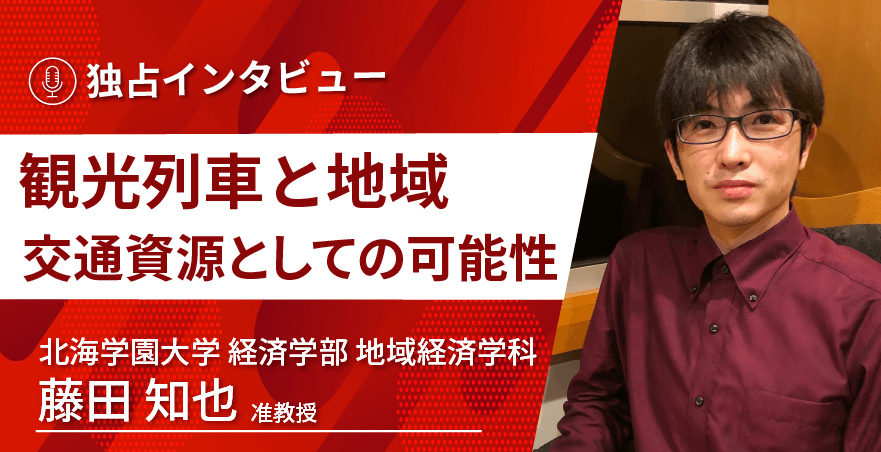少子高齢化や人口減少が進む中、地域交通の存続と活性化は大きな課題となっています。その中で注目を集めるのが、観光列車を地域資源として活用する取り組みです。
そこで今回、北海学園大学の藤田知也准教授に、交通資源としての鉄道・観光列車の可能性と持続性について独自取材を通じてお話を伺いました。
鉄道を切り口に、地域と社会を見つめ直していきましょう。
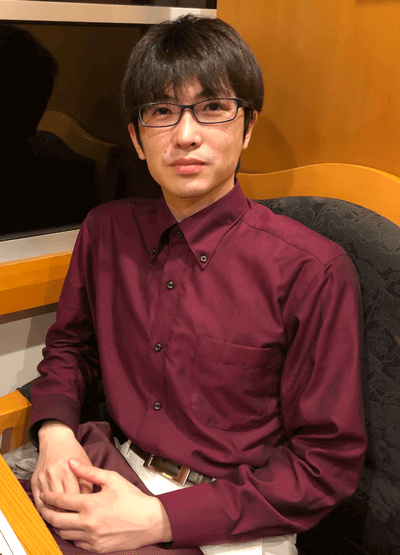
北海学園大学 経済学部 地域経済学科
藤田知也(フジタ トモヤ) 准教授
関西大学経済学部を卒業後、鉄道会社に勤務。
2020年に北海学園大学経済学部講師に就任し、2023年より現職に至る。
大阪市立大学大学院創造都市研究科にて博士(創造都市)を取得。
〈研究分野〉
交通経済学・地域経済学・観光経済学
〈著書・論文〉
「JR北海道における輸送密度・営業収益を規定する要因の把握-線区別データを用いた定量的分析-」(2025年)
「観光列車が鉄道事業者にもたらした効果-需要関数の推計による分析-」(2024年)
「観光列車の経済学的研究 -地方鉄道の維持振興と地域活性化に向けて-」(2021年)
鉄道を”観光資源”として捉えるという発想
カードローンの窓口合同会社 編集部:藤田様は「観光列車」という切り口で鉄道を地域を結びつける研究をされていると伺いました。そもそも、鉄道が「観光資源」として注目されるようになったのは、どういった背景があるのでしょうか?
藤田准教授:要因はいくつかありますが、まず1つのきっかけとして挙げられるのが、JR九州の戦略です。
特に1990年代初頭にかけて、九州では自家用車や高速バスとの競争が非常に激しくなっていました。
その中でJR九州は、「乗ってみたい」と思わせるような列車を打ち出すことで差別化を図る戦略を採っていたのです。その取り組みの1つが、観光列車の導入でした。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。当時から「乗ること自体が目的になる列車」を意識していたんですね。
藤田准教授:そうですね。その後、九州新幹線の開業もあり、JR九州ではさらに複数の観光列車が導入されました。そして2010年代半ばには、それらの成功を受けて、全国的にも観光列車の展開が広がっていったのです。
また、ちょうど同じ時期、地方鉄道に対する社会的な見方も変わってきました。2000年代前半には規制緩和の流れで鉄道の廃止が進みましたが、2000年代後半から2010年代にかけて「鉄道は公共交通として大切」という認識が広まり、2007年には「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」という法律も整備されました。
私はこのような背景の中で、観光列車を通じて地方鉄道の魅力を再発見し、地域の活性化に繋げるという社会的な流れが生まれたのだと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。近年は沿線の景色や地域の特産品を楽しめる食事など、観光列車ならではの体験の価値が高まっているのか、SNSでも「観光列車に乗ること」自体が旅の目的になっている投稿も増えてきているように思います。
こうした価値は、鉄道事業者や地域にとってどのような経済的・文化的な意味を持つのでしょうか?
藤田准教授:まず経済的な側面からお話しすると、鉄道会社にとっては運輸収入の増加が挙げられます。乗客数が増えれば当然、その分の売り上げも増えますからね。
他にも、車内で販売されるグッズなどの収益、いわゆる雑収入も見逃せません。
さらに、観光列車に乗るために現地まで足を運ぶ交通も含めれば、JRのような広域ネットワークを持つ会社にとってはその移動による収益も期待できます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:観光列車に乗るために遠くから訪れる方も多いですから、移動そのものも収益に直結するわけですね。
藤田准教授:はい。ただ、地域の小規模な鉄道事業者、例えば1つの路線しか運営していないような会社の場合、そうしたネットワーク的な利益までは享受しづらいという課題もあります。
それでも、地域全体で見ればプラスの側面は大きいと思います。例えば、観光列車で提供される食事には地域の食材が使われていますし、列車をきっかけに地域を再訪する観光客も増えているのです。
そうした意味では、観光列車は地域経済の活性化にも繋がっていると言えるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、地域全体に波及する効果も期待できるのですね!
藤田准教授:そうですね。ただし、鉄道会社にとって観光列車の運営は必ずしも黒字とは限りません。観光列車は既存の車両を改造したり、新造したりといった初期投資が必要です。
ランニングコストは賄えたとしても、導入費用まで回収できるかというと難しいこともあります。
実際、車両改造の費用を補助金で賄っているところもあり、運営自体が赤字になるケースもあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうなると、単体では赤字でも、地域への経済効果を含めて「トータルでプラスかどうか」という視点が大事になりそうです。
藤田准教授:その通りです。そしてもう1つ、文化的な意義についても触れておきたいのですが、観光列車は沿線地域の文化や伝統を紹介する場にもなっています。
例えば、地元の方が伝統舞踊でおもてなしをしたり、車内で地域の焼き物や工芸品が展示されたりといった形ですね。
そうした取り組みを通じて、地域の文化が広く知られるようになり、次世代へと継承されていく。観光列車にはそういった文化的な役割もあると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほどのお話では、経済的な側面においていくつかの課題もありましたよね。文化的な側面でも課題やデメリットなどはあるのでしょうか?
藤田准教授:そうですね、これはなかなか難しいところなのですが、いくつか課題はあります。
実は、最近の観光列車の1つの傾向として、同じ車両をいろいろな地域で運行するというケースが増えてきています。
そうなると、必ずしもその沿線地域の文化を体現していない列車が走っている、という状況も場合によっては出てきてしまうのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。地域の特性と合っていない列車が走ることで、文化的なミスマッチが生まれてしまうのですね。
藤田准教授:その可能性は否定できません。
さらに、観光全般でもよく言われることですが、受けが良い観光列車にするために内包する文化が変容してしまうリスクもあります。
例えば、昔ながらの素朴な様式ではなく、現代的にアレンジされた「映える」演出が好まれるようになると、本来の文化や「本物らしさ」が失われていく危険性もあるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、SNS映えを意識するあまり、文化的な本質が変質してしまうという問題もありそうです。
藤田准教授:その通りです。だからこそ、観光列車に地域の文化をどう取り込むか、そしてどう守っていくかは、とてもデリケートなテーマだと思っています。
持続可能な地域交通をどう描くか
カードローンの窓口合同会社 編集部:藤田様は、過去に「鉄道を残すこと自体が目的ではなく、地域にとって最善の交通手段を考えることが重要」という言葉を残されています。その考えに至った経緯や背景があれば、教えていただけますか?
藤田准教授:そうですね……。明確なきっかけがあったわけではないのですが、もともと私は根っからの鉄道好きで、いわゆる「乗り鉄」です。大学時代もいろいろな路線に乗りに行っていて、当然バスも使っていたのです。
その中で、バスを使っていると「こっちの方が便利じゃないか?」と思う場面が何度もあったんですよ。
バスは病院の前やショッピングセンターの前に停まりますよね。一方、鉄道はそういう生活導線の中にないことが多い。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、電車を使うと目的地までさらに歩かなければいけないというケースもあります。
藤田准教授:そうなんです。鉄道好きとしては「残ってほしい」と思う一方で、なら「本当にその地域の人たちにとって便利か」と考えれば、そうとは限らない。
ですから、鉄道は絶対的な存在ではなく、その地域にとって本当に必要かどうか、という視点が大事だと思うようになったのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ご自身の鉄道好きという視点と、地域にとっての「合理性」の視点の両方があるわけですね。
藤田准教授:ええ。鉄道会社に勤務した経験もあって、その思いはより強くなりましたし、今大学で研究している中でも「観光列車が好きだから研究している」という気持ちと、「鉄道の有効活用とは何か」を考える視点は常に両立させています。
少し話は変わりますが、日本の鉄道は、基本的にはインフラ部分──つまり線路や設備──と、車両の運行までを一体で同じ事業者が担っている「上下一体型」の構造です。
そうすると、列車が走っていない時間帯というのは、言い方を変えれば鉄道施設が「ほったらかし」の状態になってしまうのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、設備としては使われていない時間がありますね。
藤田准教授:はい。だからこそ、そういった空いている時間に観光列車として活用することで、これまで見えづらかった価値──いわば「隠れていた資産」を顕在化させられるのではないかと考えています。これは私自身の研究テーマの核でもあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、鉄道をただ残すのではなく、活かすということでしょうか?
藤田准教授:その通りです。本来、鉄道はまず「地域の足」として機能するべきものですが、その上で観光列車としての活用が加わることで、地域に対してより多面的な価値を提供できる可能性があります。
ただし、先ほどもお話ししたように、実際に旅行や観光の移動手段としては、バスの方が便利なこともあります。
ですから、トータルで見て、バスの方が地域にとってメリットが大きいのであれば、それはバスを選ぶべきだと思っています。
大事なのは、「鉄道を残すこと」を目的にしてしまわないこと。鉄道にはこんな価値もある、という材料を提供したうえで、地域ごとに合理的な判断がなされることが大切です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「バスの方が地域にメリットが大きいのであれば、バスを選ぶべき」というのはその通りですよね。私自身も電車があまり通らない地域に住んでいたことがあるのですが、その時の交通手段としては自家用車かバスの二択だった覚えがあります。
藤田准教授:それはよく分かります。今は鉄道とバスが対立するのではなく、むしろ共存していくべき時代に入っていると思います。鉄道とバス、どちらかを選ぶのではなく、両方を適切に使い分ける形です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、住民の利便性を考えて「交通の使い分け」をするのですね!
藤田准教授:はい。今この瞬間も、社会は地域ごとの交通事情やニーズに応じて、鉄道もバスも柔軟に活かしていく──そんな風に変わりつつあると思います。
だからこそ、私の研究も「鉄道が好きだから守る」ではなく、「地域にとっての本質的な価値は何か」を問い直すところから始まっているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ここまで、観光列車が地域経済や文化に与える影響、そして鉄道の在り方についてお話を伺ってきました。
ここからは、視点を未来に移して伺いたいのですが、観光列車を「持続可能な交通資源」として生かし続けるためには、地域や鉄道事業者のどのような取り組みが鍵になるのでしょうか?
藤田准教授:すでにお話した部分とも重なるのですが、観光列車の運営には沿線地域の人々、特に地域団体などの関与が不可欠になってきています。
そして、これからはその関与の在り方がますます重要になっていくと思います。
例えば、観光列車が人気になれば、当然「もっと走らせたい」という思いも鉄道会社側には出てくるでしょう。
ただ、その一方で、地域の方々にとっては「おもてなし」などの活動が増えることにもなり、負担が大きくなるケースもあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、地域の人たちによるおもてなしなどは観光列車の魅力に直結している印象がありますが、その実態はボランティアベースであることも多いと聞きます。
藤田准教授:まさにその通りです。歓迎イベントや車内での接客サービスなどは、多くが善意で支えられているケースも多いのです。そうすると、頻繁に列車を運行すればするほど、地域側の負担が増えてしまい、結果的に続けるのが難しくなる場合もあります。
ですから、観光列車では「どれだけ走らせれば良いか」というバランスが非常に大切です。
走らせ過ぎれば持続可能性が揺らいでしまいますから、その絶妙なバランスをいかに保つかが今後の鍵になると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。例えば「土日祝日だけ」など、運行頻度を意図的に絞ることも1つの工夫ということですね。
藤田准教授:そうですね。そして、運行本数の調整だけでなく、地域と鉄道事業者の間でしっかりコミュニケーションを取りながら進めていくことが大切です。
そんな持続可能な観光列車の運営において、私が注目している事例はいくつかあります。
1つは北海道を走る〈流氷物語号〉という観光列車です。これは冬季限定で運行している列車で、地域の有志団体「MOTレール倶楽部」が企画運営に深く関わっているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:運行期間をあえて冬場だけに限定しているのですね。
藤田准教授:はい。運転士や車掌はJRが担いますが、車内サービスや企画の多くをこの地域団体が担っていて、運行業務と営業・接客業務がしっかり分業されています。
限られた期間だからこそ、地域の人たちも無理なく協力できていて、しかも毎年楽しみにされている列車になっているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。「期間限定」が逆に成功要因になっているんですね!
藤田准教授:もう1つは、秋田内陸縦貫鉄道の〈ごっつお玉手箱列車〉です。こちらは沿線のグリーンツーリズム団体が車内での食事提供やサービスに関与していて、地域の魅力を存分に伝える仕組みが整っています。
ただし、この列車も運転日は限られていて、それがまた特別感やレア感に繋がっていますよ。
このように、無理をして頻繁に走らせるのではなく、持続可能な頻度と内容で運営する。その中で、地域資源の魅力を活かす──そうした観光列車こそが、これからのモデルになると思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ちなみに、最初の方で観光列車が「映え」を意識するあまり、本来の地域文化から離れてしまうリスクについてもお話がありましたよね。
今のように、運行日を限って希少性を高めることで、むしろそうした変質を防げる可能性もあるのではないかと感じたのですが、その点はいかがでしょうか?
藤田准教授:一定の可能性はあると思います。ただし、運行期間が短くても、やはり続けていく中ではマンネリが課題になることもあります。
実際、いろいろな鉄道事業者の方にお話を伺っていると、「リピーターにもう一度来てもらうにはどうしたら良いか」というのは、どこも悩まれているポイントです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:新規の利用者とリピーターの両方を満足させるというのは、たしかに難しそうです。
藤田准教授:はい。料理であればメニューを変えるなど柔軟な対応も可能ですが、すべての列車がそういうわけではありません。
限られた運行日数の中でも、数年単位で継続していくとなると、やはり何らかの変化は求められる。そこに「映え」の要素が入り込む可能性もゼロではないと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。藤田様は個人的にも鉄道がお好きというお話でしたが、「もう一度乗りたい」と思う観光列車には、何か共通する特徴があるのでしょうか?
藤田准教授:そうですね……。もちろん「食事がおいしい」とかもありますが、やはり一番大きいのは接客、つまりホスピタリティの部分だと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:やはり「人」の部分が大きいのですね。
藤田准教授:はい。ただ、「気取りすぎない」というのが大事で。観光列車は地域文化を色濃く反映している分、地域の空気感みたいなものがサービスにも現れるんですよ。
例えば、地元の方が方言で話してくれるとか、ちょっと親しみやすい感じの接客があると、すごく心に残ります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:それはたしかに、印象に残る体験になりますね!
藤田准教授:実際にいろいろな観光列車に乗ってきましたが、「また乗りたいな」と思える列車には、共通して「人的な魅力」があります。
客室乗務員さんの対応1つで、その列車の印象はがらっと変わるのです。逆に、もし景色だけが売りなら、極論ですが観光列車ではなくても良いということになりますからね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そこに「観光列車ならでは」の意味を持たせてくれるのが人の力なのですね。
藤田准教授:そう思いますね。そして、そうした「人の魅力」を支えているのが、沿線の地域団体などの協力です。
先ほどお話したように、地域の方が運営に関わっている列車では、その土地ならではの人の温かさや雰囲気が感じられます。
方言や地元ならではの言い回しも含めて、そこでしか味わえない接客がある。これが観光列車を「また乗りたい体験」に変えてくれるのだと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、地域の人たちが関わるからこそ、その列車に人間らしい魅力が宿るのですね。お話を通じて、観光列車というのは単なる乗り物ではなく、地域そのものを体験できる空間なのだと改めて感じました。
藤田准教授:まさにその通りだと思います。観光列車は、鉄道事業者だけが作るものではありません。
地域の人々と一緒に、無理なく、そして楽しく続けていける仕組みこそが、持続可能性の鍵です。そしてそのためには、「走らせること」ではなく、「続けられること」に重きを置いた発想が、これからの時代には求められてくると思います。
若い世代と地域を繋ぐ”鉄道”の力
カードローンの窓口合同会社 編集部:藤田様のゼミでは、学生が実際に地域に出向いて、鉄道やその周辺環境についてフィールドワークを行っていると伺いました。こうした活動を通じて、学生たちはどのような学びを得ているのでしょうか?
藤田准教授:そもそもの話にはなってしまうのですが、私のゼミに鉄道や地域交通に強い関心を持って入ってくる学生は、そんなに多くはないのです。
例えば、地元に鉄道廃止の危機があるとか、個人的に深い関心がある学生は別ですが、基本的に大学生は車の免許さえ取れれば自家用車で移動できますよね。ですから、日常的に地域交通を深く考えることはあまりありません。
しかし、世の中を広く見てみると、地域交通の問題があちこちで取り上げられている。学生たちの中にも「なんとなく気になる」「社会課題としては認識している」くらいの関心はあるようです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。藤田様のゼミでは「交通」と「観光」の2軸で活動されていると伺いましたが、やはり観光志望の学生が多いのでしょうか?
藤田准教授:はい。観光に関心を持って入ってくる学生が多く、交通への関心は相対的な興味というか、観光を学ぶ中で交通にも触れていくという流れが多いです。
実際の活動と学びの話に戻りましょう。フィールドワークでは、学生たちは現地を訪れて、鉄道をはじめとする交通機関や地域に関わる様々な人のお話を聞いたり、自分たちで観察をしたりします。
その中で、「なぜ鉄道を残すのか」「逆になぜ廃止すべきという声があるのか」といった問いに、複数の視点から考えるきっかけが生まれてきます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:実際に現場を見ることで、抽象的だった課題が具体的に見えてくるのですね。
藤田准教授:そうですね。もちろん私としては、地域交通にもっと興味を持ってほしいという思いもありますが、それ以上に大切にしているのは「どういう思考プロセスで自分なりの答えを導くか」ということです。
例えば、鉄道の存廃問題1つ取っても、答えは簡単に出るものではありません。
大事なのは、どんな情報をもとに、どんな視点で考え、それをどう他者に伝えるか、あるいは説得できるか。その思考の筋道を意識してもらえたら、それが一番の学びだと思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。「どちらが正解か」ではなく、「どう考えるか」が大事だということですね。
藤田准教授:はい。実際、去年行った地域研修では、存廃問題に関する学生の意見を事前と事後でアンケートして、「存続」「廃止」「迷っている」などの立場に分かれて、各グループで意見をまとめて報告してもらいました。
多くのゼミでは「最終的に1つの結論を出す」ことが多いのではと思いますが、あえて私たちは「複数の結論があって良い」としたんです。
交通の課題に「絶対の正解」はありませんから、地域ごとの状況や価値観によって答えは変わります。それを学生たちに実感してもらうことが大切だと思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ちなみに、研修を通じて学生たちの意見に変化は見られましたか?
藤田准教授:ありましたね。全体的には「存続」の意見が多数派でしたが、「廃止から存続に変わった」という学生もいれば、「存続派だったけれど、現地を見て廃止でもやむなしと考えるようになった」という学生もいました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:具体的には、どんな理由が印象的でしたか?
藤田准教授:そうですね、ある学生は「実際に行ってみたら、ほとんど誰も鉄道を使っていなかった。だったら残す意味ってあるの?」と話していました。非常に現実的な視点ですよね。これは一種のリアリズムで、強く印象に残っています。
一方で、存続派の中にも「条件付きで」という意見がありました。「鉄道が廃止されたら、代わりはバスになるけれど、バスの運転手が不足している今、それは難しい」とか、「冬場の積雪でバスが止まるリスクを考えると、鉄道の方が安定している」といった声もありました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、気候や人的リソースの問題は無視できないですね。
藤田准教授:その通りです。自動運転の技術に期待する声もありますが、北海道のような雪深い地域では、それだけで解決できるわけでもありません。
ですから、鉄道を残すことは「消極的な選択」に見えるかもしれないけれど、それでも現実を見据えたうえでの「合理的判断」なのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。最後の質問になりますが、今後、観光列車や地域交通の分野において、若い世代が担っていくべき役割について、どのようなことを期待されているかお聞かせいただけますか?
藤田准教授:まずはやはり「関心を持ってほしい」というのが一番ですね。
というのも、若い世代は今の時代、公共交通がなくても生活できてしまうんです。車の免許を取れば、自分でどこへでも行ける。都市部は別として、北海道のような地方では、公共交通への依存度がもともと低くなりがちなんですよ。
しかし、それは今だけの話で、将来高齢になった時には公共交通に頼らざるを得ない場面が来るかもしれない。
だからこそ、「今は使っていなくても、自分ごととして交通の問題を捉えてほしい」というのが、まず1つの願いです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。では、実際に若い世代が地域交通の担い手になることを考えた場合、どんな課題があるのでしょうか?
藤田准教授:やはり大きな課題は「人材不足」ですね。特にバスの運転手は深刻です。
最近は少しずつ改善の兆しもありますが、依然として給料やシフトの面で若い人にとって魅力的とは言えない状況です。鉄道も同様で、今後ますます運転士不足が顕在化すると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:収入面や労働環境の改善がなければ、若者に選ばれにくい仕事になってしまいますよね。
藤田准教授:そうなんです。だからこそ、給与や勤務形態を含めた「職業としての魅力づくり」が必要になります。
例えば、パートタイムの運転士制度や、兼業を認めるような柔軟な働き方の導入など、実際に一部で取り入れられている取り組みもあります。こうした制度がもっと広がっていくことも、若者が地域交通を担っていくためには不可欠だと思います。
それからもう1つ大切なのは、「利用者の意識」ですね。
近年は「カスタマーハラスメント」という言葉も浸透しつつありますが、まだまだ現場では理不尽なクレームに悩まされている職員が多い状況にあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:近年は防止ポスターなども見かけるようにはなりましたが、実際にはなかなか減っていないようにも感じます。
藤田准教授:はい。本当に酷いクレームに対しては、もう「やむを得ない強硬策」が必要かもしれません。
例えば、制服・私服警察官を乗せるとか、増えてはいますが防犯カメラを車内に設置するとか……。そういう抑止力も必要になる場面もあると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、利用者の意識を個人任せにするだけでは限界もありますね。
藤田准教授:日本は接客の水準が非常に高い分、それを当然のように要求する文化もあるのではないかと思います。
しかし、本来であれば、たとえバスの運転手が外国人で言葉が通じにくくても、安全に運転してくれるならそれで十分なはずです。
過剰なサービスに頼らなくても良い環境を整えることも、これからの交通社会には必要なのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:求めすぎない、許容することもまた、公共交通を支える一歩かもしれませんね。
藤田准教授:そうですね。若者が地域交通を担うと言っても、実はそれは若者だけの問題ではないと思っています。
運転士として働く、乗客として利用する、そして交通政策に関心を持つ──。それぞれの立場で、全世代が公共交通の在り方に関わっていく社会を作っていく必要があると思います。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年6月28日