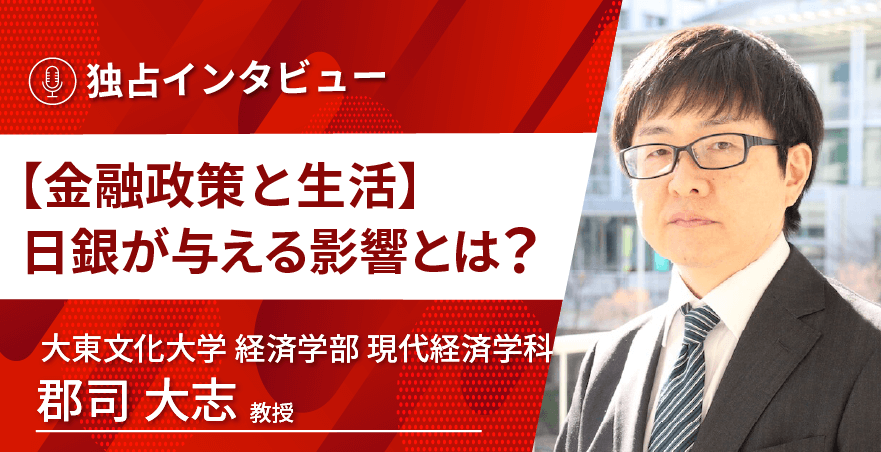ニュースでよく見る「政策金利」や「金融政策」といった単語は、私たちの生活に大きな影響を与えています。しかし、具体的な単語の意味やその影響を知っている方は多くないのではないでしょうか。
そこで今回、大東文化大学の郡司大志教授に、日銀の動きが生活に与える影響と金融政策の見方について独自取材を通じてお話を伺いました。
生活を少しでも豊かにするためのヒントを、郡司教授のお話を通じて探っていきましょう。
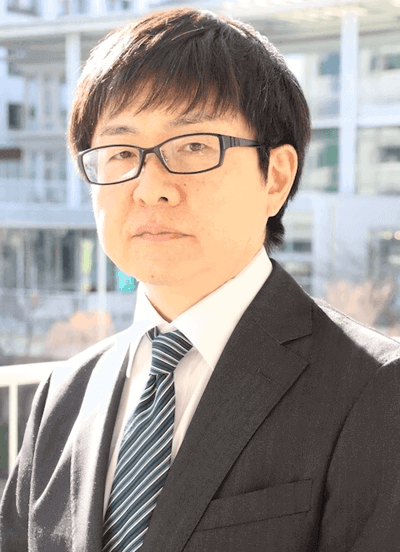
大東文化大学 経済学部 現代経済学科
郡司大志(グンジ ヒロシ) 教授
法政大学経済学部経済学科を卒業後、
同大学大学院社会科学研究科にて博士(経済学)を取得。
2006年より東京国際大学経済学部にて客員講師に就任後、2009年より大東文化大学経済学部現代経済学科にて講師を務める。
2017年より現職。
〈研究分野〉
金融・ファイナンス・経済政策
〈著書・論文〉
「Re-examination of monetary policy using a shift-share regressor and instrumental variables」(2025年・共著)
「Do reserve requirements restrict bank behavior?」(2025年・共著)
「Did the BOJ’s negative interest rate policy increase bank lending?」(2025年・単著)
金融政策の目的とは?
カードローンの窓口合同会社 編集部:最近ニュースなどで「マイナス金利」や「金融緩和」という言葉をよく耳にするようになりました。これらの言葉について、金融や経済にあまり詳しくない方にも分かりやすく説明していただけますか?
郡司教授:まず、マイナス金利政策やQQE(量的・質的金融緩和)というのは、現在ではすでに解除されて使われていない政策なのですが、以前は「政策金利を引き下げる」という伝統的な金融政策に代わる形で採用されたものです。
かつては政策金利は0%までしか下げられないと考えられていましたが、ゼロ金利政策の導入によって、「ゼロが下限」という考えが見直されるようになりました。
さらに、ヨーロッパの中央銀行では、中央銀行に預けられる預金──つまり中央銀行当座預金にマイナスの金利をつけるという政策が実施され、それが「マイナス金利政策」と呼ばれるようになりました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしか日本でも2016年頃に政策金利がマイナスになりましたよね。
郡司教授:そうです。日銀も2016年1月にマイナス金利政策を採用しました。
これはヨーロッパの中央銀行の動きに倣ったもので、従来のゼロ金利よりも一歩踏み込んだ金融緩和を目指したものです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。では、QQEについても簡単に教えていただけますか?
郡司教授:はい。QQEは、満期の長い国債やETF(上場投資信託)などを日銀が大規模に買い入れ、マネタリーベースを増やす政策です。
これにより市場全体の資金供給量を増やすと同時に、家計や企業の“期待”にも働きかけようという狙いがありました。
つまり、目的としては、急激な金融緩和を実現しようという点で、マイナス金利政策と同じ方向性の政策になります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:お金の流れを活発にさせるだけでなく、「経済が良くなるかもしれない」という空気感も作ろうとしていたんですね。ここまでのお話の中で何度か出ていた「金融緩和」という単語についても、改めて分かりやすく教えていただけますか?
郡司教授:金融緩和とは、経済に刺激を与えて需要を高めるための政策で、最も分かりやすい手段は「金利を下げること」です。
金利が下がると、お金を借りやすくなりますよね。そうなると、企業の設備投資や個人の住宅購入などが進んで、結果的に景気が良くなっていくと考えられています。
ただ、国によって多少異なりますが、中央銀行の最終目的は景気の回復そのものではなく、「物価水準の安定化」にあるというのがポイントです。
例えば、物価が低迷している場合は金融緩和を行って物価を上昇させる。逆に、物価が高騰しているときは金融引き締めを行って、物価を抑える。そうしたコントロールが金融政策の基本的な考え方です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、景気と物価のバランスを取るための手段として使われているのですね。では、実際にマイナス金利が導入されたあと、銀行の貸し出しや企業の投資、消費者の行動には、日銀が狙っていた通りの効果が現れたのでしょうか?
郡司教授:実は、想定とは少し違った結果が出ているのです。
マイナス金利政策によって銀行貸し出しが増えると予想されていたのですが、私の研究では、むしろ銀行貸し出しが減少しているという推計結果が出ました。
他の国々でも、マイナス金利政策を採用したあとに同様の傾向が見られたので、これは日本だけの現象ではないと考えられています。
つまり、狙い通りではなく、逆の効果が出ていたということです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なぜそのような結果になったのでしょうか?
郡司教授:理由としては、以下のような経路が考えられます。
例えば、金利を下げても、預金を維持するためのコストは依然としてかかります。特に、預金金利はゼロ以下には通常下げられませんので、利ざやが減ります。
これにより、自己資本が減少するのですが、銀行には「自己資本比率規制」というルールがあり、貸し出しという“リスク資産”を過剰に増やすことができないため、銀行は貸し出しを減らそうとする傾向が出てくるわけです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど……つまり、制度的な制約がある中で、単に金利を下げれば貸し出しが増えるというわけではないということですね。
郡司教授:その通りです。少なくとも、日銀が当初想定していたような効果は確認されていないというのが現状です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。では、企業の投資や消費者の行動については、どうだったのでしょうか?
郡司教授:企業の投資に関しては、マイナス金利政策による影響がはっきりと確認されていないのが実情です。
一方で、消費者側、例えば住宅ローンの借り入れなどについては増加傾向が見られました。
ただ、それが日本経済全体を大きく押し上げるほどのインパクトがあったかというと、それは確認されていません。
ですので、マイナス金利政策が狙い通りに効いたかどうかについては、いまだに評価が分かれている状態と言えます。
金融政策は私たちの暮らしにどう影響する?
カードローンの窓口合同会社 編集部:長く続いたマイナス金利政策は、私たちの暮らしにどのような影響を与えていたのでしょうか?
郡司教授:まず住宅ローンについてですが、これは長期の借り入れなので、将来の金利水準を見越して選ぶ必要があります。
例えば、将来も低金利が続くと考える人は、通常、固定金利よりも低い「変動金利型」を選ぶ傾向にあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、低金利が続くなら変動金利が魅力的ですよね。
郡司教授:はい。現在、日銀はマイナス金利政策を解除し、プラス金利に移行しましたが、それでも欧米ほどの大幅な利上げはしていません。
そのため、住宅ローンでも変動金利を選ぶ人はまだ多いと考えられます。結果として、低金利時代に変動金利を選んだ人たちは、比較的得をした可能性がありますね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。ということは、今後の金利上昇に不安を感じている方は、固定金利の方が安心かもしれませんね。
郡司教授:そうですね。日銀が今後急激に金利を上げると見ている方や、不安を抱えている方は、固定金利を選択した方が気持ち的に落ち着けると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。今は住宅ローンのお話でしたが、政策金利は借りる側だけでなく、貯める側にも影響があったかと思います。例えば、資産運用の面でマイナス金利政策の影響はあったのでしょうか?
郡司教授:はい、定期預金のような「安全資産」は、長い間ほぼゼロ金利状態が続いていました。
ですので、より高い利回りを求めて「リスク資産」へ資金を振り向ける人が増えたのです。
しかも日銀が国債を大量に買い入れていたことにより国債市場が縮小し、機関投資家も株式市場などに資金を向けるようになりました。
他にも、ETF(上場投資信託)の買い入れによる影響もあって、株価は徐々に上昇し、ついにはバブル期の最高値を超える水準にまで回復しました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、ここ数年の株高は印象的でしたね。リスクを取った人たちはその波にうまく乗れた、という感じでしょうか。
郡司教授:その通りだと思います。ただし、それは「リスクを取ったことの見返り」で得た利益だという点に注意が必要です。逆に、リスクを避けて定期預金などで資産を運用していた人たちは、利息がほぼつかず、苦しかったかもしれません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。逆に言えば、リスクを取らなかったからこその安心もあった、というわけですね。
郡司教授:そうですね。そういった意味では、マイナス金利政策は、借りる面と貯める面の両方で、私たちの生活に影響を与えていたと言えます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。ここまで金利のお話を伺ってきましたが、経済学的には、金利を引き上げることで物価を下げるという効果があるとされていますよね。現在のように物価が上がっている局面では、金利引き上げの効果はどうなっているのでしょうか?
郡司教授:おっしゃる通り、現在は短期的には物価が上昇している状況にあります。
そのため、金利を引き上げることで物価上昇を抑えるという効果は一定程度期待されています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:では、将来的には物価が下落する可能性の方が高いと見て良いのでしょうか?
郡司教授:これはなかなか断言できません。
実証分析の結果を見ても、金利を上げたからといって必ず物価が下がるとは限らないのです。
つまり、「金利を引き上げれば物価が安定する」とは一概には言えない、というのが正直なところです。
ですので、日銀が今後どのような政策を取るのか、そしてそれが私たちの生活にどのように波及していくのかを見ていくことが大切だと思います。
これからの金融政策と私たちの生活
カードローンの窓口合同会社 編集部:現在、すでにマイナス金利が解除されてプラス金利に移行していますが、将来的にはさらに金利が上昇する可能性もあります。今後の経済や私たちの暮らしにはどのような変化が予想されるのでしょうか?
郡司教授:先ほどもお話ししたように、金利の上昇はお金を“貯める”時と“借りる”時の両方で影響を与えます。
まず貯める側にとっては、金利が上がることで預金などから得られる利息が増えるので、ありがたい変化とも言えますね。
ただし、金利が上昇し続けるような局面では注意が必要です。
例えば、1%の金利で5年間の定期預金をしたとします。その後2年、3年と経つうちに金利が2%、3%と上がってしまったら、もっと高い金利で運用できたはずの資金が、ずっと1%のまま固定されてしまうことになるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうなると、結果的には「機会損失」になるということですね。
郡司教授:おっしゃる通りです。金利の上昇が続くと予想される場合は、長期間の運用よりも、1年ごとなど短期間での運用を重ねる方が柔軟に対応できるかもしれません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:逆に、借りる側はどうなるのでしょうか?
郡司教授:借りる側にとっては、逆のことが起きます。金利が今後上がると予想されるならば、今の相対的に低い金利で固定してしまう方が有利です。
例えば、今1%で借りて、その金利を10年固定できるとしたら、来年2%、再来年3%と上がっても、1%のままで借り続けられるわけですから。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど……固定金利のメリットが生きてくる局面なのですね。
郡司教授:はい。ただし、これも日銀の金融政策次第です。
急激に金利を上げるのか、ゆっくりと上げていくのか、それとも一定期間は据え置くのか──この見極めがとても重要になります。
お金を貯めるにしても、借りるにしても、長期的に金利がどう動いていくのかを見据えた上で、自分にとって最適な選択をしていくことが大切だと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ちなみに日銀は現在、金利引き上げを視野に入れていると伺いましたが、こうした局面で、日銀が参考にしている国や金融政策のロールモデルなどはあるのでしょうか?
郡司教授:おそらく日銀はアメリカのFRB(連邦準備制度理事会)や、欧州中央銀行(ECB)などを参考にしている面が大きいと思います。
実際、マイナス金利政策などもそうですし、その他の政策のタイミングについても、欧州の動きに倣って政策を組み立ててきた経緯があるのです。
なお、欧州中央銀行やFRBでは、金利を上げる局面がしばらく続いてきましたが、最近はECBが利下げに転じています。
こうしたタイミングを日銀も注視しつつ、政策金利の引き上げや維持をどう判断するか検討していると考えられます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。アメリカのFRBを参考にしているというお話でしたが、FRBとトランプ現大統領の間で金融政策について意見が食い違っていたという話を聞いたことがあります。それは現在も続いているのでしょうか?
郡司教授:はい。私はアメリカの中央銀行制度が専門というわけではないのですが、トランプ大統領は景気刺激策を重視しているので、基本的に「金利を下げたい」という考えを持っています。
一方で、FRBは物価の安定を最優先しているため、物価が上昇していたり、賃金の上昇が続いていたりする現在の状況では、金利を維持、あるいは上げたままにしておきたいというスタンスをとっています。
こういったスタンスの違いから、FRBと大統領の間で、政策に対する意見のズレがあると言われているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうした意見の対立があった場合、やはり最終的には中央銀行の判断が優先されるのでしょうか?
郡司教授:基本的に、先進国の中央銀行制度では、中央銀行が政府から独立して金融政策を決められるようになっています。
とはいえ、もちろん国によって制度の違いはあります。例えば、イギリスの場合、目標とするインフレ率を政府が決めることができるとされているのです。
一方、アメリカや日本では、中央銀行が物価の安定などの目標を最優先にして動く独立性が保障されているため、たとえ政府が「金利を下げてほしい」と求めても、中央銀行側が判断すればそれに従わないということも普通にあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。中央銀行は政治的な意向と距離をとりつつ、中立的な立場から政策を進めているのですね。
郡司教授:その通りです。その意味では、金融政策は政治とはまた異なる論理で動いている部分が大きいと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ここまで様々なお話をしていただきましたが、これから私たちが日々生活していく上で、特に気をつけておくべきポイントや、経済ニュースを見るときに意識しておきたい点があれば教えていただけますか?
郡司教授:先ほども少し触れましたが、今後、日銀が長期的にどう金融政策を変えていくのかという点は、お金を「貯める」時にも「借りる」時にも非常に重要になってきます。
そのため、日銀が政策金利を上げた、下げたといった報道だけでなく、それを決定している「日銀の委員たちの発言」にも注目しておくと、より精度の高い判断ができるようになるでしょう。
日銀の金融政策は、総裁1人、副総裁2人、そして審議委員6人の合計9人で決められています。
そのうちの誰がどんな発言をしているかによって、次の政策の方向性を読み取ることができる場合もあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:具体的にはどれくらいの頻度で発言があるのでしょうか?
郡司教授:だいたい2〜3週間に1回程度、何らかの講演やコメントがニュースになることが多いですね。
ただ、金融政策が注目されている局面では、1週間に何度もニュースが出てくることもあります。
これらの発言は、政策の方向性を読み取る上で非常に重要です。
特に、住宅ローンを組む予定のある方や、まとまった資金を長期的に運用しようと考えている方には、ぜひチェックしていただきたいと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:今のお話の中で、「委員の発言をチェックするのが良い」ということでしたが、具体的にどんなキーワードや文脈があれば、特に注目しておいた方が良いのでしょうか?
郡司教授:日銀のホームページには、委員の講演や記者会見が掲載されているのですが、内容がやや専門的で、一般の方にはやや難解かもしれません。
そのため、新聞やテレビ、ネットニュースなどで、そうした発言を要約したものをご覧になるのが現実的だと思います。
報道の中では、日銀委員が「金利を引き上げる意思を示した」や「金利を維持する姿勢を示した」といった表現がよく使われます。
例えば「利上げに前向き」といった表現が出たら、将来的に金利が上がる可能性が高いというシグナルです。一方、「現状維持」や「慎重な姿勢」などが目立つようなら、すぐに金利が動く可能性は低いかもしれません。
このように、日常の経済ニュースにも経済に関するヒントは数多く散りばめられています。まずは、そうした表現に注目する視点を少し加えるところからニュースを見ることを始めてみていただきたいですね。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年7月4日