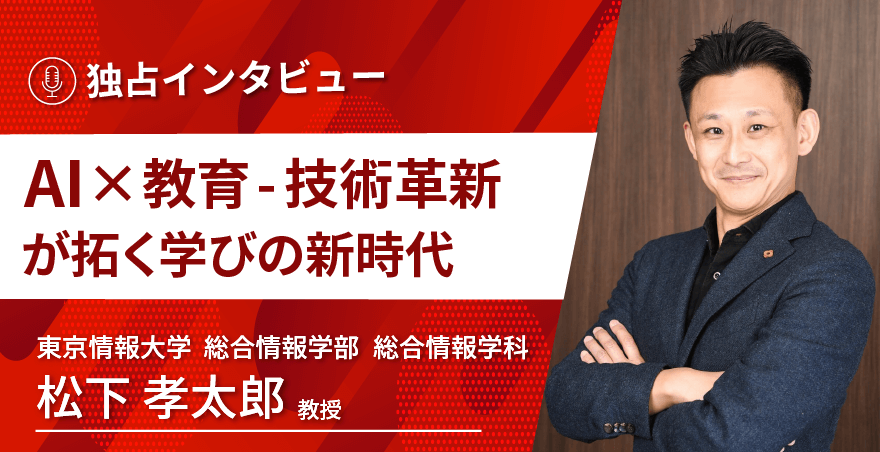テクノロジーの進化は、私たちの生活だけでなく、教育の世界にも革新をもたらしています。AIの活用によってこれまでの学びの常識が大きく変わりつつある今、こうした技術革新は本当に教育の質を向上させるのでしょうか?
そこで今回、東京情報大学の松下孝太郎教授に、技術革新が拓く学びの新時代について、独自取材を通じてお話を伺いました。
AIの進化とともに、教育の形も変わる現代で、私たちはどのように学びを活用していくべきなのか、本インタビューを通じてそのヒントを探っていきましょう!

東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科
松下孝太郎(マツシタ コウタロウ) 教授
横浜国立大学大学院工学科研究科にて博士(工学)を取得。
2006年より(学校法人 東京農業大学)東京情報大学環境情報学科にて講師、
2010年より同大学情報文化学科にて准教授、
2016年より現職に至る。2023年より東京情報大学総合情報研究所所長を兼任。
〈研究分野〉
画像工学・コンピュータグラフィックス・教育工学
〈著書・論文〉
『親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑【Scratch 3.0対応版】』(2019)
『スクラッチプログラミング事例大全集』(2020)
『スクラッチプログラミングゲーム大全集』(2023)
他、多数。
生成系AIと教育の融合
カードローンの窓口合同会社 編集部: そもそも、現在の教育現場ではAIがどのように活用されているのでしょうか?
松下教授:例えば、教材では単純な図表などがAIによって生成されています。こうした図表は、教材として十分に活用できるレベルで生成できるようになっているのです。
他にも、単純な写真やイラストなどもAIで作成できるため、視覚的に分かりやすい資料を作る際にも活用されています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。資料作成以外ではどのような活用方法があるのでしょうか?
松下教授:そうですね。大学の話にはなりますが、私たちの学科では情報系の授業としてプログラミングを教えています。
このプログラミングのコードも、AIに作らせることができるのです。
もちろん、私や他の先生が作成したものを学生に提供することもできますが、基本的なコードは誰が書いても似たようなものになります。そういう点では、AIは単純な教材作成に向いていると言えるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ということは、小学校から大学・大学院まで、幅広い教育分野でAIは活用できるのですね。
松下教授:はい。学校の段階を問わず、AIが生成した教材は十分に実用的なレベルに達しています。
特にプログラミングの分野では、「こういうプログラムを作って」と指示すれば、AIがコードを生成するだけではなく、その解説までしてくれるのですよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:解説までしてくれるのは便利ですね。学習のサポートにもなりそうです。
松下教授:そうですね。以前はネットでは基本的な命令やコードを調べる程度でしたが、今ではAIがコードに加え、コードの意味や仕組みまで説明してくれるので、学習効果も高まると思います。
特にプログラミング初心者の方にとっては、試行錯誤しながら学べる良い環境に整いつつあるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。今は情報系の大学における活用方法を紹介していただきましたが、一般の小中高や文系の大学ではどのようにAIを活用できるのでしょうか?
松下教授:情報系以外の教育現場だと、例えば子どもたちが喜ぶものとして「電子紙芝居」が簡単に作れるようになりました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:面白そうですね!具体的には、どのように作成するのでしょうか?
松下教授:電子紙芝居は、最近話題のChatGPTを使って作成できます。
例えば、「こんな感じの物語を作ってください」という大まかな指示を出すと、AIがストーリーを生成してくれます。
そこに登場するキャラクターのイメージを、今度は画像生成系のAIに入力すると、イラストなどの視覚的な素材も自分で作成できます。
このようにして、生成された物語とイラストを組み合わせれば、あっという間に絵本が完成するのです。
ちなみに、私が教えている学生たちは、画像生成AIのStabel Diffusion(ステーブルディフュージョン)をよく使っています。無料で利用できるツールなので、先生や学生たちはもちろん、子どもたちでも楽しみながら絵本を作れるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:子どもから大人まで楽しめそうですね。そんなAIですが、活用する人が増える一方で「考える力」が衰えるのではないかと心配する声もあります。この点について、松下様はどうお考えですか?
松下教授:そうですね。最近の学生の提出物を見ていると、「これは生成系AIを使ったのでは?」と感じることもあります。
これは先生の立場からするとちょっと困りますが、技術の発展により生活が便利になってきたと考えれば、時代の流れとして受け入れる必要があるのかもしれません。
先ほどもお話しましたが、AIというのは単純な文章や絵などはかなり正確に生成できるようになりました。だからこそ、今後はAIの生成物をそのまま利用するのではなく、それらをどう活用し、組み合わせるかという「融合する力」が求められるのではないかと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「融合する力」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?
松下教授:例えば、電子紙芝居を作る場合、AIはストーリーやイラストを生成できますよね。しかし、それらをどう組み合わせるかは人間が考えなければなりません。
これは単なる作業ではなく、情報を整理し、全体の構成を考える力が必要になってきます。
こうした「組み合わせる力」は、今後AI技術がさらに進化したとしても、人間にとって重要なスキルとして求められるだろうと考えているのです。
カードローンの窓口合同会社:ありがとうございます。松下様は「スクラッチプログラミング」に関連する書籍を多数出版されていますよね。このようなスクラッチプログラミングと生成AIの融合が進むと、どのような教育的価値が見込まれるのでしょうか?
松下教授:前提として、小学校では2020年からプログラミング教育が必修化されました。
ただし、この教育の目的は、子どもたちが必ずしもプログラミングの技術を習得することではなく、プログラミング的な考え方を学ぶことにあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。小学校でのプログラミング教育は、技術そのものよりも考え方を重視しているのですね。
松下教授:そうですね。技術的な内容は中学校以降で本格的に学ぶことになります。
とはいえ、プログラミング教室がたくさんあることからも分かるように、小学生の中にもプログラミングが好きな子は多いですし、実際に学校でもプログラミングを扱う機会が増えてきています。
ただし、プログラミングが好きな子ばかりではないのも事実で、全体としては「プログラミングが大好き」という子は半数以下だと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、全員が全員プログラミングに興味を持つわけではないですし、中には苦手意識を持っている子どももいると思います。
松下教授:そうなんです。みんなが興味を持っているわけではなく、他の分野に関心があることも多いですよね。
どの学問にも共通ですが、勉強というのは興味がないとなかなか取り組めないものです。ただ子どもに「プログラミングをやれ」と教えても、興味がなければやりたくないですし、ますますプログラミングから遠ざかってしまいます。
そこで私は、どうすれば子どもたちがプログラミングに興味を持ってもらえるかを考え、大学生にも協力してもらいながら研究を進めています。
現在は小学生もスマホを持っていて、写真や動画を撮るのが好きな子も多いですよね。この「みんなが好きなこと」をプログラミングに活用できないかと考えました。
それが私が学会でも提唱した、「コンテンツ利用プログラミング」という手法です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:コンテンツ利用プログラミングとは、具体的にどういうものなのでしょうか?
松下教授:コンテンツ利用プログラミングは、撮影した画像や録音した音声、さらには生成系AIといったコンテンツをプログラミングにより制御する手法です。
簡単に言うと、「写真やイラストなどのコンテンツをプログラミングにより動かす」ことです。
なぜ「コンテンツ」と呼んでいるかというと、写真や音声、動画が融合することで、より多様な表現が可能になるからです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。このコンテンツ利用プログラミングに使われているのがスクラッチプログラミングなのでしょうか?
松下教授:その通りです。これらのコンテンツをプログラミングで動かす際、最も簡単に扱えるのがスクラッチです。
プログラミング初心者が専門的なコードを書くのは難しいですが、スクラッチならブロックを組み合わせるだけでプログラミングができます。
このようにスクラッチを利用すれば、自分で撮った写真やAIで生成したイラストなどを自由自在に動かして、オリジナルの作品が作れるわけです。
例えば、近くの公園を撮影して観光案内を作ったり、生成系AIで作成したキャラクターを動かして電子絵本のような作品を作ったりすることもできますよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:子どもたちが自分の興味を活かしながらプログラミングに取り組めるのは非常に魅力的ですね!
松下教授:そうですね。このように、スクラッチと生成系AIを組み合わせることで、子どもたちも楽しみながらプログラミングに触れることができます。
今後、この分野が発展することで、さらに様々な可能性が生まれることに期待したいです。
教育現場でのAI活用
カードローンの窓口合同会社 編集部: AIは便利ですが、教育現場で活用する際には注意しなければならない点もいくつかあると思います。実際、AIを教育現場に導入する場合、どのような技術的ハードルがあるのでしょうか?
松下教授:これは私も常々考えていることなのですが、まずアカウントを取得する作業が意外と面倒だと思います。
普段からコンピューターに触れている方であればそれほど難しくありませんが、シニアの利用者もいらっしゃるでしょうし、その点がハードルになるかもしれません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:見落としがちですが、アカウントの取得は重要な最初のステップですね。
松下教授:そうなんです。
また、生成系AIツールは頻繁にインターフェースが変わるので、「ログイン方法が分からない」なんてことも起きます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、パソコン操作に慣れていない方だとログインするだけで一苦労ですね。
松下教授:その通りです。他にも、頻繁に変わるルールの把握など、アカウント管理の煩雑さが導入のハードルになっています。
ソフトウェアのバージョンアップによる操作変更も避けられませんから、コンピューターに慣れている人でもストレスを感じるポイントだと思います。
また、最近は日本語対応が増えてきたとはいえ、日本語未対応のツールもまだ多く存在します。
例えば、ChatGPTは日本語入力に対応していますが、画像生成や動画系のツールでは英語が必要になるケースも多いのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:その場合、翻訳しても意図が正しく伝わるか不安になりそうですね。そう考えるとAIの導入はハードルが高いように思いますが、教育現場ではどのような対応を取っているのでしょうか?
松下教授:主に行っているのは教師のトレーニングです。
例えば、私は千葉県の教育委員会から依頼を受けて、小中高の先生向けに技術的トレーニングを実施しています。
先生方は学生時代にプログラミングを学んでいない世代が多いので、情報の専門家である私がスクラッチプログラミングなどの指導を行っているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:現場の先生方の負担は大きそうですね。
松下教授:そうですね。小中高の先生方は非常に忙しいので、新しいスキルを学ぶ時間を確保するのが難しいという現状があります。
そのため、実際の業務の中で少しずつスキルを身に着ける形になっているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。教育現場では、生成AIによるコンテンツの質や信頼性、データの取り扱い、プライバシーなど、倫理的な問題も懸念されていますよね。これらの問題にはどう取り組んでいくべきなのでしょうか?
松下教授:生成系AIに関しては、特に著作権の取り扱いが大きな問題となっています。
私自身、本を出版する中で時々講演の依頼を受けることがあります。その際、著作権について、複数の著書の共著者でもある横浜国立大学の山本光先生とともにお話する機会がありました。
その講演でも触れましたが、かつて著作権に関するルールは比較的シンプルでした。しかし、最近はAI技術の進展に伴い、状況が非常に複雑になってきているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、AIに関する法整備が追い付いていないのですね。
松下教授:その通りです。現在、著作権は国ごとに異なる法律が適用されており、それぞれの国の規則を確認することが求められます。
また、生成AIツールには必ず利用規約があり、それに則って使用しなければなりません。例えば、「自由に利用可能」なのか、「個人利用に限る」のか、「公開は可能だが商業利用は禁止」なのかなど、細かく利用条件が定められています。
そのため、個人利用の範囲ではそれほど気にする必要はないかもしれませんが、外部に公開する際には、必ず利用規約を確認することが重要です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、AIに限らず、利用するコンテンツのルールを把握することは大切ですね。
松下教授:もう1つ重要なのは、コンテンツの信頼性です。一般的に、生成AIは膨大なデータを学習しており、特にメジャーな情報については信頼性が高い傾向にあります。
例えば、「東京タワー」といった広く知られた情報は、比較的正確に生成されることが多いのです。
一方で、「東京情報大学」に関する情報のように、一般的にあまり知られていない内容に関しては、誤った情報が含まれる可能性があります。
そのため、生成された情報が正しいかどうかを確認するために、書籍や他の信頼できるネット資料を使ってダブルチェック、トリプルチェックを行うことが欠かせません。
趣味で楽しむ分には大きな問題にならないかもしれませんが、仕事や学術的な場面で利用する場合は、慎重に情報を精査する必要があります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。では、教育者がAIを適切に活用するためには、どのような工夫が求められるのでしょうか?
松下教授:これは難しいところで、「こうすれば良い」と一概には言えません。
それはなぜかというと、生成AIの分野はまだ発展途上であり、何がメジャーになるかは予測しにくいからです。
現在、ChatGPTやStabel Diffusionなどが一定の地位を築いていますが、それらもバージョンアップやインターフェースの変更が頻繁に行われ、技術的にはまだ安定しているとは言えません。
教育者としては、「このツールを学べば十分」と決めつけるのではなく、柔軟に対応する姿勢が必要になると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、技術の進化が早い分、1つの学習方法に固執してしまうのはあまり良いと言えないのかもしれませんね。
松下教授:私は学生たちにも、まずはメジャーなツールを押さえておくことを勧めています。
また、これは専門家を目指す場合に必要なことですが、最新情報を定期的にアップデートし、今使っているツールが本当に有用なのかを確認することも大切です。
現在主流のツールも、今後使われ続ける保証はありません。新しい技術が登場する可能性もあります。そのため、メジャーなツールを活用しつつ、情報のアップデートを怠らないように意識すると良いのではないでしょうか。
未来の教育とAI
カードローンの窓口合同会社 編集部: AIとプログラミング教育が融合しつつある今、学生たちはどのようなスキルを身に着け、将来的にどのようなキャリアや社会での役割を担うことができるのでしょうか?
松下教授:AIを活用すると、単に入力すれば答えが出るため、創造力が必要ないと考える方もいるかもしれません。
しかし、今回お話したような「組み合わせる力」をはじめとして、AIの活用には様々な能力が求められます。
例えば、画像を生成する場合でも、何の計画もなく単にキーワードを入れるだけでは、思ったような結果にはなりません。つまり、望んだものを出すためには細かく指示を出す必要があるのです。
そうしたプロセスを通じて、今までとは異なる形の創造力や論理的思考力が確実に身に付くと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。他に身に付くスキルや、将来に役立つ点などはあるのでしょうか?
松下教授:そうですね。リモートワークの場面においても、こうしたスキルがあれば簡単に業務を効率化できると思います。
私は企業で働いているわけではないので、実際の現場でどこまで浸透するかは分かりませんが、例えばプログラミングにしてもコードをだらだら書くのではなく、ある程度まとまった機能として作り、それを呼び出して使うことが一般的です。
これまでなら、リファレンスを参照しながら手作業で確認する必要がありましたが、現在はChatGPTのようなAIを活用すれば、すぐに必要な情報が得られ、しかも解説までしてくれます。
そのため、ある程度の規模のプログラムを書く際も、誰が書いても同じようなものになる部分は生成AIに任せ、それを適切に組み合わせることで仕事の効率化が図れるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:基礎部分をAIに任せるというのは、エンジニアだけでなく他の職種でも活かせそうですね。
松下教授:その通りです。今はエンジニアを例に挙げましたが、プレゼン資料を作成するような営業職、事務職でも活用できると思います。
また、私自身もAIツールを活用することで作業を効率化できるようになりました。
例えば、書籍に入れるイラストをデザイナーさんに依頼する場合、イメージが分かるようにお絵かきソフトなどで簡単なラフを描いていました。ですが、最近では出版社の方から「そこは生成系AIに作らせて貼っておいて頂ければ、それを参考にデザイナーさんに作成してもらいます。」と言われることがあります。
つまり、AIを文房具のように使いながら作業を進められるようになったのです。こうしたツールを活用すれば、資料の作成なども格段に効率化され、本来必要な知的作業に集中できるようになるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:AIの活用範囲は本当に広がっているのですね。では最後に、松下様は今後AIを活用してどのような未来の教育を実現したいとお考えか、教えていただけますか?
松下教授:現在、私はAIを利用した研究教育では「コンテンツ利用プログラミング」や「電子紙芝居」を作る取り組みをしています。そんな中、AIの登場によって、コンピューター操作が難しかった年配の方々も、より身近にコンピューターに親しめるようになるのではないかと考えています。
私自身、近隣の教育委員会からの依頼で小中高の先生方を指導するだけでなく、シニア向けのコンピューター指導も行っています。
2020年からプログラミング教育が必修化されましたが、シニア世代の方々は、「孫が学校でプログラミングを学んでいるらしい」ということをよく知っているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。お孫さんの影響でプログラミングに関心を持たれる方が多いのですね。
松下教授:そうなんです。10年くらい前だったら、「孫と一緒にプログラミングをやろう」と思ってもコードを書く必要があるため、プログラミング未経験のシニア世代の方が取り組むのは難しかったでしょう。
しかし、現在はスクラッチのようなビジュアルプログラミングを使って、簡単にプログラミングができます。さらに、「コンテンツ利用プログラミング」であれば、親子や祖父母が一緒に素材を撮影し、プログラムに取り入れることも可能です。
こうした活動が広まれば、単にコンピューターに触れるだけでなく、世代を超えたコミュニケーションの場が生まれるのではないでしょうか。
まだ実証段階には至っていませんが、将来的にプログラミングやAIが、親や祖父母と一緒に楽しめるものになる可能性もあると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:確かに、AIは使い方次第で世代を超えた学びの場を提供できそうですね。
松下教授:はい。今の学生を見ていると、以前はゼミ室でワイワイと会話していたのに、スマホが普及してからは部屋に入るとすぐにスマホを見ていることが多くなった気がします。
こうした状況において、生成AIやプログラミングを活用することで、世代を超えて一緒に学び、楽しめる機会を増やせるのではないでしょうか。また、こうした活動がコミュニケーション能力の向上にも寄与することを期待しています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:スマホは便利ですが、それ1台で完結してしまう点はコミュニケーションの阻害になり得てしまうのかもしれません。今後のAI活用によるコミュニティの広がりに期待したいですね。
松下教授:そうですね。
未来の教育というのは、おそらく今とは全く違うものになっているでしょう。教育の効率化が進み、教師自身も成長しながら、より効率的な指導が可能になるのではないかと思います。
私は今後、「コンテンツ利用プログラミング」を軸に、スマホや生成AIを活用し、プログラミングと画像制作を組み合わせた学習方法を探求するプロジェクトを進めていきたいと考えています。
最終的な目標は、「学生が情報技術全般に興味を持てるようにする」ことです。その実現に向けて、これからも研究を続けていきます。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年1月24日