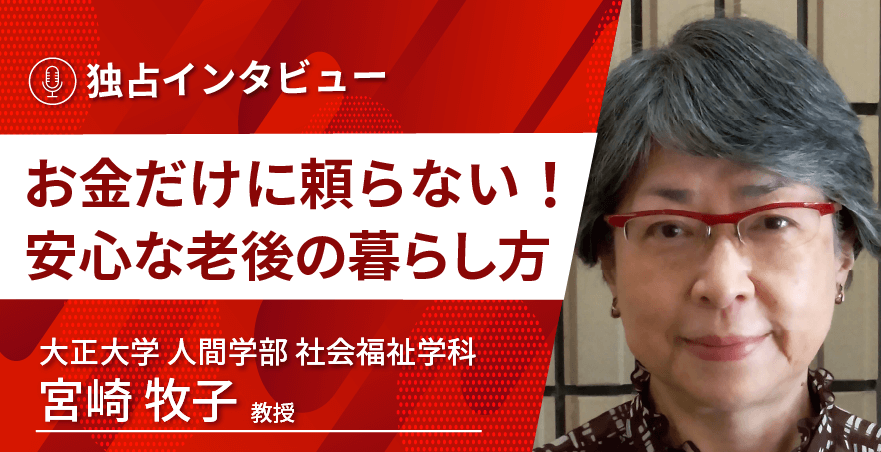人生100年時代を迎え、老後の経済的な備えはますます重要視されています。
一方で、高齢者が抱える不安は経済面だけにとどまらず、健康や認知症のリスク、住み慣れた地域での生活継続など、多面的な課題が浮き彫りになっています。
そこで今回は、社会福祉の専門家である宮崎教授に、老後の安心を支える経済的準備以外の要素、特に「地域」や「人とのつながり」の役割について伺いました。
フレイル予防や地域活動の具体例を通じて、社会全体で取り組むべき課題と解決策を多角的に探っていきます。

大正大学 人間学部 社会福祉学科
宮崎 牧子(ミヤザキ マキコ)教授
日本女子大学文学部社会福祉学科を卒業後、1986年に日本女子大学大学院社会福祉学専攻を修了。その後、社会福祉法人東京弘済園非常勤職員、介護福祉士養成の専門学校教員を務める。
1997年より大正大学人間学部社会福祉学科専任講師・助教授を経て、2006年より現職。その他、全国老人福祉問題研究会事務局長、日本ソーシャルワーカー協会副会長、豊島区介護保険事業計画推進会議会長、区民ひろば西巣鴨運営協議会委員などを兼任。
研究分野は社会福祉。主に高齢者福祉・地域福祉に焦点を当てて研究している。
“老後の不安”の正体とは?
カードローンの窓口合同会社 編集部:さっそくですが、現代の高齢者の方々が日々の生活の中で抱えている主な不安や課題には、どのようなものがあるとお感じでしょうか?
宮崎教授:高齢期は非常に長くなっており、昔は人生50年時代で60歳というと、60歳以上生きられる人は少数でした。
しかし、今は人生80年どころか、人生100年時代と言われています。
現在、65歳から高齢者となっていますが、70代くらいまでは比較的元気な方が多いので、高齢期でも世代によって課題が異なります。
例えば、高齢期に入る前の50代後半から70代くらいの人たちは、経済的な不安や、自分が癌や病気になったらどうしようか、あるいは認知症になることへの不安を抱えていると思います。
特に最近は認知症に対する不安が大きいようです。
一方、80代以降になると、無事に80歳を迎えることができたという安心感がある一方で、例えば夫婦で2人暮らしをしていた場合、どちらかが亡くなるということを考えるようになります。
そうした時に、1人になったらどうするのだろうかという不安や、長年住み慣れた地域や家で最後まで生活できるのだろうか、もしできなくなった場合はどうすれば良いのかといったことを考えるようになります。
安心して最後までいられる場所、つまり生活できる場所をどのように探せば見つかるのだろうか、それは自宅なのか、という不安を抱えるようです。
人生の最後を過ごす場所を探すということは、介護問題にも繋がってくると思います。
家族に最後を看てもらうことができるのか、あるいは家族がいても期待できない、または家族がいないため、施設を利用するのか。
施設を利用して安心して過ごしたいけれど、そのような施設が見つかるのだろうか、といった不安があると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。高齢期の中でも年代によって不安や課題が異なるというお話、とても興味深く感じました。
そうした中で、安心して暮らせる老後を考える上では、経済的な備えがもちろん大切かと思いますが、それ以外にも必要なことはあるでしょうか?
例えば、人とのつながりなどについて、どのようにお考えでしょうか?
宮崎教授:もちろん、人や地域とのつながりは非常に大切だと思います。特に注目されているのが「フレイル予防」です。
フレイルとは、心身の活力が低下していく状態(虚弱・衰弱状態)のことで、放置すると寝たきりや認知症につながる恐れがあります。
そのため、現在はこのフレイルの予防に力が入れられています。
特に高齢期においては、フレイル予防が非常に重要です。
フレイルを予防するためには、心身の活力を低下させないようにするために、3つの大切なことがあると言われています。1つ目は食事、2つ目は運動、そして3つ目が社会参加です。
これらの3つの柱を日常生活の中でバランス良く取り入れることが、フレイル予防に繋がります。
そして、フレイルを予防することは、人や地域との繋がりを深めることにも繋がっていくのです。
例えば、社会参加をしていくことは、その人が地域の中で何か自分にできることや楽しみを見つけたり、あるいはどこかに出かけて行って活動したりすることです。
フレイル予防をすることは、人と地域との繋がりが不可欠になります。
また、運動もスポーツセンターに行って運動するだけでなく、毎日散歩をしたり、あるいはラジオ体操をすることも有効です。
特にコロナ禍以降、再び注目されているのがラジオ体操です。
多くの地域では、公園などに早朝(例:朝6時)に人が集まり、音楽に合わせて体操をしています。
その場で「おはようございます」と挨拶を交わしたり、軽い会話をしたりすることで、自然と人間関係が育まれていきます。
また、いつも来ている人がいないと心配になるといったような、地域の見守りの機能も生まれています。
このように、地域の中でラジオ体操があるということは、フレイル予防にも繋がります。
特にコロナ禍では、三密(密閉・密集・密接)を避ける必要があった中で、屋外でのラジオ体操は換気の心配もなく、マスクをしながらでも安心して参加できる活動として再評価されました。
大声での会話こそ控えられていましたが、顔を合わせて挨拶を交わすことができることで、お互いの元気を確認し合える貴重な場となりました。
様々な活動が制限される中で、比較的早い段階でラジオ体操が再開されました。
多くの高齢者が定期的に外出し、心身の活力や筋力の低下を防ぐことに繋がっています。
そのため、人や地域とのつながりは、安心して暮らせる老後を支える非常に重要な要素だと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。
コロナ禍という困難な状況の中でも、安心して参加できる場があったことで、多くの高齢者の方々が支えられていたんですね。
孤立しない老後は、地域とのつながりから生まれる
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほどのラジオ体操のお話も踏まえて、地域のコミュニティや人とのつながりが高齢者の暮らしにどのような影響や効果を与えているとお考えでしょうか?
宮崎教授:仕事をしている時は、毎日決まった時間に出かける場所ややるべきことがありました。
しかし、リタイアするとそうした「日々の目的」が見えにくくなります。
そんな時に、地域とのつながりがあると「ここに行けば自分のことを必要としてくれる人がいる」という目的ができるので、例えば「明日の10時にこの場所に行こう」といった予定を立てやすくなります。
地域との繋がりがあることで、出かける場所や予定ができ、外出することで様々な人と出会うことが可能になります。
また、外出するときには、歩いたり、自転車に乗ったり、地域によっては車で遠くまで出かけたりすることもあります。
つまり、外出は体を動かすことにつながります。高齢者の方が体を動かすことで、脚力や筋力を保ち、骨を丈夫にする効果も期待できるのです。
予定を立てたり、予定があるということは、そのための準備をすることにもつながります。
仕事をしている時は、仕事の準備をしていましたが、それだけではありません。
例えば、「明日、誰々さんと会うから何を着ていこうかな」と考えるようになります。
普段あまり人に会わず家にいると、服装も適当になりがちですが、予定があると服装にも気を遣うようになります。
暑ければ涼しい服を選んだり、気温が下がってくれば秋らしい服を選んだり、マフラーを巻いたりと、季節に合わせて服装を考えるようになります。
また、人に会うから髪を整えたり、髭を剃ったりと、身だしなみを整えることも心と体の活力につながります。
予定があるということは、楽しみがあるということです。
明日誰々さんと会う、孫と会う、地域の人たちと食事をするなど、楽しみがあるとワクワクして気持ちも明るくなります。
高齢者の方は、曜日の感覚が薄れてしまうことがあります。
毎日が休日のように感じられるため、予定を作ることは曜日感覚を保つ助けにもなります。
また、人と会うことは、話したり声を出したりする機会にもつながります。
高齢になると一人暮らしの方も増え、声に出して話す機会が減ってしまいますが、人と出会い、会話をしたり、笑い合ったり、驚き合ったり、悲しみを分かち合ったりすることで、全身に良い刺激がいきわたります。
さらに、様々な年代の人と交流することで、新しいことを学ぶこともできます。
例えば、若い人が使う言葉の意味を聞いて知ることで、新しい情報を得ることができます。
このように地域とのつながりがあることで、高齢期になっても意欲が高まり、健康につながり、楽しみが増えて生きがいにもつながることが多いのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、地域とのつながりが心身の健康だけでなく、生きがいにもつながっているのですね。
そうしたお話を聞くと、具体的にどのような社会福祉の取り組みや成功事例があるのか、とても気になります。
これまでのご経験の中で、特に印象に残っているものがあれば教えていただけますか?
宮崎教授:大正大学社会福祉学科の学生が行っている「学生出前定期便」という活動があります。
この活動は12年ほど続いていますが、始まりは大学院生の研究がきっかけでした。
大学院生が地域の町内会役員の方々にインタビューした際、大正大学周辺で町内会活動を熱心に行っていた高齢者の方から「研究したことをぜひ地域の活動として取り組んでほしい」というメッセージをいただきました。
そこで、町内会の役員の方々に「どんなサポートがあれば助かりますか」と尋ねたところ、「高齢者のちょっとした困り事を手伝ってくれる活動があればうれしい」という意見が出て、それが「学生出前定期便」誕生のきっかけとなりました。
現在、この活動は一時中断する時期もありましたが、なんとか12年間続けることができています。
この活動を支えているのは、大正大学の学生の力だけでなく、豊島区民社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーの存在が非常に大きいです。
学生が活動を続けられるのは、彼らがしっかりバックアップしてくれているからこそです。
さらに、コミュニティソーシャルワーカーを支えているのは区民社協であり、区民社協は豊島区の行政によりサポートされています。
このように、自治体と社会福祉法人である社会福祉協議会との連携によって、大正大学の学生は地域で高齢者のちょっとした困り事を支援する活動を続けているのです。
具体的には、庭の草むしりが一人暮らしや高齢夫婦には大変というケースがあり、その依頼を受けて学生が手伝います。
また、換気扇の油汚れ掃除の依頼や、電球・蛍光灯の交換、カーテンの取り替えなどもサポートしています。
学生たちは「出前定期便」として高齢者の自宅を訪問し、こうした問題を解決しています。
コミュニティソーシャルワーカーのバックアップがあるため、学生が困る場面はほとんどありません。
換気扇掃除に関しては、自分の家でやるのとは勝手が違うので、学生は事前にインターネットで簡単な油汚れの取り方を調べてから訪問するなど、しっかり準備をしています。
また、学生が草むしりや換気扇掃除をしているとき、高齢者の方もできる範囲で一緒に協力しているのが素晴らしいところです。
例えば、高齢者は一人で草むしりができなくても、学生がまとめた雑草を袋に入れたり、暑いので休むよう声をかけたり、換気扇掃除の際に手袋を用意したりと、無理のない形で参加されています。
こうした共同作業の中で世代間交流が生まれており、とても良い関係が築かれていると感じます。
このような活動が全国に広がれば、高齢者の生活を支える新たなモデルになるのではないかと期待しています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:素敵な取り組みですね。学生さんたちが地域の高齢者の方々と直接関わることで、世代を超えた絆が生まれているのがよく伝わってきます。
「このまちで生きていく」暮らしを支えるために
カードローンの窓口合同会社 編集部:続いて、住み慣れた地域で暮らし続けることは、高齢者の方々にとってどのような意味や価値があるとお考えですか?
宮崎教授:そうですね。住み慣れた地域というのは、高齢者の方にとって愛着のある場所だと思います。
地域に愛着を持つということは非常に大切です。
愛着は簡単に作られるものではなく、長く住んでいる中で「この地域は安心して暮らせる」と感じたり、顔なじみの人がいたり、どこに行けば何が買えるかを知っていたり、顔なじみの店員さんがいるお店があったりすることで生まれます。
長く住んでいることが愛着に繋がりやすいですが、定年退職後に引っ越してくる人もいます。
60代後半から70代の元気な高齢者の方々が、暮らしやすい地域にしたいから、元気なうちに地域の活動に参加したいという気持ちを持っている方もいます。
元気な高齢者の方々が「もっと暮らしやすい地域にしたい」という気持ちを持って取り組むことで、住み慣れた地域で暮らし続けることの意味や価値が、人生の最後に「この地域で暮らしてきて良かった」と思えることに繋がると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど、地域への愛着や安心感が高齢者の方の暮らしに大きな意味を持つのですね。
最後に、これからの高齢化社会を見据えて、若い世代や地域の皆さんにはどんな心構えや行動が大切だと思われますか?
宮崎教授:若い世代の方々には、同じ年齢の人と楽しむだけでなく、年齢の違う人とも交流してみようという姿勢を持ってほしいと思います。
高齢者は頑固だとか、自慢話ばかりするから嫌だという固定観念を払拭してほしいと思います。
若い世代に求めるだけでなく、高齢者世代も頑固さを和らげ、自慢話ばかりするのではなく、若い人の話にも耳を傾けるよう努めましょう。
一方、特に若い世代には、年齢の違う人ともっと交流してみようという姿勢を持ってほしいと思います。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年8月20日