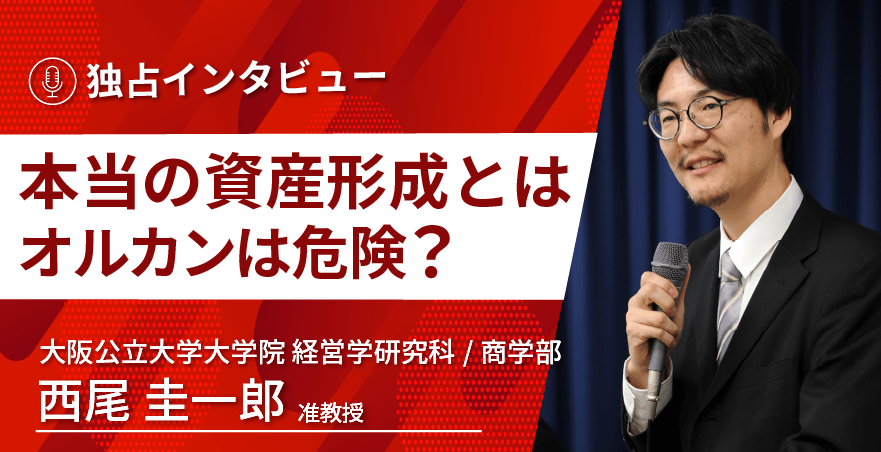「とりあえずオルカン」「とりあえずNISA」。そんな言葉がSNSを中心に広がり、投資は今や当たり前のものになりつつあります。しかし、よく考えずに始めた投資が、大きなリスクに繋がることもあるのです。
そこで今回、大阪公立大学の西尾圭一郎准教授に、本当に大切な資産形成とそのポイントについて独自取材を通じてお話を伺いました。
利益を追う前に本当に考えるべきこととは何か、西尾准教授のお話から考えていきましょう。

大阪公立大学大学院 経営学研究科/商学部
西尾圭一郎(ニシオ ケイイチロウ) 准教授
大阪市立大学を卒業後、同大学大学院にて博士(商学)を取得。
2007年ノースジア大学経済学部講師、2009年松山大学経済学部准教授、2015年愛知教育大学教育学部講師、2018年同大学准教授を経て2023年より現職。
〈研究分野〉
金融教育・金融システム・金融機関経営・外国為替・国際通貨・インド経済・アジア経済
〈著書・論文〉
「貨幣とは何か? : 支払決済システムと金融仲介」(2024年、共著)
「変わる時代の金融論」(2023年、共著)
「オルカン万能論」に流される人たち―投資が”目的”からズレる時
カードローンの窓口合同会社 編集部:最近、若い世代の間で「とりあえずオルカン」「とりあえずS&P500」という言葉が合言葉のように広がっていますが、この現象についてどのようにお考えでしょうか?
西尾准教授:良い面と悪い面の両方がありますね。
良い点としては、投資に不慣れな人でも、「とりあえず」と言われるオルカンのような商品は始めやすい選択肢になっていることが挙げられます。
実際に、これまで投資に触れてこなかった層が投資を始めるきっかけとしては非常に有効でしょう。
ただ、その「とっつきやすさ」が逆に問題を引き起こすこともあります。
例えば、「とりあえずオルカン」と言っている人の中には、自分でいろいろ調べたり考えたりした末に、「やっぱりオルカンがいいな」とたどり着いた人もいれば、なんとなく周囲がそう言っているから選んでしまった、という人もいるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、同じ商品を選んでいたとしても、その選び方や背景にある考え方に大きな差があるということですね。
西尾准教授:その通りです。前者のように自分で考えてたどり着いた人は良いですが、後者のように理由も分からず投資商品を選んだ人の場合、いざ損をした時に、すぐに狼狽してしまう傾向があります。
また、後者は自分で納得して投資していない分、損をした時に「友達に勧められたから投資したのに」「SNSで見た人のせいで損をした」といった他人への責任転嫁に走りやすくなります。
SNSで発信していた人などに対して、攻撃的な言動を取ってしまう人もでるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:投資そのものではなく、周囲との関係まで悪化させてしまう恐れがあるわけですね。
西尾准教授:「目的意識のない投資」には、他にも大きなリスクがあります。
投資をする上で本来必要なのは、「何のためにお金を増やすのか」という明確な目的です。
例えば、「老後にいくら必要なのか」「どんな生活を送りたいのか」といったイメージがあって初めて、金融商品を選ぶ意味は出てきます。
しかし、「とりあえず増えたら嬉しい」という考え方だけで動くと、いつまでもゴールが見えてきません。人間の欲望は無限ですから、ゴールが明確ではないままだと、いくら資産が増えても満足できないのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。増やすこと自体が目的になってしまうと、「いつ辞めるか」「どう使うか」といった判断が難しくなりそうです。
西尾准教授:そうですね。投資では、どこかで利益を確定させなければなりませんが、目的がなければ引き際が分からず、際限なくリスクを取り続けてしまいます。
結果として、暴落が起きても正しい対処法が分からず、パニックに陥ってしまうのです。
加えて、もう一つの問題は、預金より利回りが良いからといって全財産を投資に回してしまう人がいることです。
生活防衛資金をしっかり確保しておかないと、相場が下がった時に生活そのものが崩れてしまう可能性もあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、投資は資産形成の手段の1つですが、生活の基盤を脅かすようでは本末転倒ですよね。
西尾准教授:はい。さらに言えば、素人が一斉に相場に参加すると、相場全体が荒れるリスクもあります。
例えばアメリカでは、ロビンフッドを通じて多くの個人投資家が一斉に株を買い、価格が急騰し、ヘッジファンドが損失を被るという出来事がありました。
個人の群衆行動は、市場そのものが本来持っている価格発見機能に歪みを生じさせてしまいかねません。そういう意味でも、投資に対する理解を深めておくことは大切だと思います。
「資産形成」は”人生の設計図”―手段ではなく目的から考える
カードローンの窓口合同会社 編集部:ここまでのお話を伺っていて、特に若い世代では「とりあえずオルカン」のように、投資そのものというより「買うこと」が目的化してしまっている人が多いように感じました。
西尾様が講義されている中でも、そういった学生は実際にいらっしゃいますか?
西尾准教授:はい、実際にそういった学生はいます。最近の学生たちは特に短期的な「コスパ」や「タイパ」を重視する傾向が強く、それは投資に限らず、さまざまな選択に影響が出ています。
例えば、年金の話になると「納める意味はあるんですか?」「破綻するんじゃないですか?」「もらえないかもしれないですよね」といった声が上がることがあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そういった反応は、SNSやネットの影響も少なからずありそうですね。
西尾准教授:そうだと思います。たしかに、払った以上にもらえなくなる可能性はあり、それを否定するつもりもありません。
ただ、それに対して私は、「払った以上にはもらえないかもしれないという可能性はあるけれど、それでも年金という制度が何のためにあるのかを理解して考えることが大切なんだ」と伝えるようにしています。
「損か得か」だけで判断してしまうと、自分の老後のリスクをすべて自分1人で背負うという選択をしてしまいかねません。
それが本当に良い選択なのか、自分自身に問いかけてほしいのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。制度の役割や自分自身の備えについても考える必要があるのですね。
西尾准教授:そうです。「何のためにお金を増やすのか」「何のためにポートフォリオを組むのか」という問いを抜きにして、ただ「増えそうだからオルカン」と選ぶのは、本質的ではありません。
例えば、株式はインフレに備えるための手段かもしれませんが、それだけではリスクには対応しきれません。だからこそ、さまざまな資産に分散投資する必要があります。
こうした基本的な考え方を、自分自身の生活設計と紐づけて理解してもらいたいと思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。年金や投資に対して「損か得か」という視点だけで考えてしまう風潮が広がっている今だからこそ、「何のために」という問いかけは重要になりそうです。
西尾准教授:そうですね。年金も、「いくらまで生きるか分からない」という前提があるからこそ、リスクに備える仕組みとして存在しています。
それにもかかわらず、「元が取れないかもしれない」という利益率だけで制度を捉えてしまうのは危ういのです。
そういう意味では、若い人たちは制度や仕組みの背景にある目的を、多面的・総合的に考える機会が不足しているのではないかと感じています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:投資も年金も、仕組みの理解と目的意識を持って向き合う必要があるという点では共通しているのですね。
西尾准教授:その通りです。ただ、「何のために投資するのか」といった問いを教育現場で意識させるのは、実際にはとても難しいことです。
なぜなら、そもそも「人生で何をしたいのか」という問いに即答できる若者は少ないからです。例えば「20年後、40年後にどうなっていたいか?」と尋ねても、日頃から考えていなければなかなか答えられません。
もちろん、MLBの大谷翔平選手のように幼い頃から明確な目標を持っている人もいます。
しかし、ほとんどの人はそうではありません。多くの学生が、自分の生活や価値観について、深く考える機会を持たずにここまで来ているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、投資のテクニックや年金・税の仕組みは学ぶ機会があっても、それを「自分の人生」と結びつけて考えることは少ないと思います。
西尾准教授:はい。「税金はなぜ必要で、どう使われているか」「年金はなぜ必要か」といった制度面の教育や、「このように投資をすると効率的に儲かる」といったセミナーはありますが、それを通じて「自分はどう生きたいのか」を考える機会はほとんどありません。
「人生の目的」を教育で教えること自体は非常に難しく、やり方を間違えると全体主義にもつながりかねません。
だから私は、まず「どう生きたいか?」と問いかけることにしています。
「この制度や投資手法は、君の人生にどう関係する?」と、自分自身に置き換えて考えさせることで、初めて「投資をするかしないか」という判断にも意味が生まれるのです。
例えば、家族が土地や不動産を多く持っていて、安定した収入の基盤があるような学生もいるでしょう。そういう人には「よりリスクを取って投資をすべき」とは言えません。
むしろ、その資産を維持するための知識や考え方のほうが重要になるかもしれません。
一方で、その人が「もっと不動産を増やしたい」とか「投資で事業を拡大したい」という強い意志をもつなら、それに見合う知識や戦略を身につける必要があるでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:一律に「投資すべき」と教えるのではなく、それぞれの生き方や状況に応じた判断が大事ということですね。
西尾准教授:そうですね。投資は「長期・分散・積立が大原則」と言われますが、すべての人が余剰資金を分散投資すれば良いというわけではありません。
価格が下がるたびに心臓がバクバクしてしまう人は、正直に言って投資は向いていないかもしれません。
向いていないのに無理して投資を続けると、生活にも心にも負担がかかってしまいます。ですから、私はそういう人にはなんなら「投資はやめたほうが良い」「極力少ない配分でいい」と率直に伝えているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:自分に合った投資スタイル、もしくは投資をしないという選択も、立派な判断なのですね。
西尾准教授:全員が投資で儲けようとする必要はありません。
山の中で静かに暮らしたい人もいれば、都市でバリバリ働いて贅沢をしたい人もいる。それぞれの価値観に合った生き方があって良いのです。
ところが今は、「投資していないのは遅れている」といった空気が蔓延しています。それは価値観の強制であり、ある種の圧力でもあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、私も「今すぐ投資を始めないと損だよ」と言われた経験があります。
西尾准教授:そうした価値観の統一は、とても危ういと感じています。投資は「やるべきこと」ではなく、「自分にとって意味があるかどうか」を考えた上で判断すべきことです。
そのためにも、自分自身の人生設計と向き合う時間を、若いうちにしっかり取ってほしいと思いますね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほどもお話に出ていましたが、「何のために」「いくら必要か」を若いうちから考えることが、資産形成では非常に大切だと感じました。
改めてその理由について、もう少し詳しく伺えますか?
西尾准教授:もちろんです。資産形成にはさまざまな手段がありますが、最も分かりやすく注目されやすいのが「投資」です。
とはいえ、投資だけが資金形成の手段ではありません。
預貯金も立派な手段ですし、もっと言えば「人的資本形成」、つまり自分自身のスキルアップや学びへの投資も重要な資産形成です。
例えば、「自分は働いて稼いだほうが性に合っている」「相場を追いかけるのに時間を使うのは非効率だ」と思う人もいます。
そういう人は、むしろ投資よりも自分のキャリアに集中した方が、結果的に大きなリターンを得られることだってあるのです。もちろん、それに邪魔にならない範囲で積み立てをするのが現実的ではありますが。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、「投資だけが資産形成の道」と思い込んでしまうのは視野を狭めてしまいそうです。
西尾准教授:はい。例えば、「将来自分で会社を立ち上げて大金持ちになりたい」「ある分野で独立して活躍したい」という明確な目標がある人は、そこに必要な資金やスキルを逆算して準備すれば良いでしょう。
そのために何年かけて、どれくらい貯めるのか、どのタイミングで投資や起業に踏み切るのか——そういった人生の目標に応じて、資産形成の手段は変えるべきなのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「資産を増やすために投資をする」ではなく、「目的の実現に必要だから投資を選ぶ」という視点が重要なのですね。
西尾准教授:その通りです。目的がないと、いつの間にか投資に時間を割きすぎてしまうことがあります。
さらに、チャートや銘柄選びに時間を奪われ、気づけば生活の中心が投資になっている──そんな状態に陥ってしまう可能性もあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。「とりあえずオルカン」の話にも繋がりますが、周囲に流されるまま投資を始めると、投資の意義や自分との関係を深める前に、思考が止まってしまいそうです。
西尾准教授:本当は、その「とりあえずオルカン」にたどり着くまでに、「自分にとって何がベストなのか」を考える時間が必要になります。
そのプロセスをすっ飛ばしてしまうと、相場が下がった時に不安になったり、反対に相場が上がったことで根拠なくリスクを取りすぎたりすることにもなりかねません。
ここまでお話ししたように、投資に対してどれくらい時間や労力をかけるかという点も、人によって適切なバランスは違ってきます。
重要なのは、「自分にとって資産形成とはどうあるべきか」を見極めた上で、投資とどう向き合うかを決めることなのです。
自分を知ることから始まる資産形成―リスク許容度の範囲と感情コントロール
カードローンの窓口合同会社 編集部:投資初心者の方はリスクコントロールがうまく行かず、狼狽売りしてしまうことがよくあるかと思います。
こういった狼狽売りを防ぐために必要なリスク許容度の測り方や、感情との向き合い方のポイントがあれば教えていただけますか?
西尾准教授:前提として、人間は基本的に狼狽する生き物です。私自身も、分かっていても狼狽売りをしてしまったことはあります。
今でも、含み損が100万円を超えると、体がガクガクし出します。それくらい、自分の限界が明確にある上で投資をしているのです。
だからこそ、学生には「人間は狼狽してしまうものだ」と踏まえた上で、自分なりのルールを考えておくように伝えています。強靭なメンタルを持った人なんて、そうそういませんからね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。しかし、狼狽を前提に投資をするのはなかなか難しい気もします。実際、自分の限界を明確にするためには何をすれば良いのでしょうか?
西尾准教授:体験するしかない部分はありますね。これは学生向けになりますが、私は「自己責任だけれど授業をサボっても良い」と言っています。
どれだけ授業をサボったら自分の社会復帰に支障が出るのか、どこまで行ったら自分は戻れなくなるのか——それを学生のうちに体験するのも1つの手だと思っています。
実際、私自身も学生時代にやったことがあります。
しかし、途中で「このまま進めば本当に戻れなくなるかもしれない」と強い不安を覚えた瞬間がありました。同じように、学生にも人としての一線を越えてしまう手前で、そういう感覚をつかんでほしいのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「やりすぎてしまった結果、戻れなくなりそうになる」という感覚を、自分で把握しておくわけですね。
西尾准教授:はい。それは投資でも同じです。
私は学生に、「授業をサボっても良い」と言う他にも、オルカンのような分散型商品だけでなく、あえて個別株にも挑戦してほしいと言うことがあります。
個別株は変動が大きいですし、突然TOB(株式公開買付)が発表されたり、不祥事が起きて株価が急落したりすることもあります。そういう変動の激しさを、実際に経験しておくことが大切なのです。
例えば、学生が30万円をなんとか捻出して投資し、もしそれが15万円になったら、ものすごい冷や汗をかくでしょう。
ただ、そういう「15万円で人生が終わったような気持ちになる」経験は、若いうちしかできないものです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、大人になると、その金額に対する感覚も変わってしまいますし、失敗の影響も大きくなりますね。
西尾准教授:そうです。だからこそ、学生のうちに「自分はどのくらい損をすると冷静さを失うのか」「逆に、利益がどれだけ出たら浮かれてしまうのか」という“感情の限界”を体験しておいてほしいと思います。
人間は、理性だけでは動けません。感情に振り回される生き物です。だからこそ、その非合理さを前提にして行動するべきなのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:事前にそうした経験があるかどうかで、投資との付き合い方もかなり違ってきそうです。
西尾准教授:はい。こういった時、冷静に淡々とできる人なら、投資家に向いていると思います。積極的に学んで挑戦していけば良いでしょう。
一方で、感情の限界を感じる場面で「やっぱり自分は弱い」と感じたなら、その人なりの投資スタイルを見つければ良いのです。
例えば、「手取りが月20万円なら、そのうち2万円以上は投資には回さない」「投資先はインデックス投信のみ」といった、自分なりのルールを持っておく。そういう「決意」をもって投資と付き合っていくことが大切です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:失敗を前提にした上で、自分に合ったルールやバランスを見つけていくことが大事なのですね。
西尾准教授:その通りです。大人になってから初めて投資を始めると、退職金を一括で投じてしまって大損するというケースも実際にあります。
それを防ぐためにも、若いうちに小さな失敗をしておくのは大切です。そうすれば、「一点集中は危ないんだな」「自分には合わないな」という感覚が自然と身につきます。
投資で生活が苦しくなって、夜も眠れない——そんな状態になるなら、現金比率を高めて投資は1割だけにしておく。それもひとつの正解です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:投資に向いているかどうかは、実際に体験して初めて分かる部分が多いですね。
西尾准教授:そうですね。投資は、試してみて合わないと感じたら無理に続ける必要はありません。
向いてないと思ったら、投資は脇に置いて、自分の生活スタイルに合った資産形成の方法を選ぶ。それが長く穏やかに続けられるコツなのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。ちなみに、投資における価格変動というのは避けられない要素だと思います。その中で狼狽せずに、長期間投資を継続していくためには、どのような心構えが必要なのでしょうか?
西尾准教授:これもやはり、その人のメンタルの強さによる部分が大きいですね。
理屈としては「長期・分散・積立」が正しいと分かっていても、実際に価格が下がった時にパニックになってしまう人は少なくありません。
ですから、そういうタイプの人には「見ない」という選択肢もあると思います。最初にしっかり設計して、あとはもう放っておくのです。
年に1回くらいチェックする程度にして、「ああ、上がってたな」「下がってたな」と淡々と受け止める。それくらいの距離感で付き合う方が、結果的に継続しやすい人も多いでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:無理に情報を追いかけすぎず、自分の感情を乱さない工夫をするということでしょうか?
西尾准教授:そうです。調子が良い時にだけ画面を開いて、「今のままで良いな」と確認する。それくらいがちょうど良い人もいます。
逆に、メンタルが強くて冷静に判断できる人は、状況に応じて資産配分を見直すこともできます。そういう人には、定期的なポートフォリオの組み換えも有効ですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:自分の性格や感情の傾向に合わせて、投資との距離感を調整するという発想が大切なのですね。
西尾准教授:その通りです。ちなみに、私は感情に流されやすい人にはiDeCo(個人型確定拠出年金)をおすすめしています。
iDeCoは一度配分を決めたら、後は引き出せないし、そもそも頻繁にチェックをするものでもありません。そのため、投資を「忘れる」ことにちょうど良いと言えます。
結局、投資は「自分のメンタルで耐えられるやり方」を知って、それを続けていくことが最も効果的なのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。では最後に、この記事を読んでいる方へ、納得して投資を選ぶために必要な視点やマインドセットについて、メッセージをいただけますか?
西尾准教授:「とりあえず投資」というのは、自分の頭で何がどうなるかを考えずに始めてしまうという点で、非常に危うい行動だと思っています。
分かっていないものに対して、人は必要以上に恐怖を感じるものです。お化けもそうですが、正体が分からないからこそ怖いのは、投資も変わりません。
だからこそ、まずは「理解した上で投資する」という経験を一度はしてほしいと思います。そしてその上で、「それでも人は狼狽するんだ」という前提を持っておくことが大切です。
投資で得られる“プラス”は、お金だけではありません。心の安定も重要な要素です。
価格が上がっても下がっても、平穏に暮らせること。それが、結果として一番良い投資だったと言えるのではないでしょうか。
また、よく「リスク許容度」と言いますが、それは金額の話だけではありません。「自分の心が耐えられるかどうか」も含めて考えて、資産配分を決めることは、投資をする上で欠かせません。
感情も含めた「バランスシート」を常に意識して、自分にとって最も自然なかたちで投資と向き合ってもらえたらと思います。「とりあえずオルカン」から「やっぱり自分はオルカン」。同じ投資でもそういうスタンスで臨んで欲しいです。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年5月31日