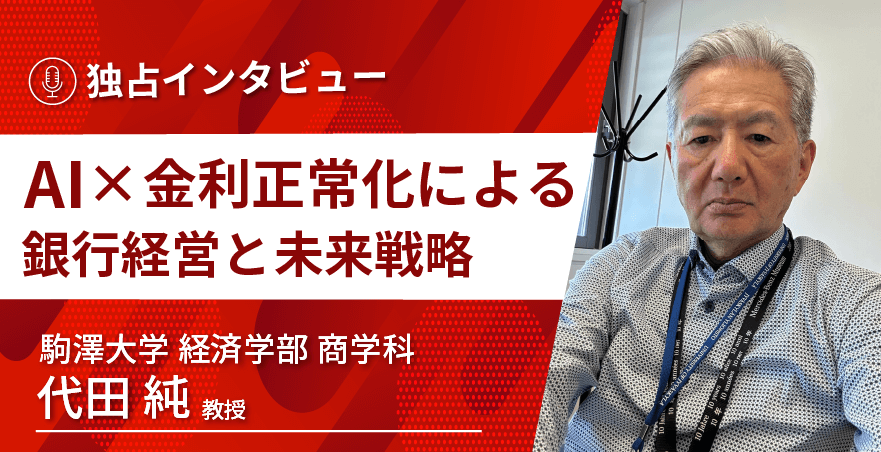日銀によるマイナス金利政策の終了を受け、「金利」の動向が再び注目を集めています。
NISAやiDeCoに代表される資産形成の関心が広がる中、銀行の収益構造や経営戦略にも、これまで以上に大きな転換が求められる時代を迎えています。
そこで今回は、金融論を専門とし、ドイツをはじめとするユーロ圏と日本の比較を通じて、日本における金融・財政政策の課題を研究されている駒澤大学の代田純教授に、お話を伺いました。
金利正常化が銀行経営に与える影響から、AI時代の与信判断、そして今後の人材育成まで。多角的な視点から、金融機関が直面する課題と未来の戦略を深掘りします。
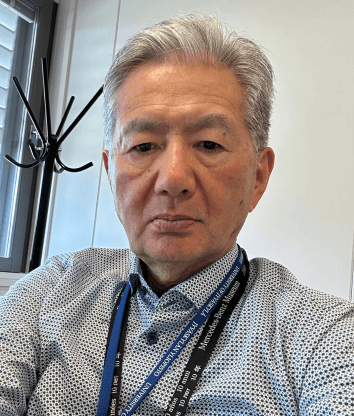
駒澤大学 経済学部 商学科
代田純(シロタ ジュン) 教授
駒澤大学経済学部商学科で金融論を担当。ドイツを中心とするユーロ圏と日本の比較から、日本における金融財政の課題を研究。
著書に「デジタル化する証券市場」(金融財政事情研究会)、「ファイナンス入門」(ミネルヴァ書房)、「入門銀行論」(有斐閣)ほか。証券経済学会 常務理事、公益財団法人 日本証券経済研究所 現代債券市場研究会主査等を歴任。
現在、ユバスキュラ大学客員研究員、在フィンランド。
金利正常化が銀行収益と経営戦略に与えるインパクト
カードローンの窓口合同会社 編集部:それでは、まず最初の質問になります。日銀がマイナス金利政策を終了しましたが、この変化は銀行の資金運用や利ざやの確保にどのような影響を与えているとお感じでしょうか?
また、現在の金利上昇局面は、銀行経営にとっては追い風と見てよいのでしょうか?
代田教授:一言で言うと、大枠では追い風になっていると思います。ただし、部分的に見ると、預金金利の引き上げによって、銀行の資金調達コストも上がっています。
メガバンクは、貸出金利の引き上げ交渉で力があるため、貸し出し資金でも金利を引き上げられており、全体としては非常に追い風になっているという前提でお話しします。
しかし、預金金利の引き上げはコスト負担の増加につながる面もあります。
個別の銀行で見ると、貸し出し金利の引き上げがうまくいかず、預金金利の引き上げをしなければならない場合、利幅、つまり利ザヤが縮小している銀行も少なくありません。
まとめると、全体としては追い風ですが、部分的にはそうではなく、向かい風になっているところもあるということになります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。銀行によって状況は異なるとのご指摘、非常に興味深く感じました。
そうした環境下では、特に地方銀行や中小金融機関においては、収益機会を広げる一方で、リスク管理の重要性もより一層高まっているように感じます。
現時点で顕在化している課題や、今後求められる対応については、どのようにお考えでしょうか?
代田教授:これも最初の質問と関連しますが、2025年3月期の決算を見ると、特に地方銀行と第二地銀で、総資金利ざやがマイナスになっている銀行が全国で4行あります。
また、総資金利ざやが0.1%を切っている銀行が6行ほどあります。総資金利ざやが0.1%を切っているというのは、一般企業で言うと非常に厳しい状況です。
一般企業で利益率が0.1%を切っていたら、経営は成り立ちませんよね。
総資金利ざやが0.1%を切っている銀行が6行、マイナスの銀行が4行ということは、合わせて10行ほどの銀行が、ほぼレッドカード状態と言えるでしょう。
金融庁が色々心配しているのも、頷ける状況です。
もう1つは、国債の利上げによって評価損が出ている問題です。有価証券、特に債券の評価損がかなり大きくなってきています。
地方銀行の場合、長期の国債を多く抱えている銀行が多いため、影響は大きいです。
長期の国債は、持てば持つほど評価損が出やすいという構造になっているため、放置できない問題になってきています。
メガバンクは、ここ数年、短期国債しか保有していません。
しかし、メガバンクにもリスクがないわけではなく、その他有価証券として海外の証券化商品も保有しています。
債券の損失対策として、地方銀行もメガバンクもしっかりとリスク管理をしていく必要があります。
リスク管理ができないものは、できる限り減らしていくべきでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:地方銀行も一般企業同様、厳しい経営環境にあるのですね。
国債利上げの影響がここまで大きいとは、改めて驚きました。
AI時代の銀行業務再設計──効率化と信用判断の革新
カードローンの窓口合同会社 編集部:続いて、AIの導入によって、融資審査や与信判断のプロセスにどのような変化が生じているのか、お伺いしたいと思います。
特に、実務の精度やスピードに対して、どのようなインパクトがあるとお考えでしょうか?
代田教授:スコアリング審査は、すでに10年以上前から行われています。
これは、年収や過去の借入状況などの情報をコンピューターに入力し、その点数(スコア)をもとに融資の可否を判断する方法です。
最近ではAIの技術が進化し、さらに審査がスピーディーかつ正確になっています。
例えば中国のアリペイやWeChat Payでは、キャッシュレス決済を通じて大量のデータが蓄積されており、そのデータをもとにAIが融資の可否を判断しています。
中国では支払いにおいて、アリペイやWeChat Payの利用率が約8割にのぼり、豊富な決済データを活用したAI審査により、審査時間が大幅に短縮され、スムーズな与信判断が可能になっています。
日本の金融学会での報告によると、中国の商業銀行よりも、アリペイやWeChat Payの方がデフォルト率が低いという状況になっています。
AIによる判断は、リテール領域、つまり1人あたり数十万円の融資や、個人企業や個人事業主向けの数千万円程度の融資に活用されることが多いでしょう。
M&Aなどで大企業が買収するような、数百億円、数千億円単位の融資では、AIではなく最終的には人間が判断することになると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:AIの導入で審査がさらに迅速かつ正確になっているのですね。
一方で、AIの活用範囲や役割に応じて適切に使い分けがされているという点も、非常に興味深いです。
続いて、日本の銀行が今後さらにAI活用を進めていくにあたり、どのような課題があるとお考えでしょうか?
技術面だけでなく、組織や人材、そして文化的な側面におけるハードルについても、ご見解をお聞かせいただければと思います。
代田教授:日本の銀行はマネーロンダリング対策が甘いと言われており、国際機関からも指摘を受けています。
私自身も今年4月からフィンランドに移り住み、生活のために銀行口座を開設しようとした際、その違いを強く実感しました。
日本では、運転免許証のコピーと本人確認書類を郵送するだけで口座を開設できることが多いですが、フィンランドでは手続きがとても厳格です。
パスポートや居住者カードなどの書類をPDFで提出し、インターネット上で申請を行い、さらに時間制限もあります。申請後は銀行での面談も必須です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:申請に制限時間が設けられているとは驚きました。
海外ということで書類の準備や手続きが複雑になる中、その時間的な制約は大きな負担になりそうですね。
代田教授:そうですね。外国人であることや、AIによる自動判断が影響しているのかもしれませんが、日本との違いには驚かされました。
また、フィンランドでは一人につき銀行口座は一つしか作れないそうです。
国際機関から日本の銀行がマネーロンダリングに甘いと言われていることが、実際に海外で生活してみて初めて理解できました。
ヨーロッパ全体で本人確認や口座開設の厳しさは増しており、特にフィンランドはウクライナ情勢の影響でマネーロンダリング対策が一層強化されています。
また、偽札の問題もあります。日本では偽札がほとんど流通していないという認識が一般的ですが、ヨーロッパでは紙幣に対する信頼度が非常に低いのが現状です。
日本でマネーロンダリング対策を強化するには、クレジットカードの不正利用対策にAIを積極的に活用することが重要だと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:貴重なお話をありがとうございます。フィンランドでのご経験から、日本と海外の対策の違いがよく分かりました。
本人確認や口座開設の厳しさが国によって違うこと、地政学的な背景も関係している点はとても興味深いですね。
不確実性の時代に銀行が取るべき戦略と人材育成
カードローンの窓口合同会社 編集部:続いてお伺いします。
現在、金融業界は大きな変革期を迎えていますが、そうした中で銀行にはどのような中長期的な経営戦略の視点が求められているとお考えでしょうか?
特に、収益モデルの見直しや地域社会との関わり方について、ご意見をお聞かせいただければと思います。
代田教授:さまざまな考え方があると思いますが、一つの大きな視点は「AIによる単純労働の代替」です。
昨年ノーベル経済学賞を受賞した、MITのサイモン・ジョンソン教授も講演で、「AIによって単純労働は不要になり、その結果、単純労働者の賃金は下がるだろう」と述べています。
銀行でいえば、支店の窓口業務や、バックオフィスでのデータ入力などは、すでに減少傾向にありますが、今後はさらにAIに置き換えられていくでしょう。
実際、日本の銀行では、非正規雇用の職員が全体の約30%を占めており、その多くがこれらの業務に従事しています。
日本の銀行業界は、1980~90年代の成功モデルを2000年以降も続けてきましたが、その結果、一人当たりGDPの成長は鈍化しています。
つまり、雇用構造にも大きな変化が求められる時代になってきているということです。
これからの時代、競争を勝ち抜いていくためには、既存のやり方を見直し、大胆に経営戦略を変えていく必要があると感じています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:貴重なお話をありがとうございます。
AIによる単純労働の代替や、これまでのやり方を見直す必要性について、改めて考えさせられました。
そこでお伺いしたいのですが、AIやデジタル技術の進展を踏まえ、今後の銀行業務を支える人材にはどのような資質や姿勢が求められるとお考えでしょうか?
技術面だけでなく、価値観や倫理の面についても、ぜひお聞かせください。
代田教授:まず、銀行の「トップに立つ人」と「現場で働く人」では、求められる資質が少し異なると思います。
経営者に求められるのは、長期的な視野を持つことです。
AIへの投資は、すぐに業績に表れにくいという課題があります。
たとえば、海外の銀行やGAFAMのように、AIに積極的に投資しても、日本の銀行の場合、短期的にはなかなか成果が見えづらい。
そのため、株主から「ROEが下がっている」「配当が増えない」といった声が上がることもあるでしょう。
それでも、経営者は将来を見据え、AI関連投資の重要性を株主にしっかりと説明しながら進めていく必要があります。
目先の利益だけでなく、長期的な企業価値の向上を重視する姿勢が問われます。
一方で、現場の銀行員に求められるのは「倫理的な判断力」です。
生成AIは、文章作成や画像生成など、非常に高い能力を持っていますが、その分リスクも伴います。
たとえば、AIを使って作成したレポートが、著作権を侵害していたり、個人情報やフェイク情報を含んでいたりする可能性もあります。
これは大学の学生がレポートをAIで書く場合と同じで、便利な一方で、情報の正確性や倫理性をどう担保するかが重要になります。
生成AIを使ってレポートを作成する場合、著作権や個人のプライバシーに触れるような文章が作成されていないか、倫理的に慎重にチェックする必要があります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:AI投資における長期的視点の重要性や、現場で求められる倫理意識について、改めて考えさせられました。
最後に補足としてお伺いしたいのですが、海外の金融機関と比べたときに、日本の銀行におけるAI活用にはどのような特徴や違いがあるとお感じでしょうか?
また、今後参考にすべき点があれば、併せて教えていただけますと幸いです。
代田教授:先ほども少し触れましたが、日本と海外では「現金」に対する信頼度が大きく異なります。
日本では現金に対する信用が非常に高いため、キャッシュレス化やマネーロンダリング対策がどうしても後手に回ってきた印象があります。
また、現在の課題とも関係する点として、日本では「経済安全保障」という視点がまだ十分に根付いていないように感じます。
経済産業省もキャッシュレス決済を推進していますが、それによってVisaやMastercardといったアメリカ系のブランドの存在感が大きくなっています。
一方のヨーロッパでは、こうした外資系ブランドへの警戒心が強く、「Made in Europe」のカード会社を育成する動きが活発です。
決済情報が海外企業に握られることは、経済の自立性を脅かすリスクがある、という警戒心があるからです。
日本では、そうした「Made in Japan」のカード会社を育てようという姿勢があまり強く感じられません。
さらに言えば、ヨーロッパではVisaやMasterだけでなく、中国系のAlipayなどにも警戒感を強めています。
中国の企業が決済シェアを伸ばすことで、個人や企業の決済データが中国に流出する懸念があるからです。
日本でもAlipayのマークを見かけることが増えていますが、そうしたリスクに対する意識はまだあまり高くないように思います。
今後は、AIやキャッシュレスの活用を進めるにあたっても、経済安全保障の視点をしっかり持つことが非常に重要になってくるでしょう。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年7月31日