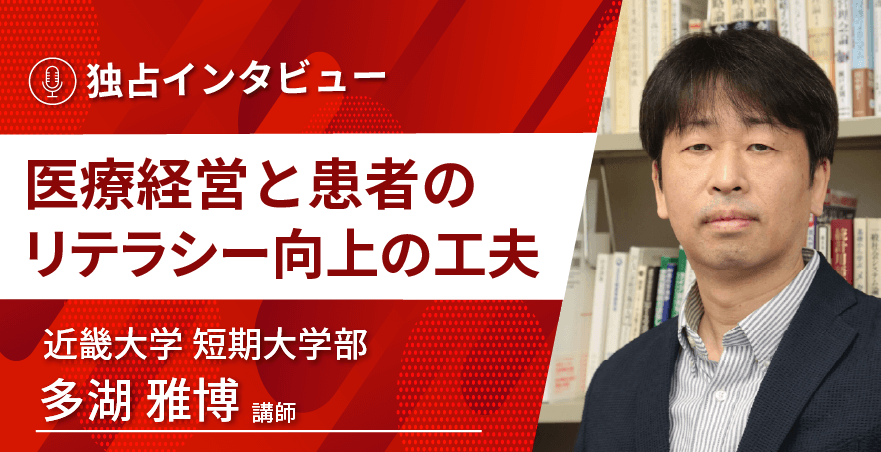医療を受ける上で欠かせない「納得」と「理解」。
近年、患者満足だけでなく、治療内容やリスク、メリットを理解したうえで「自分で納得して選択する」ことの重要性が高まっていて、医療現場における組織運営やチーム医療のあり方にも、大きな影響を与えています。
そこで今回は、看護師としての現場経験と医療経営の知見を併せ持ち、現在は近畿大学短期大学部で医療教育に携わる多湖雅博講師にインタビューしました。
医療現場で求められる「患者の納得」の実態や、組織づくり・デジタル活用を通じたリテラシー向上の工夫について、お話を伺います。
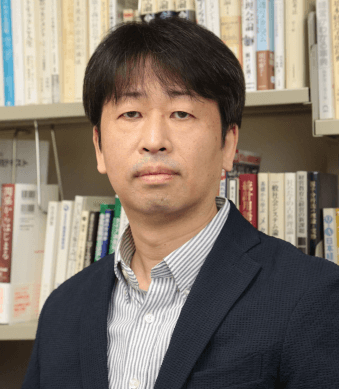
近畿大学 短期大学部
多湖雅博(タゴオ マサヒロ) 講師
看護の専門学校卒業後、看護師として勤務。マネジメントを一通り経験後、大阪府立大学院に進学。
甲南大学大学院にて博士(経営学)を取得。
新潟医療福祉大学、京都文教大学などを経て、2025年から近畿大学短期大学部講師として経営学系の科目を担当。
「患者満足」から「患者の納得」へ—医療現場の変化と背景をどう捉えるか
カードローンの窓口合同会社 編集部:これまで「患者満足」という言葉は、患者さんの感情的な評価を中心に語られることが多かったように思います。
ですが最近では、医療の内容やリスク、メリットを理解した上で「自分で納得して選択する」ことが重視されるようになってきています。
先生は医療現場の組織運営やチームづくりの視点から、この変化をどのように実感されていますか?
多湖講師:はい。おっしゃる通り、これまでの患者満足度調査では「気持ちよく受診できた」「スタッフが親切だった」といった感情的な側面が中心でした。
もちろんそれも大切ですが、近年はそれだけでなく、患者さん自身が「理解し、考え、選択する」場面が増えてきていると感じます。
背景には、医療のサービス業化という流れもありますが、それ以上に根拠に基づいた説明や、患者さんの意思・価値観を尊重した意思決定が重視されるようになってきたことが大きいでしょう。
たとえば、聖路加国際病院などで実践されている「シェアード・ディシジョン・メイキング(SDM)」の取り組みがあります。
これは、医療者が選択肢を提示するだけでなく、患者さんと共に考え、納得できるまで話し合うというプロセスです。
「説明を受けて同意する」だけでなく、「説明を受け、納得して選択する」というかたちに、医療の現場は確実に変わりつつあります。
そしてこの「納得してもらう」という視点は、医療に限らず、組織マネジメント全体にも通じる大切な考え方だと思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。患者さんが自ら考えて選ぶ時代になっているのですね。
感情だけでなく、理解と納得が評価の基準になるのは興味深いです。
社会や技術の発展も、この変化に影響しているのでしょうか。
多湖講師:社会的・技術的な変化は非常に大きいですね。
まず情報社会の進展により、インターネットやSNSを通じて、誰でも簡単に自分の病気や治療法、病院の情報を得られるようになりました。
これは良い面もありますが、感情的な投稿や誤った情報に影響されてしまうリスクもあります。
以前は「医師の言うことがすべて」だった時代もありましたが、今は自分で調べて納得したいという患者さんが増えています。
その意味で、患者さんの“納得の質”が変化していると感じます。
また、社会的な側面では権利意識の高まりも見逃せません。これはここ数年の話ではなく、10年、20年という長いスパンで進んできた変化です。
医療訴訟の増加や情報公開の進展によって、かつて“ブラックボックス”だった医療現場の内側が見えるようになってきています。
一方で、医療技術も日々進歩し、治療法や薬が高度化する中で、使う側の判断や説明の難しさも増しています。
ICTやデジタル化、DX化の進展も非常に大きな影響を与えていますね。
たとえば、患者さん自身が画像を通して自分の病状を確認できるようになったことで、理解や納得が深まる面もあります。
その一方で、不安を助長してしまうケースもあります。
大病院の中には、治療内容や病状をデジタルフォーマットで患者さんと共有する仕組みを導入しているところもありますが、地域のクリニックや中核病院ではまだ難しい面もあります。
いずれにしても、こうした情報や技術の進展が、患者さんの「納得」に良くも悪くも影響していることは間違いありませんね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:情報の量が増えることで患者さんの理解の質も変化しているのですね。読者にも身近な変化として実感できます。
医療経営と患者の医療リテラシー向上の関係性
カードローンの窓口合同会社 編集部:患者さんが理解し納得できるために、組織体制やコミュニケーション、デジタル技術の活用はどのように進めるべきでしょうか。
多湖講師:難しいテーマですね。本日お話しすることも理想論に近い部分があるかもしれませんが、そのうえでお話しします。
まず、組織体制を整えることはできますが、実際に運用するのは「人」です。その人に合った形で機能しているかどうかが重要になります。
組織づくりという点では、やはりチーム医療、つまり多職種連携は欠かせません。
医師だけでなく、看護師や他のスタッフがチームとして関わることが大切です。
患者さんの中には、特に高齢の方ほど医師には言いづらいことを抱えている方も多く、診察後に看護師へ質問するケースもよく見られます。
そうした背景を踏まえて、医師だけで完結させず、看護師や他の専門職がそれぞれの立場から関わるチーム体制が必要です。
また、個人の力量や善意に頼るのではなく、意思決定を支援する仕組みを組織として設けることも重要です。
たとえば「患者相談センター」のように、患者さんの意思決定をサポートする専門部署やスタッフがあると良いでしょう。その際、現場との連携は欠かせません。
評価の仕組みも大切です。どの業界にも言えることですが、行った支援の内容と評価がきちんと結びついていなければ、組織としての持続性が生まれません。
患者支援によって満足度が上がれば、関わった職員やチームの評価に反映されるような仕組みをつくってほしいと思います。
コミュニケーションに関しては、「シェアード・ディシジョン・メイキング(SDM)」のように、患者と医療者が一緒に考え、意思決定を共有していく姿勢が大切です。
聖路加国際病院や名古屋大学などでも、そうした取り組みが進んでいます。
組織開発の観点から言えば、「ナラティブ(語り)」の共有も重要です。患者さんの語りを聞くこと、スタッフ同士が語り合う場を設けることが、チームの理解を深めます。
日々の業務に追われる中でも、強制的にでも話し合う時間や空間を設けることが大切だと思います。
先日、看護師のDX化に関する発表を学会で行いましたが、組織としてテーマを設定し、対話の場を意図的につくることで、意識の変化が広がっていくと感じています。
説明のあり方についても、教育者として「説明しました」「言いました」で終わらせるのではなく、相手が理解し、納得しているかどうかが本質だと思います。
それを常に意識し、互いに確認し合うことが必要です。
デジタル技術については、電子カルテや患者ポータル、動画などを積極的に活用すると良いでしょう。
特に動画は、医療者の教育だけでなく、患者さんへの説明にも有効です。YouTubeなども活用できると思います。
ただし、デジタルツールを「やらされ感」で使っていては効果が出ません。
使う側にも教育が必要ですし、「それを使うことで患者のためになり、自分たちのためにもなる」という意識づけが求められます。
また、セカンドオピニオンやオンライン診療も今後ますます重要になりますが、高齢の方がすぐに使いこなせるわけではありません。
医療機関だけでなく、地域との連携の中で、公民館や役所などに支援の場を設けるなど、環境づくりが必要です。大規模病院ではすでに実践しているところもあるようです。
組織体制、コミュニケーション、デジタルツール。どれか一つ欠けても機能しません。
これらを組み合わせ、根気強く取り組んでいくことが、最終的に「患者の納得」につながるのだと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:院内だけで完結せず、チーム全体で支えることが「納得」を支える鍵なのですね。
地域との連携や高齢者への配慮も重要だと感じます。
多湖講師:医療リテラシーは、個人の努力だけに任せるものではありません。チームや組織、社会全体で支えていく視点が必要です。
行政や教育機関などと連携することで、より効果的に活かされると思います。
まずは地域連携の前に、院内での多職種連携や情報共有をしっかり行うことが前提です。コミュニケーションを取る仕組みを整えることが欠かせません。
地域との関わり方はさまざまですが、関連病院や施設との連携、市民講座の開催などを通じて、地域住民と交流する機会を増やしていくことが大切です。
地域のキーパーソンとの信頼関係を築く場としても有効だと思います。
医療の現場は「病気になってから」の対応が中心でしたが、今は予防へとシフトしています。
生活の中で健康を維持し、健康寿命を延ばすための活動が求められています。
以前、私が勤務していた地域の病院では、大学や高校と連携して医療に関する対話の場を設けていました。学校だけでなく地域住民とも気軽に話せる環境づくりが重要です。
デジタルの活用も欠かせません。
たとえば、トヨタ記念病院では「マイホスピタルポータル」を導入しており、検査結果や治療計画、医師のコメントなどをリアルタイムで確認できます。
利用者の8割が「納得感が高まった」と答えたというデータもあります。
一方で、「知らないでいる権利」についても考える必要があります。
がん告知のあり方が変化してきたように、すべての情報を伝えれば良いわけではありません。
患者さんが自分のペースで向き合えるよう、バランスの取れた支援が求められます。
デジタルツールを使える世代とそうでない世代の格差をどう埋めるかも課題です。医療リテラシーの向上は、病院経営の持続にも関わります。
患者さんの理解や納得の度合いが、病院の評価や信頼につながる時代です。
今後は、医療・行政・教育・テクノロジーが協働する「共創型マネジメント」が重要になるでしょう。
その中で働く人々が互いに説明し合い、理解し合い、納得できる文化を育てること。それが医療リテラシーの土台になると思います。
情報を知り、納得するためには、人とのつながりが欠かせません。患者さんもスタッフも孤立しないような制度や仕組みを整えることが理想です。
そうした思いをもとに、私は今も組織開発の取り組みを続けています。
カードローンの窓口合同会社編集部:情報を知り、納得するためには、人とのつながりや環境づくりも不可欠なのですね。
今後の医療経営に求められる視点と課題
カードローンの窓口合同会社編集部:これからの医療経営では、患者の納得を組織運営や経営戦略にどう反映させるべきでしょうか。
多湖講師:これまでの医療経営では「患者満足」が重視されてきましたが、これからは「患者の納得」がより重要になっていくと感じています。
患者さんが理解し、自ら選択し、「自分ごと」として治療を受け入れていく姿勢を支えることが大切です。
医療は「患者中心」と言われますが、私は“患者さんを真ん中に置く”というよりも、医療従事者と患者が同じ輪の中で共に創る関係性が理想だと思っています。
経営理念や方針の中にその考え方を明文化し、現場のスタッフに理念の意味を丁寧に伝えていくことも大切です。
また、患者の納得を支えるチームをつくることも重要です。
医師一人に任せるのではなく、多職種のスタッフがそれぞれの立場でリーダーシップを発揮し、患者さんや家族も同じ輪の中に入ってもらう。
理想論ではありますが、少しでもハードルを下げるために、患者が納得した結果どういう良い変化があったのかを事例として学ぶ場を設けると良いと思います。
患者さんの価値観も多様化しています。外国人患者の増加もその一つです。
私自身、通訳がいない中で手術説明をする必要があり、偶然その言語を話せる人に同席してもらった経験があります。
こうした課題を踏まえ、多言語対応をDXの力で現場レベルにまで浸透させることが求められます。
また、地域の自治体と連携して健康講座などを開き、病院と地域が歩み寄る関係を築くことも大切です。
そこにデジタルツールをうまく取り入れることで、より多くの人がアクセスできる環境が整うでしょう。
カードローンの窓口合同会社編集部:“患者さんを真ん中に置く”のではなく、“共に輪を作る”という考え方が印象的です。
医療者と患者が対等な関係で向き合うことが信頼の基盤になるのですね。
最後に、医療現場のリーダーが「患者の納得」に取り組む際、特に意識すべきことは何でしょうか。
多湖講師:医療現場でのリーダーシップはこれまで、安全性や効率性、成果を重視してきました。
もちろんそれも大切ですが、今後は「患者の納得をどうデザインするか」という視点を加えることが欠かせません。
リーダーは、ただ情報を伝えるだけでなく、関係性の中で自然に理解を深められる「知る環境」をつくることが求められます。
そして、これを特別なことではなく「当たり前の文化」として根付かせる。そのためにも、日常の中でのコミュニケーションや対話を大切にしてほしいと思います。
スタッフの意見を引き出し、それを活かしていくこともリーダーの大事な役割です。
新人であってもベテランであっても関係なく、誰もが意見を出せる雰囲気をつくる。
その支えとしてデジタルツールを活用し、理念に基づいた成功・失敗事例を共有することが重要です。
こうした取り組みが、結果的に心理的安全性の高い職場文化につながっていきます。
また、リーダー教育の中で「聴く力」「語る力」を育むことも欠かせません。
現場は忙しく、じっくり話す時間が減り、コミュニケーション能力がすり減っている印象があります。だからこそ、“聴く・語る”ことの価値を改めて取り戻してほしい。
さらに、患者の納得度を可視化する仕組みも必要です。
たとえば、オンライン上で「納得した」「まだ不安がある」といった意思を簡単に入力できるシステムを導入すれば、医療者も患者の理解状況を把握しやすくなると思います。
リーダーは一人で背負う必要はありません。
患者やスタッフと一緒に歩む「共有型リーダーシップ」、つまりシェアード・リーダーシップを医療現場にも根付かせていくことが理想です。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年10月10日