近年、キャリア教育は単なる就職支援ではなく、人生そのものに関わる学びとして捉えられるようになってきました。
しかし、めまぐるしく変化する現代において、キャリア教育はどのようにあるべきなのか、その答えはいまだ手探りの状態です。
そこで今回、法政大学の田澤実教授に、未来を切り開く力を育てるために必要なキャリア教育と家庭のサポート術について独自取材を通じてお話を伺いました。
教育のあり方も含めて、私たちにできることは何か、そのヒントを田澤教授のお話から紐解いていきましょう。
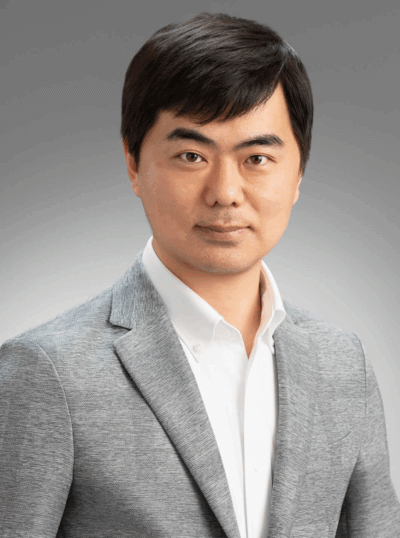
法政大学 キャリアデザイン学部
田澤実(タザワ ミノル) 教授
中央大学文学部教育学科心理学コースを卒業後、
同大学大学院文学研究科にて博士(心理学)を取得。
2007年より法政大学キャリアデザイン学部にて助教。
その後に専任講師、准教授を経て2020年より現職。
〈研究分野〉
生涯発達心理学・教育心理学
〈著書・論文〉
「コロナ禍が大学進学時の都道府県間移動に与えた影響」(2024年)
「大卒者への就職支援と初期キャリア」(2024年)
「社会正義のキャリア支援論から見た若年無業者:地域若者サポートステーション事業に焦点を当てて」(2022年)
これからの時代に求められるキャリア教育の特徴と課題
カードローンの窓口合同会社 編集部:AIなどの技術革新が加速する今、将来の見通しが立ちにくい中で、若者自身が主体的にキャリアを考え、築いていくことがますます大切になっています。
そこで、まずは「キャリア教育」とはどのような特徴があるのか、大切なポイントと併せて教えていただけますか?
田澤教授:キャリア教育は就職準備といった限定的な意味ではなく、もっと広く「人生全体」に関わる教育だというのが1つの大きな特徴です。
かつては、「キャリア」という言葉を聞くと、「キャリア官僚」のようなイメージで捉える方も多かったと思います。
しかし、キャリア教育では、「職業キャリア」だけではなく「ライフキャリア」、つまり人生そのものをどのようにデザインするかという視点が基本的な方針になります。
文部科学省の方針や学習指導要領などでも、そういった考え方は近年明確になりつつありますよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。たしかに、私自身もキャリア教育と言えば「人生そのものについて考える」という広い意味で捉えていました。
田澤教授:そうですよね。そんなキャリア教育では「自分で考えて選ぶ力」、さらに「変化に応じて修正する力」を育むことが重要です。
つまり、一度選んだ進路がすべてではなく、変化に対応しながら進んでいける力を身につけることこそが、キャリア教育の特徴と言っても良いでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:進路を選ぶだけで終わらない、ということですね。
田澤教授:そうです。そして、これらの力に加えて非常に重要なのが「社会に対する眼差し」です。
あえて「力」とは呼ばず、「眼差し」と表現したいのですが、これがキャリア教育におけるもう1つのキーワードとも言えます。
この「社会に対する眼差し」は、社会をどう見るか、自分と社会がどのように関わっていると感じているか、ということを指します。
この眼差しが育たなければ、主体的な選択や修正という行動はできなくなってしまうのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、自分と社会が切り離されているように感じていたら、キャリアを「自分事」として捉えることはできませんよね。
田澤教授:その通りです。キャリア教育というのは、「自己理解」と「他者理解」から始まります。ここでいう他者とは人間だけでなく、職業なども含め、個人と環境と言い換えることもできます。この2つは、社会と切っても切り離せない関係性があるのです。
単なる職業選択ではなく、自分の人生と社会との繋がりをどう築いていくのか。
その意識があるかどうかで、キャリア教育のあり方も、私たちの生き方そのものも、大きく変わっていくのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。今回は大学生を主な対象としてお話を伺っていますが、大学生になる前の家庭での過ごし方や経験の積み重ねも、「社会に対する眼差し」に深く関係していそうですね。
田澤教授:そうですね。どこからが「社会」なのかという定義は様々ありますが、実は家庭の中でもすでに社会との関わりは始まっているのです。
例えば、日常の中でどんな会話が交わされているかによっても、子どもが社会をどう見ているかに大きな影響を与えることがあります。
そういったテーマも含めて、家庭や学校、地域といった日常の関わりが、若者の「社会に対する眼差し」を育てる上で重要な土台になっていると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:では、今お話しいただいたようなキャリア教育の理念がある中で、実際の大学現場ではどのような課題があるのでしょうか?
田澤教授:先ほど「キャリア教育は就職教育とは異なる」と説明しましたが、大学の運営上、当初に掲げた理想をそのまま貫くのが難しいケースも少なくありません。
例えば、進路実績が大学の評価や存続に直結している場合、どうしても就職率の向上が優先されることもあります。
そうなると、本来のキャリア教育ではなく、「就職支援」がキャリア教育の中心として扱われてしまうことがあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:仕方のないこととはいえ、現場では理念とのギャップが生じているのですね。
田澤教授:はい。ただ、文部科学省の方針としては「各大学の学びの特色に応じて、キャリア教育のあり方は柔軟で良い」とされています。
例えば、文学部の学びは直接職業に結びつくとは限りませんよね。それでも、その学びが将来の生き方や考え方に影響を与えることはあります。
その学びに連動する形でキャリア教育を行うべきだというのが、今の基本的な考え方です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。そうした方針がある中で、大学側も試行錯誤している段階にあるのですね。
田澤教授:そうですね。大学によっては、履歴書の添削や企業説明会、テスト対策といった実務的な内容がキャリア教育の中心になっている講義もあります。
もちろん、こうした内容にも意味はありますし、学生にとって役立つものです。ただ、それだけではなく、生き方や働き方そのものを考える機会も必要だと感じています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、履歴書の添削や企業説明を受けるのは、決して無駄ではありません。とはいえ、キャリア全体を見通せるかと言われると難しいところだと思います。
田澤教授:おっしゃる通りです。例えば、「一度就職したけれど辞めた」「転職した」「家庭との両立に悩んだ」──そんな人生の選択にどう向き合うかまで含めて考えるのが、本来のキャリア教育と言えます。
私自身、大学教員として「まずは就職が大事」という考え方にも共感していますし、現実的に学生や保護者に納得してもらえる成果も求められています。
だからこそ、今あるキャリア教育を単純に「良い」「悪い」で判断するのではなく、何を目的として行うのか。その目的に応じてプログラムをどう設計するかが、今後ますます重要になると考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。先ほど、「分野によってキャリア教育のあり方は変わって良い」という文部科学省の方針があると伺いましたが、理系の場合はどのような特徴があるのでしょうか?
田澤教授:理系の場合、特徴的なのは「大学院への進学」がキャリア選択の一部として自然に位置づけられている点ですね。
学びをさらに深め、専門性を高めたいと考える学生にとっては、大学院へ進むことがごく当然の選択肢となっている分野もあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、理系だと大学院が前提のような雰囲気はありますね。
田澤教授:はい。特に理系では、将来の職業や研究との繋がりを意識して、比較的早い段階から研究室選びなどを視野に入れて行動する学生が多く見られます。
このような姿勢には、キャリア教育的な要素が自然に含まれているとも考えられるかもしれません。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そう言われてみると、研究室選びは就職活動やキャリア選択と似たところが多いような気がします。
田澤教授:まさにその通りです。
研究室を選ぶ際には、限られた時間の中で情報を集め、いくつかの選択肢を比較検討し、自分の価値観と照らし合わせながら優先順位を決めていきます。
さらに、希望する研究室とのマッチングも必要です。こうした一連の流れは、就職活動と非常によく似た構造を持っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。過程そのものが、キャリア教育としての学びに結びついているということですね。
田澤教授:はい。例えば「なんとなく」で研究室を決めた場合、その後の就職活動で「この経験を活かしたい」と考えても、実現には大学院進学が必要だと気付くこともあります。
しかし、家庭の事情などで大学院に進学できないとなると、関心を持てない別の進路を選ばざるを得なくなるケースもあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、研究室選びの段階から「この選択が将来にどんな影響を及ぼすのか」「どんな意味を持つのか」を考えるのが大切ということでしょうか?
田澤教授:おっしゃる通りです。その選択を「なぜ自分はそう決めたのか」と言語化できているか。そして、自分がどこに社会との繋がりを見出しているか。この2点は非常に重要です。
この2つの視点を持っていれば、仮に進んだ道が直接的に職業に結びつかない場合でも、自分で選んだという納得感があります。その結果、将来の選択肢も広がっていくでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:その2点に関しては、就職活動が始まってから突然考えようとしても中々難しそうですね。
田澤教授:そうですね。そういう意味でも、研究室選びの段階で「自分がなぜその選択をしたのか」という意識を持つことは、キャリア教育の本質に近い経験になると思っています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。今回は理系の話でしたが、日常の意思決定すべてにおいても、「自分がなぜその選択をしたのか」を考えるのは重要そうです。
田澤教授:まさにその通りです。大学受験での学部選びもそうですし、履修登録で時間割をどう組むかですら、自分の価値観や優先順位と向き合う機会になります。
もちろん、すべてを深く考える必要はありません。とはいえ、日々の中には多くの「学びのきっかけ」があると私は思っていますよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかにそうですね。キャリア教育では「自分で考えて選び、変化に応じて修正する力」が大切だと伺いましたが、それは講義の中で身につけるというよりも、日常の中で育まれる要素が強いように感じました。
田澤教授:そうですね。少し話が逸れるかもしれませんが、この「意思決定」はキャリア教育の中でも特に議論の多いテーマの1つです。
例えば、「就職や人生の選択は、”今日のお昼に何を食べるか”という選択と、同じ枠組みで語って良いのか?」という点では、研究者の間でも意見が分かれることがあります。
一見すると、どちらも複数の選択肢から比較・決定しているという点では、構造は似ていると思いますよね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:そうですね。選択した結果の重要度は違うかもしれませんが、プロセス自体は同じように感じます。
田澤教授:まさにそこがポイントです。昼食であれば、たとえ選択に失敗しても翌日に「これは好みではなかったな」というように、ある種のリセットが可能です。
一方、就職や進路といった大きな選択は、1つの判断がその後の人生に長く影響します。
さらに、「絶対に内定がもらえると思っていた企業に、予期せぬ理由で落ちてしまった」など、不確定要素が含まれるケースもあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。選択の結果による重みがまったく違いますね。この話を聞くと、先ほどの議論に明確な正解はないように思えてきました。
田澤教授:その通りです。ですから、「昼食と就職の意思決定の重みを一緒にしてはいけない」という考えの研究者も当然います。
一方で、意思決定の構造を学生に伝える際には、そのような例が分かりやすく感じられる場面もあります。
誤解が生じる可能性は理解していますが、それでも「こういう枠組みがありますよ」と今回のお話でもお伝えしておきたいです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、今の例は比喩として非常に分かりやすかったです。意思決定というテーマが難しいとおっしゃった意味の一端が見えた気もします。
田澤教授:ありがとうございます。また、もう1つお伝えしたいのが、「意思決定の重み」という視点でも、感じ方は人によって大きく変わるということです。
例えば、以前私のゼミで、学生に「ゼミ選びは人生に関わる重要な決断だから、本気で選ぶよね?」と聞いたところ、「いや、そこまで真剣には考えていませんでした」と答えた学生がいました。
その学生の考えの良し悪しは置いておくとしても、このように「選択とその結果の重さ」は人によって違います。今回のケースのように、こちらの想定とはまったく異なることもありますから、その点を踏まえても「意思決定」は難しいテーマですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、そういうケースもありますよね。実際、私の友人にも「どのゼミもピンと来ないから適当に決めた」という子がいました。
田澤教授:そういう学生も少なくありませんね。ただ、「どのゼミでも私はそれなりに学べる」と思って選んでいるのであれば、それも1つの立派な意思決定だと思います。
一方で、特に理由もなく選んだり、将来との繋がりをまったく意識せずに決めたりしてしまうと、後から「あれ?これは自分に合っていないかも」となるリスクがある点には注意が必要です。
大学の中には、ゼミが必修でないところもありますし、その場合は選ばない自由もあります。ただ、もし複数の選択肢があるとするなら、ある程度自分なりに考えて決める姿勢を学生には持っていてほしいですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:先ほどのお話もそうでしたが、「自分の選択に意味を持たせられるかどうか」が大事なポイントなのですね。
田澤教授:その通りです。選択そのものに正解・不正解があるというよりは、「自分はなぜその選択をしたのか」と振り返り、意味付けることが後のキャリア形成にも繋がると思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ここまでのお話を伺って、現在のキャリア教育にはいくつかの課題があることが見えてきました。そうした課題を解決するには、どのような視点や取り組みが求められるとお考えでしょうか?
田澤教授:まず前提として、今のキャリア教育が抱える課題の背景には、「大学の生き残り」という非常に現実的で切実な問題があることを知っておいていただきたいです。
そのため、私としては各大学のキャリア教育の取り組みを否定するつもりはまったくありません。
その上で申し上げるなら、これからは「社会に対する眼差し」を育てるキャリア教育に、より重点を置いていくべきではないかと考えているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:最初の方でも、「社会に対する眼差し」と言うキーワードが何回か出てきましたね。
田澤教授:はい。現在は「キャリア教育=就職支援」といった捉え方は徐々に薄れてきています。
かつては「キャリア教育なんてきれいごとではないか」といった批判もありましたが、今は「人生そのものをデザインする学び」としての認識が、少しずつ社会に浸透してきているのです。
最初の方でもお話したように、私は一貫してキャリア教育の核は「自己理解」と「他者理解」、そして「社会に対する眼差し」にあると考えてきました。この考えは、研究を始めた当初から今まで変わっていません。
このようにキャリア教育の研究を続ける中、今注目しているのが「インターンシップ制度の見直し」です。
これまでは1日だけの「1dayインターンシップ」なども「インターン」として扱われてきました。しかし、最近では原則として5日間以上のプログラムを「正式なインターン」と位置付ける動きが進んでいます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかにそうですね。最近はプレゼンや課題提出があるような、より本格的な形式のインターンが主流になってきた印象があります。
田澤教授:はい。学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取り組みには様々ありますが、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、これら三省合意の改正により、学生の参加期間が5日間以上のものをインターンシップと呼ぶようになってきています。取得した学生情報を採用活動に活用できるタイプですので、学生側も企業側も注目をしています。
その結果として、学生が「インターンに行かなければ就職できないのではないか」と感じ、学業よりもインターンを優先しようとする動きが強まっているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。現在の就職活動にはそのような傾向があるのですね。
では、先ほど田澤様がお話されていた「社会に対する眼差し」と現在の就職活動には、どのような関係があるのでしょうか?
田澤教授:最初の方で、「社会に対する眼差し」がなければ主体的な選択や修正という行動は難しくなるというお話をしたかと思います。
しかし、「インターンに行かなければいけない」という、ある種の強迫観念のようなものが広がっている中で、学生が本当に社会に対する眼差しを育てられているかというと、必ずしもそうではないかもしれません。
就職活動において本当に大切なのは、企業を複数の視点から捉え、自分なりに納得して意思決定できるかどうかです。
そこでここからは、2つの観点からお話しできればと思います。
1つ目は、インターンを通じて見えてくる現在の就職活動の実態について。2つ目は、民間企業に限らない、より広い意味での「社会に対する眼差し」についてです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:分かりました。では、前者の「インターンを通じた現在の就職活動のあり方について」から詳しく伺えますか?
田澤教授:はい。前提として、民間企業というのは1つの「社会」と言えます。
ですから、本来の理想的な就職活動のあり方としては、いくつかの社会(=企業)を実際に体験し、その中から自分に合った場所を選ぶという流れが望ましいのです。
ところが現在は、「5日間のインターンに参加しなければ内定がもらえない」と信じている学生も多く、そのような”ルール”を真面目に守ろうとする傾向があります。
ただ、よく考えてみてください。たとえ夏季休暇中であっても、参加できるインターンの数には限りがあります。多くても2社、3社ほどではないでしょうか。
さらに、意識の高い学生ほど、夏に長期インターンに参加し、秋以降は短期インターンを複数こなすといった動きを取ります。
その結果、いざ本選考が始まった時に、「本当はどの企業に行きたいのか」「どこに集中すべきなのか」が分からなくなり、かえって混乱してしまうのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、「インターンに行かなければいけない」という思い込みがあると、時間的にも精神的にも追い詰められてしまいそうです。
田澤教授:おっしゃる通りです。ただ、冷静になって考えてみると、企業はインターンに参加していない学生も採用していますよね。
つまり、「インターンに行かないと就職できない」という空気とは裏腹に、実際の採用現場ではその限りではないというギャップ、いわば制度上の混乱があるのです。
とはいえ、そうした構造上の矛盾に気付くのは、特に就職活動の真っ只中にいる学生にとっては難しいことだと思います。
そこで私が提案したいのは、「企業全体の採用スケジュールの中で、インターン経由の採用枠の位置づけについて情報を開示すること」です。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。採用枠が明らかになれば、学生もインターンの優先順位を付けやすくなりそうです。
田澤教授:そうなんです。もちろん、企業によっては明確な採用枠を設けていない場合もあるかもしれません。ただ、昨年度の採用スケジュールについての情報開示や、今年度のある程度の目安や方針だけでも公開されていれば、学生にとっては大きな判断材料になります。
今の就職活動は、企業の選択肢が多いように見えて、実は情報が不透明で選びにくい構造になっているのです。
このような状況は、学生にとっても、インターンを運営する企業側にとっても負担が大きくなってしまうのではないでしょうか。
ですから、学生が過度な不安を感じず、インターンを本来の学びとして活かせるような、よりフェアで分かりやすい構造が整っていくことを期待したいです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、インターンの構造自体が疲弊を生んでいる可能性は無視できませんね。とはいえ、制度や構造を変えるには長い時間がかかります。
これから就職活動に臨む学生たちは、一体どのような行動を意識すれば良いのでしょうか?
田澤教授:これはあくまで私個人の考えになりますが、5日間以上のインターンではなく、2~3日程度の短期プログラムに参加することを検討してほしいです。
先ほど、三省合意の改正について述べましたが、この類型によればこのような短期の取り組みが「キャリア教育」と呼ばれています。ただ、制度上では、取得した学生情報を採用活動に活用できません。インターンシップとは異なるモチベーションが学生側にも企業側にも必要になるでしょう。
特徴的なのは、企業が採用活動の一環としてではなく、地域貢献や教育的視点からプログラムを実施している点が挙げられます。
例えば、「地元を知る」「地域活性化に取り組む」といったテーマで、学生が地域社会と関わる機会を提供しているケースもあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:私自身もそういった短期プログラムを見かけたことがあります。参加条件や志望動機の提出は不要など、長期のものより柔軟な印象がありますね。
田澤教授:そうですね。都心部の有名企業のように高倍率な選考を勝ち抜く必要もなく、気軽に参加しやすい点も、短期プログラムの魅力の1つです。
実際、そういったプログラムに参加したことがきっかけで、「地元で働くという選択肢もあるかもしれない」と感じる学生もいます。
もしそういった気づきが得られたなら、「都心の有名企業で働くしかない」というプレッシャーから少し離れられるかもしれません。もちろん、都市で積極的にキャリアを築きたいという意思があるなら、それも立派な選択です。
ただ、「自分には別の可能性・選択肢があるのかも」と思えたら、それはとてもラッキーですよね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:つまり、そうしたプログラムへの参加が、新たな価値観や視点を広げるきっかけになるということですね。
田澤教授:まさにその通りです。そもそもインターンシップの本来の意義は、まさにそうした「視野を広げる体験」にあったはずです。
ところが現在では、参加人数が多すぎて内容が希薄になったり、選考の要素が強くなりすぎて狭き門になったりせざるを得ない傾向にあります。
こうした状況の中で、インターンの採用枠や短期プログラムの情報がしっかりと提示されていれば、学生は「この時期は何を重視するか」「どう動くべきか」といった戦略や見通しを立てやすくなるはずです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。事前に計画を立てて動ければ、就職活動への不安も軽減されそうですね。
田澤教授:そう思います。今の状況では、意欲的に動いている学生ほど「終わりの見えない就職活動」に疲弊してしまいがちです。
その結果、「卒論もあるし、そろそろ決めてしまおう」と妥協して就職先を選んでしまうこともあります。
ただ、そうして決めた直後に新しい情報が入ってきて、「やっぱり迷ってしまう」というケースもあり、さらに消耗してしまう。このような負のループが起きやすい構造になっているのです。
だからこそ、企業側が採用の方法やインターンの位置づけを明示し、学生が「夏のインターンを軸にする」「秋の本選考に集中する」といったように、自分なりの計画を立てられるようになることを期待しています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:学生にも企業にも過度な負担がかからないような制度設計が求められますね。
田澤教授:そうですね。就職活動は「選ぶ力」を問われるものですが、現状はその力の育成を阻む構造的な問題があることに私たちは目を向けていく必要があります。
そして、採用に直結しないキャリア教育の経験が、地元を見る眼差しを育てたり、結果として選択肢を広げたりすることもある。そんな可能性に注目していきたいですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:今すぐに仕組みを変えるのは難しいにしても、社会構造が就職活動に与える影響は想像以上に大きいのですね。
ちなみに、現在の大学生は、こうした社会の構造や社会そのものを、どのように捉えているのでしょうか?
田澤教授:それは、2つ目の「民間企業だけではない社会の広い眼差しについて」にも大きく関わってくる点ですね。
私は「大学生が社会をどう捉えているか」に関しても研究を行っているのですが、興味深いことに、性別によって社会への捉え方に違いが見られるのです。
例えば、男性の場合は「社会=成果を出す場」「稼ぐ場」というイメージを持ちやすいのですが、女性は「自己成長の場」「学びの場」として社会を捉える傾向にあります。
そして、「社会は生きにくい」と感じているのは、圧倒的に女性が多いのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、女性の生きづらさやライフキャリアについては、話題になる機会も多いですね。
田澤教授:そうですね。特に、三大都市圏以外の地域に住む女性の方が、社会に対して「生きづらい」と感じやすいという傾向もあります。
背景には、性別による役割期待が地方ほど根強く残っていることがあるのではないかと考えています。
例えば、「地元を出て自分のやりたいことに挑戦したい」と思っていても、「それは女性がやるべきではない」といった無言の圧力を受けるケースがあるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:性別による役割の期待は、無意識に向けられることも多いですよね。とはいえ、当事者からすれば、それだけでも十分に重荷になると思います。
田澤教授:おっしゃる通りです。さらに、実際に社会に出てからは「やはり男性の方が優遇されているのではないか」と感じ、失望するケースもあるでしょう。
このように、制度上の不平等や実際の経験を通じて、社会に対する見方がより厳しいものになってしまうこともあるのです。
重要なのは、こうした問題は個人の心理だけに原因があるのではなく、社会構造に根差したものであるということです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。「社会に対する眼差し」は、まさにここに繋がるのですね。
田澤教授:その通りです。「社会に対する眼差し」は、個人の能力や性格だけで育まれるものではありません。
その人がどんな経験をしてきたか、どんな環境に身を置いていたかが大きく影響します。
そのため、大学教育や家庭、地域の環境などが、「社会とはこういうものかもしれない」と思える経験を提供できるかどうかが、その眼差しを育てる鍵となるでしょう。
もっとも、それは簡単なことではありません。
実際に、学生の中には社会に対して強い不信感や諦めを抱いているケースもあります。自由記述のアンケートで「あなたにとって社会とは何ですか?」と尋ねたところ、1行目に「地獄です」と書いた学生がいたこともありました。
その言葉にたどり着いた背景には、様々な事情や経験があるのだと思いますが、読んだときはやはり複雑な気持ちになりました。
カードローンの窓口合同会社 編集部:もしかすると、その学生は就職活動などで行き詰まっていたのかもしれませんね。
田澤教授:そうかもしれません。だからこそ、就職活動が本格化する前の、まだ心に余裕のある時期に、社会と触れ合う機会を持つことが大切なのです。
「何とかして就職先を決めなければならない」といった切迫した状況ではなく、もっと自由な気持ちで社会を見られるタイミングで、「社会に対する眼差し」を育てていく経験が必要だと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、何かに追われて焦っている時は、選択する力も削られますし、ポジティブに考える余裕も失われてしまうと思います。
田澤教授:本当にそうなのです。これは少し極端な例かもしれませんが、不動産会社で3件の物件だけを提示され、「今日中に決めてください」と言われたら、納得できる選択ができるでしょうか。
仮にその3件が「悪い」「もっと悪い」「そこそこ」といった内容であっても、他に選択肢を探す余裕がなければ、消去法で「そこそこ」に決めざるを得ないかもしれません。
しかし、時間や気力に余裕があれば、「もっと良い物件があるはず」と考えて別の会社を回ることもできますよね。
「社会に対する眼差し」も、それと同じようなものです。エネルギーのあるうちに、様々な社会の姿に触れ、自分なりの視点を持つことが大切だと思います。
その上で、自分のペースで情報を集めて、納得できる判断をするための準備をしていく。それこそが、キャリア教育の本質なのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。社会に触れることを通じて「選択する力」を身に着け、その上で就職のステップに繋げていくのですね。
田澤教授:はい。焦らずに社会を知る機会を見つけていくこと。
そして、大学もそうしたプログラムを積極的に紹介していき、「社会に対する眼差し」を育てる土壌を整えていくことが重要です。
何度かお話しましたが、現在のキャリア教育がすべて間違っているとは思いません。ただ、今後は「社会との関わり方を学ぶ教育」へと軸足を移していく必要があるのではないかと感じています。
就職活動に限らない、より広い意味でのキャリア教育の重要性を、これからも多くの人に伝えていきたいと考えています。
生涯発達心理学・教育心理学の観点から見たキャリア形成の支援
カードローンの窓口合同会社 編集部:これまでは社会構造などの外的な要因に注目してお話を伺ってきましたが、キャリア形成を考える上では、学生側の心理的な側面、つまり内的な要因も大切ではないかと感じています。
そこで、大学生が余裕のあるうちに身につけておいた方が良い力やスキルがあれば、ぜひ教えてください。
田澤教授:はい。最初に、キャリア教育では「自分で考えて選び、変化に応じて修正する力」が大切だとお話しましたよね。
これは「自分で問いを立てて、調べて、考えて、自分なりの答えを導き出す力」と言い換えることもできます。そして、まさにそれこそが、学生のうちに身につけておいてほしい力です。
社会は、正解が1つに決まっている場面がほとんどありません。そのため、自分なりに現状を捉えて、「もしかしたら、こうなのではないか」と考え、試行錯誤していく必要があります。
そのためには、まず問いを立てて、情報を集め、周囲の意見にも耳を傾けながら、自分なりの答えをつくっていくというプロセスを重ねていくことが大切です。
こうした一連の流れを、一言で表すなら「探究」という言葉がふさわしいでしょう。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「探究」ですか?
田澤教授:例えば、大学の講義で感想を書く課題がありますよね。実はあれも探究の入り口なのです。
ただ出席のために書いている人も多いかもしれませんが、情報を自分なりに意味付けて、言葉にしていく行為そのものが、「社会を自分事として捉える力」を育てているのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、高校や大学では、感想やレポートを書く機会が多くありました。あまり意識していませんでしたが、「自分なりに言葉をまとめる力」は、そうした場で培われてきたのかもしれません。
田澤教授:そうですよね。そして、卒業論文もまた、感想文の延長線上にあるものだと思います。
最初は「これに関心がある」「こういうことを知りたい」といった問いから始まり、それについて調べ、考え、自分なりの結論を導き出していく。まさに、先ほどの「問いを立てて考える力」と同じ構造です。
そしてこの探究は、社会に出てからも続いていきます。
自分の関心をもとに、どう工夫して仕事を意味付けられるかが、やりがいや納得感に繋がるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:「仕事に意味を見いだす」という視点は、これまであまり意識してこなかったかもしれません。
田澤教授:もちろん、劣悪な労働環境であればまずは改善が優先されるべきです。
ただし、それと並行して「自分の仕事をどう捉えるか」という視点を持っていないと、何をしてもつまらなく感じてしまうという可能性もあります。
自分なりの工夫や視点があることで、日々の経験はもっと豊かになるはずです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。日々の行動に対して、自分なりの考えを持ち続けること。そして、それを習慣として育てていくことが重要なのですね。
田澤教授:その通りです。自分の行動や選択に対して、どんな意味があるのかを考えるということは、社会との関わり方そのものでもあります。
この「自分事として捉える力」を学生時代のうちに授業や卒論、インターンなどを通じて育てていくことを、大学生の方には重視していただきたいですね。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。「自分事として捉える力」「社会に対する眼差し」は、キャリア教育や学生自身の姿勢によって育まれる部分が多いとは思いますが、やはり家庭の影響もありますよね。
実際、若者のキャリア形成において家庭が担うべき役割などはあるのでしょうか?
田澤教授:これは子どもの年齢によっても変わってくる点ですね。
例えば小学生の段階では、保護者参観や学校行事、PTA活動などを通じて、子ども自身よりも保護者の方が学校(=社会)と関わる機会があります。
そして、これが中学・高校になると保護者だけではなく、子ども自身も部活動や地域活動に関わったり、「総合的な探究の時間」で地域の課題を調べたりと、社会との接点がより広がっていくでしょう。
その時、家庭としての関わり方には大きく2つの視点があると思います。
1つは「自分の子どもに対してどう接するか」、もう1つは「地域の大人として、その世代の子どもたちに何を伝えるか」ということです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:1つ目は何となく分かるのですが、2つ目はどういうことでしょうか?
田澤教授:例えば大学生や高校生が、地元の課題をテーマに探究活動を行ったり、地域の企業や施設でインターンやインタビューをしたりする場面がありますよね。
そういった時に、地域の大人が自分の経験や仕事、地域のことを丁寧に説明してあげる。これは「地域の大人」として、その世代の若者に社会への眼差しを伝える貴重な機会になります。
自分の子どもに限らず、同じ世代の子どもたちに対して、社会との関わり方を共有するというのは、キャリア教育の実践の1つと言えるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。社会人としての経験をもとに、身近な大人が地域や社会の一面を伝える機会になるのですね!
田澤教授:その通りです。一方、家庭内での関わり方となると、少し内容が変わってきます。
例えば、小さい頃であれば、お小遣い帳をつけるとか、外食で料理の値段を一緒に見てみるといったことも、良いきっかけになります。
あるいは、夕食の買い物を一緒にして、「これ、思ったより高かったね」「レシートこんなに長くなったね」なんて話すのもおすすめです。
それだけでも、「お金がどういう風に使われているのか」という流れや「お金の価値」は自然につかめます。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、子どもの頃はレシートが長いと面白がっていた記憶があります。そういう経験の中で、お金についての感覚が少しずつ育っていったのかもしれませんね。
田澤教授:そう思います。とはいえ、「家計について心配させたくない」と考える親御さんも多いのではないでしょうか。そうした思いから、つい「そんなことは気にしなくていい」と言ってしまう場合もあるかもしれません。
しかし、いつかはお金の大切さや価値について、伝えるタイミングがやってくるはずです。
とはいえ、いきなり「今日からお金の話をするよ」と言っても、子どもは構えてしまいますよね。だからこそ、日常の中でタイミングを見ながら少しずつ伝えることが大切なのです。
また、「これだけお金をかけているんだから頑張れ」という言い方では、かえって反発を招いてしまいます。押しつけではない形で、お金の価値を伝えていく工夫も必要だと思いますよ。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。堅い話を真面目に長く続けるよりも、旅行などのちょっと特別なシーンで、さりげなく話してもらえた方が印象に残る気がします。
田澤教授:はい。そして、そこから先はもう家庭ごとの自由で構いません。
「この金額を稼ぐために何時間働いている」と伝えても良いですし、言いたくなければ無理に言う必要もありません。
繰り返しになりますが、大切なのは、あくまで日常生活の中で自然に話せる機会を持つことです。
よく「親は自分の仕事について子どもに語りましょう」といったことも言われますが、現実には難しい部分もあります。子どもが興味を示さなかったり、「うちはお金がないの?」といった話にすり替わってしまったりする場合もありますからね。
だからこそ、家庭内での関わり方は、常にバランスが重要になるのです。
カードローンの窓口合同会社 編集部:ありがとうございます。ここまでは、小中学生との家庭での関わりについてお話しいただきましたが、大学生になると関わり方もまた変わってきそうですね。
田澤教授:おっしゃる通りです。そもそもの話、親世代が学生だった頃と今とでは、社会の状況が大きく異なっています。
子どもが大学生になると、「自分の時はこうだった」と言いたくなる気持ちもあるかもしれませんが、そこはぐっと堪えることも大切です。
「お金は出して、口は出すな」という極端な言葉がありますが、ある意味で的を射ていると思います。
大学生活はもちろん、就職活動にも相応の費用がかかりますし、その時期はアルバイトも難しくなることがありますから、親が経済的に支えつつ、少し距離を置いて見守るのがちょうど良いのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、精神的に負荷のかかる就職活動中に「自分の時はこうだった」と言われると、アドバイスというよりプレッシャーに感じてしまうかもしれません。
田澤教授:はい。そうですね。学校や就活、あるいは企業で思うようにいかないことは多々あると思います。そんな中で、家庭でも同じような指摘をされてしまうと、学生は逃げ場を失ってしまいます。
だからこそ、大学生にとって家庭は「最後の砦」であってほしいと願っています。
この言い方は、親にとって負担が大きいかもしれませんが、落ち込んで帰ってきたときに「大変だったね」と一言かけてもらえる場所であることが、本人にとっては何よりの支えになるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:大学生になると一人暮らしの人も増えますから、そんな時に「話せる場所」があるだけで救われることはありますよね。
田澤教授:本当にその通りですね。実際、新社会人になってからも、会社の悩みや不安を親にだけは話せるという人も少なくありません。
上司や同僚には言えないけれど、親になら話せる──そういった存在であることは、思っている以上に大きな意味を持ちます。
とはいえ、親の側もつい「気にするな」「大丈夫」と言ってしまいがちです。
しかし、その時々の悩みは、本人にしか分からないものです。だからこそ、まずは静かに耳を傾け、助けを求められた時にアドバイスをするくらいの距離感を意識してほしいと思います。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。難しいことではありますが、まずは子どもの心に寄り添う姿勢が求められているという認識でしょうか?
田澤教授:はい。ただし、「寄り添いましょう」「歩み寄りましょう」と言っても、タイミングが合わなければ逆効果になることもあります。
だからこそ、「お金は出して、口は出すな」という姿勢は、ある種の理想形とも言えます。
もう少し踏み込んで表現すれば、「子どもを信じて見守り、必要な時にお金とアドバイスをそっと差し出す」というスタンスが、ちょうど良い関わり方なのではないでしょうか。
家庭でできるキャリア支援の具体的な方法と親へのアドバイス
カードローンの窓口合同会社 編集部:田澤様もお子様がいらっしゃるとのことで、ここからは少しご自身のご経験についてもお伺いできればと思います。
例えば、子どもとの距離感や、子育てに伴うストレスとの向き合い方について、日頃から意識されていることや理想とされている関わり方があれば教えていただけますか?
田澤教授:正直なところ、私自身も模索している最中です。完璧にできているとは思っていませんし、むしろアドバイスをいただきたいくらいですよ。
それでも、1つ大切にしていると感じているのは、「子どもの発達段階を理解する」という視点です。
現在、私の子どもは小学生で、まさに「強めの反抗期」に差しかかっています。以前は素直に応じてくれていたのに、最近では寝る時間を守らなかったり、宿題を嫌がったりと、小さな衝突が日常的に増えてきました。
このような時に、父親と母親の両方から同時に注意や指摘を受けると、子どもにとっては逃げ場がなくなってしまうのです。
実際に、我が家でもそういった行き詰まりを経験したことがあります。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、親の善意や心配が、かえって子どもにとってはプレッシャーになる場面もありますよね。特に反抗期はその傾向が強くなるのかもしれません。
田澤教授:そうですね。例えば、母親が子どもに教えている様子を父親が見て「そのやり方は違うのでは」と口を挟んでしまうと、家庭内の空気が悪くなってしまうこともあります。
私自身もそうした失敗を経験し、それ以来「役割を分ける」ということを意識するようになりました。
これは、どちらかが積極的に関わっているときには、もう一方は少し距離を置くという意味です。
例えば、子どもがどちらかの親とぶつかった直後に、もう片方がさりげなくフォローにまわるという関わり方が理想だと感じています。ぶつかる場面がある以上、同時に逃げ場を作るという意識が必要なのです。
もちろん、家庭の事情は様々ですし、条件が異なることもあります。同じようにできるとは限りません。
ただ、「追い詰めない姿勢」を意識するのは、どのような家庭環境でも共通して大切なことではないかと考えています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:なるほど。どちらか一方に役割が偏らないよう配慮しながら、子どもが安心して成長できるよう、適切な「逃げ道」を用意することが大切なのですね。
田澤教授:はい。子どもは成長に伴って、心身ともに大きく変化していきます。それに伴い、以前は通じていた関わり方がうまくいかなくなる場面も出てくるでしょう。
そうした時、「どうして言うことを聞いてくれないのか」と苛立ちを感じるのは、親として自然なことだと思います。
ただ、そこで1つ意識していただきたいのが、それもまた「子どもが成長している証」である、という視点です。
その成長に合わせて、親としての関わり方を少しずつ変化させ、最終的には「見守る姿勢」へと移っていくことが求められるのではないでしょうか。
カードローンの窓口合同会社 編集部:見守るというのは、簡単なようでとても難しいですね。大人には経験がある分、どうしても口を出したくなってしまう場面も多いと感じます。
田澤教授:そのお気持ちはよく分かります。ですから、もし「ここだけは譲れない」という部分があるのであれば、それはしっかり伝えて良いと思います。
たとえぶつかることがあったとしても、それだけは守ってほしいという願いがあるなら、真剣に伝えるべきでしょう。
ただし、そうした“譲れない部分”が多すぎると、子どもにとっては逃げ場がなくなってしまいますし、親自身もストレスを抱え込みやすくなってしまいます。
だからこそ、「近付きすぎれば衝突もある」「ぶつかった後は調整する」、そうした繰り返しを丁寧に積み重ねていく姿勢が大切だと感じています。
カードローンの窓口合同会社 編集部:たしかに、まったく衝突のない家庭というのは、むしろ不自然かもしれませんね。家族とはいえ、一人ひとりが異なる価値観を持つ人間なのですから。
田澤教授:まさにその通りです。ですので、衝突を一概に「悪いこと」と捉えるのではなく、その後どう調整していくか、どう理解を深め合うかを考えることが大切です。
私自身も、まだまだ手探りの状態で子育てを続けています。
ただ、理想を語るだけではなく、現実の中でどう折り合いをつけ、工夫して向き合っていくか。その試行錯誤を家族全体で共有しながら積み重ねていくことが、「家族」というものを支える土台になるのではないかと感じています。
取材・記事執筆:カードローンの窓口合同会社 編集部
取材日:2025年7月14日

